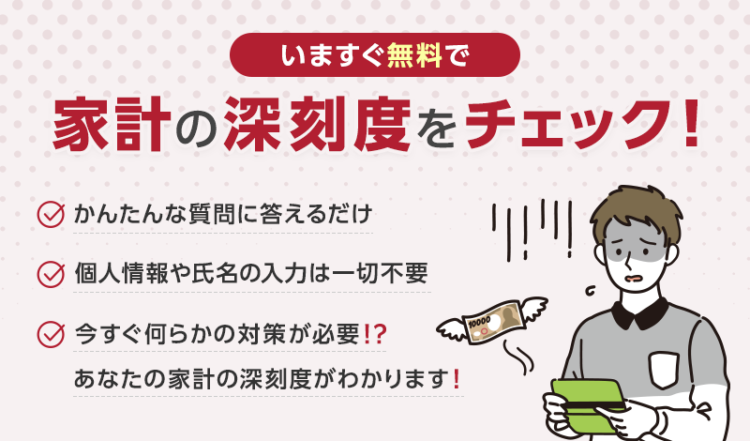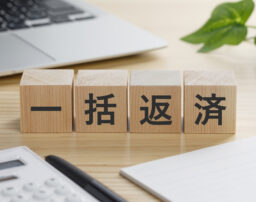「借金あるけど生活保護を受けられる?借金はどうしたらいい?不動産はどうなる?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
結論からすれば、借金があっても基本的に生活保護を受けることはできます。
また、生活保護を受けている間、取り得る債務整理の手段は、基本的には自己破産手続き(原則全ての支払義務が免除)になります。
生活保護で受け取ることのできる金額は、最低限度の生活を維持するための額であり、そこから返済していくことは困難だからです(また、生活保護の受給中に借金を返済をしていることが発覚すると「返済に回すお金があるということは、生活保護は不要なのでは」と判断され、生活保護が打ち切られてしまうリスクもあります)。
一定の条件を満たせば生活保護を受けても、居住している不動産を維持できますが、なかには不動産を売却するよう指導を受ける場合もあります。
今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。
- 生活保護の概要
- 生活保護の4要件
- 生活保護を受けるまでの流れ
- 不動産売却の指導
- 生活保護を受けている場合の債務整理
生活保護とは?
生活保護の目的は、国が、生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することです(生活保護法1条)。
生活保護法には、次の4つの基本理念があります。
- 国家責任の原理
- 無差別平等の原理
- 最低生活保障の原理
- 保護の補足性の原理
あらゆる手を尽くしても最低限度の生活を維持できない場合には、国家の責任として(1.)、生活が困窮するに至った理由を問わずに(2.)、生活保護費を支給することとなります。
保障されるのは、健康で文化的な最低限度の生活です(3.)。また、支給される金額は、本人が資産や能力、その他の法律上の給付などを活用しても足りない金額です(4.)。
参考:生活保護制度とは(1) 保護の目的、原理と原則|旭川市
借金があっても生活保護は受けられる?生活保護の4要件
生活保護費を受給するにあたって借金があるかは問われません。
そのため、借金があっても、今回お伝えする条件を満たす限り、基本的に生活保護を受給できます。
生活保護費の申請は世帯単位で行われるため、世帯全員が受給の条件を満たす必要があります。
生活保護費を受給するための主な要件は、次の4つです。
- すでに自身が持っている資産を活用している状況であること
- 働けない/働いても、「最低生活費」分の収入を得られない状況であること
- 親戚や親族からの援助が受けられない/受けても、「最低生活費」分の収入が得られない状況であること
- 年金や手当など、他の制度を利用しても「最低生活費」分の収入が得られない状況であること
それぞれについてご説明します。
参考:生活保護制度|厚生労働省
(1)すでに自身が持っている資産を活用している状況である
生活保護費を受給するための1つめの要件が、すでに自身が持っている資産を活用している状況であることです。
生活保護法4条1項では、保護の補足性の原理に関して次のように定められています。
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
引用:生活保護法4条1項
もし現金や預貯金、有価証券、車、不動産といった資産を持っているのであれば、生活保護を受給するにあたって、売却を含めて検討し、売却できるのであればその代金を生活費に充てなければなりません。
例外的に自家用車は、交通のアクセスが不便なところで仕事のために利用する必要があるなどの事情があれば、手元に残しておける可能性があります。
また不動産も後述のように、生活に利用しているなどで一定の場合には保有し続けられる可能性があります。
(2)働けない/働いていても「最低生活費」分の収入を得ることができない状況である
生活保護費を受給するための2つめの要件が、働けないか、働いていても「最低生活費」(※)分の収入を得ることができない状況であることです。
※最低生活費(生活扶助基準額)とは、住んでいる地域などを元に決まる、生活保護の受給金額の基準です。
計算方法については、こちらをご覧ください。
参考:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)|厚生労働省
健康状態が良好で働く能力があれば、働かなくてはいけません(能力の活用、生活保護法4条1項)。
「働きたくない」との理由で、働かずに生活保護を受給することはできません。
(3)親戚や親族からの援助が受けられない/受けていても、「最低生活費」分の収入が得られない状況である
生活保護費を受給するための3つめの要件が、親戚や親族からの援助が受けられないか、受けられても最低生活費分の収入を得られない状況であることです。
生活保護法4条2項では、保護の補足性の原理に関して次のように定められています。
民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
引用:生活保護法4条2項
生活保護費を支給する前に、市(区)役所は扶助義務者に援助を依頼する通知(いわゆる扶養照会)を送ります。
そして、親族による十分な援助を受けられると判断されると、生活保護費は支給されません。
もっとも、厚生労働省は、2021年2月26日に制度を見直す通達を発して、次のいずれかに該当する場合には、扶養照会をする必要はないとしています。
引用:扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について│厚生労働省
- 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫など)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者など
- 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない(例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい関係不良の場合等が想定される。なお、当該扶養義務者と一定期間(例えば10年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合は、著しい関係不良とみなしてよい)。
- 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等)
(4)年金や手当など、他の制度を利用しても「最低生活費」分の収入が得られない状況である
生活保護費を受給するための4つめの要件が、年金や手当などの他の制度を利用しても最低生活費分の収入を得られない状況であることです。
他の制度で給付を受けられる場合には、まずそれらの制度を利用し、それでも収入が最低生活費に満たない場合に不足分を生活保護で受給できることとなります(生活保護法4条2項)。
生活保護の受給方法

生活保護の申請から受給までの流れは、通常次のようになります。
事前の相談
保護の申請と調査
受給開始
それぞれについて説明します。
生活保護の申請から受給可否の結果が出るまで、原則14日以内とされています(生活保護法24条5項、やむを得ない事情がある場合などでも最長で30日)。
不正受給をした場合には、最大で不正受給分の140%分を支払わなければならないこともある(生活保護法78条1項)ので、今の状況を福祉事務所に正直に話すようにしてください。
(1)事前の相談

まずお住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当窓口へ相談に行きましょう(お住まいの地域の管轄に福祉事務所が設置されていない場合には、町村役場で手続きを行います)。
なお決まった住居がない場合には、最寄りの福祉事務所から申請します。
その際、できるだけ持っていきたい書類は次のようなものです。
- 身分証
- 給与明細
- 通帳
- 年金・障がい者手帳
- 診断書 など、自分の現状を説明できるもの
事前相談では、次のようなことについて説明を受けることとなります。
- 生活保護制度の概要
- 生活福祉資金や各種社会保障施策等の活用
もし体調が悪く直接福祉事務所に行けないのであれば、生活保護の申請業務を担当する福祉事務所の職員(ケースワーカー)に自宅を訪問してくれるように連絡してみましょう。
参考:「生活保護制度」に関するQ&A|厚生労働省
参考:福祉事務所|厚生労働省
(2)保護の申請と調査
事前相談の次に、福祉事務所に備え付けてある申請書に必要事項を記載して、窓口に提出します。
生活保護の要件を満たすかについて、次のような点についての調査が行われます。
- 就労の可能性、収入
- 預貯金、保険、不動産等の資産
- 年金などの社会保障給付
- 親族による仕送り等の援助の可否(仕送りの意思があるかの確認) など…
必要に応じて、福祉事務所の担当者が自宅を訪問(生活状況等を把握するための実地調査)することもあるので、調査に協力しましょう。
(3)受給開始
調査の結果、生活保護費の支給が相当であると判断されると、受給開始となります。生活保護の受給中に収入などに変動があった場合は、すみやかに届出を行う必要があります(生活保護法61条)。
生活保護費の受給中は、収入の状況を定期的に申告することを求められるのが基本です。
また、福祉事務所のケースワーカーが年数回程度訪問調査を行い、就労に向けた助言や指導を行うことがあります(生活保護法28条1項)。
その指導が不当なものでない限り、受給者は原則として従わなければなりません。
生活保護申請で不動産売却の指導を受けるのはどんなケース?
不動産については、売却することが原則ですが、生活保護費を受給するとしても、生活保護費を受けようとする世帯が暮らすためのものであれば、家屋やその家屋の土地はそのまま保有することができる可能性はあります。
一方、次のような場合には不動産売却の指導を受けることもあります。
- 居住用の家屋や土地であっても、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合
処分するかどうかを決めるにあたっては、生活扶助基準となる金額等をベースに、当該地域の住民意識や処分の可能性などが考慮されます。また、住宅ローンの返済が残っているケースでは、不動産の売却を求められることが多い傾向にあります。
また、このような考慮事項からであれば保有を認めてもらえそうな場合であっても、不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)を利用することができるのであれば、そもそも生活保護費を受給できない可能性があります。
不動産担保型生活資金とは、不動産を担保にして生活資金を借り入れることです。
生活保護受給中に不動産を相続したら?
生活保護受給者は、相続により、価値のある財産を受け継ごうとしている場合、それを拒否すること(相続放棄)は原則としてできません。
生活保護費は生きるための最終手段なので、他に財産を得られるのであれば、その財産を活用するべきだと考えられているからです(先ほど出てきた「資産の活用」です)。
そのため、不動産を相続した場合には、それを売却するのか居住するのかをケースワーカーと相談することになります。もし相続財産により、ある程度の期間自力で生活することができるのであれば、生活保護は一旦「停止」や「廃止」などになる可能性が高いです。
相続したのにそれを報告せずに生活保護費を受給していると、場合によっては受給した生活保護費の範囲内で、生活保護費の返還を求められることになりかねません(生活保護法63条)。
注意すべきなのが、被相続人が価値のある財産よりも借金など負債を多く抱えていた場合です。この場合には、相続放棄をすることができる可能性が高いので、被相続人の財産をしっかりと調査して、不動産や預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産はそれぞれいくらあるのかを見極めましょう。
相続放棄について、詳しくはこちらをご覧ください。
生活保護の受給と利用できる債務整理
生活保護受給前の借金について解決するためには、自己破産の手続きをするという選択が考えられます。
それでは、自己破産の手続きの概要や、費用を工面できない場合の対処法をご説明します。
自己破産
「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、そのうえで、原則全ての借金の支払義務を免除してもらう(免責許可決定)手続きです。
債務整理には、自己破産のほかに民事再生と任意整理があります。
しかし、民事再生も任意整理も、基本的には数年間返済し続けることになる手続きです。
生活保護の受給中に民事再生や任意整理の返済をしていることが発覚すれば、「返済に回すお金があるということは、実は生活に余裕があるのではないか」と、不正受給を疑われたり、生活保護が打ち切られてしまうなどのリスクがあります。
そのため、生活保護受給者が採りうる債務整理は基本的に自己破産に限られてくることになります。
法テラスの利用を検討する
法テラスとは、全国どこでも、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して設立された公的な法人です。法テラスの弁護士費用等の立替制度を利用することで、例えば月5000円など、分割で支払いをすることができます。
生活保護受給者であれば、費用の支払いが免除されることもあります。
東京都内や大阪に住んでいる方が法テラスを利用できる収入基準は以下のとおりです。
| 世帯人数 | 手取り月収 |
|---|---|
| 1人暮らし | 20万200円以下 |
| 2人暮らし | 27万6100円以下 |
| 3人暮らし | 29万9200円以下 |
※家賃や住宅ローンを利用している場合には、限度額がいくらか増額します。
※収入基準のほか、資産基準も満たす必要があります。
参照:費用を立て替えてもらいたい|日本司法支援センター 法テラス
ご自身が法テラスを利用できるかはこちらからチェックしてください。
自己破産の手続きにかかる費用について、詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】借金をしていても、生活保護を受けられる可能性はある!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 生活保護とは、国が、生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度
- 生活保護費を受給するための主な要件は、次の4つ。
- すでに自身が持っている資産を活用している状況であること
- 働けない/働いても、「最低生活費」分の収入を得られない状況であること
- 親戚や親族からの援助が受けられない/受けても、「最低生活費」分の収入が得られない状況であること
- 年金や手当など、他の制度を利用しても「最低生活費」分の収入が得られない状況であること
→これらを満たしていれば、借金があるからといって生活保護費を受給できないわけではない。
- 生活保護を受けるまでの流れは、通常次のようになる。
事前の相談→保護の申請と調査→受給開始
- 生活保護を受けるとしても、居住用の家屋は手放さずに済む可能性がある。もっとも、その家屋の処分価値が利用価値に比して著しく大きい場合などには、不動産売却の指導を受けるケースもある。
- 生活保護以前に抱えた借金については、自己破産を検討することがおすすめ
生活保護を受給できないか検討中で、現在借金を抱えているという方は、法テラスなどを通じて自己破産を利用できないかご検討ください。