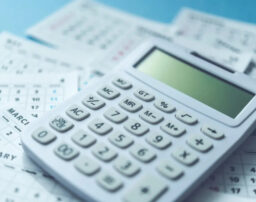昔の借金について「もしかしたら時効じゃないの?時効援用は自分でできるの?」とお考えかもしれません。
しかし、時効援用は単に時間が経過しただけではできず、あなたからの意思表示が必要になります。また、時効援用には失敗してしまうケースもあります。
時効援用を失敗しないようにするために、失敗例や成功のコツを押さえておきましょう。
この記事を読んでわかること
- 時効とは
- 時効援用の失敗例と成功のコツ
- 時効援用の失敗した場合の対処法
ここを押さえればOK!
時効が成立するためには「時効の援用」が必要です。これは時効を主張する意思表示を行うことで、初めて権利が消滅します。例えば、借金の返済期限から5年経過した場合でも、借りた側が時効を主張しない限り、返済義務は残ります。時効援用の失敗例としては、時効期間の誤解や口頭での援用、債務の承認などが挙げられます。これらの失敗を避けるためには、時効援用通知書を内容証明郵便で送るなどの手続きが推奨されます。
借金問題に直面している方は、弁護士が最適な解決方法を見つけるお手伝いをしますので、アディーレ法律事務所に一度ご相談ください。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
時効とは
時効とは、権利を行使できる状態だったのに権利を行使しなかった結果、権利を失うことを定めた制度です(民法166条)。法律の世界では、「消滅時効」といいます。
そして、次の期間の短い方で、権利が時効によって消滅する可能性があります。
- 権利の発生原因や権利行使の相手方などを知った時から5年間
- 権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時から10年間
例えば、お金の貸し借りで考えてみましょう。
この場合、通常、お金を貸した人がお金を貸した事実(権利の発生原因)やお金を借りた人を知らないはずはありません。そのため、「1か月後にお金を返して」と約束していた場合には、お金を貸してから1か月経った日から5年間経つと、時効が成立してしまう可能性があります。
時効の成立には、裁判や支払督促、催告などが行われていないことも必要です。時効期間が経過していても、債権者が裁判などの法的手続をとった場合には、後で説明するように時効の進行がいったん停止したり、リセットしたりすることがあります。
いつお金を借りたかで時効の期間が変わる!?
2020年3月31日以前にお金を借りたかどうかで時効の期間が変わる可能性があります。
どういうことかというと、2020年4月1日から改正民法が施行され、消費貸借契約の締結時期(お金を借りた時点)がいつかによって改正民法か旧民法どちらが適用されるかが変わってしまうのです。
基本的には、2020年3月31日以前に消費貸借契約を締結した場合には旧民法が、2020年4月1日以降に消費貸借契約を締結した場合には新民法が適用されます。
| 借金の消滅時効 | ||
| 2020年4月1日より前の借金 | 個人から借りた場合 | 貸主が権利を行使できる時から10年 |
| 金融機関から借りた場合 | 貸主が権利を行使できる時から5年 | |
| 2020年4月1日以降の借金 | 貸主が権利を行使することをできることを知った時から5年 (又は権利を行使できる時から10年のうちの、早い方) | |
時効の援用とは
時効の期間が経過したら、すぐに時効が成立するわけではありません。当事者が「時効による利益を受ける」旨の意思表示をして、初めて時効が成立します(民法145条)。
この意思表示を「時効の援用」といいます。
例えば、仮称Aさんが仮称Bさんにお金を貸し、お金を返すべき日から5年が経過した場合を考えてみましょう。
この場合、5年を経過したからといって、時効が成立し、BさんはAさんにお金を返さなくてもいいというわけではありません。Bさんがお金を返さずに済むためには、あくまでもBさんからAさんに対し「5年過ぎたので、時効を理由に払いません」と伝える必要があるのです。
このように、Bさんが時効の援用をして、はじめてAさんはお金の回収を諦めざるを得なくなるのです。
もっとも長期間返済を求められていない状態で、「そろそろ時効が完成したかな」とお金を借りた側から連絡をする必要はないでしょう。基本的には、「お金を返して」と言われたときに支払いを拒む理由として、時効の援用を行います。
時効援用の失敗例と失敗を回避するコツとは
ここでは、時効援用の失敗例とその失敗を回避するコツについて紹介します。
(1)失敗例1:時効期間を誤解していた
時効援用における最も一般的な失敗の一つは、時効期間を正確に理解していないことです。例えば、時効が始まる日を間違えた、時効期間を間違えたなどです。
特に、時効期間はリセットされたり、先延ばしにされたりした場合には注意が必要です。この場合、「お金を返すべき日から5年」と思っていても、実は時効の期間がリセットされていたというケースも多くあります。
例えば、お金を貸した側から次のような行為があった場合には、時効の完成が一時的にストップし、先延ばしされる(時効の完成猶予)ことになります。
- 裁判上の請求、支払督促、調停、破産手続参加など(民法147条)
- 強制執行、担保権の実行など(民法148条)
- 仮差押え、仮処分(民法149条)
- 催告(お金の支払いを請求する通知)(民法150条)
- 協議を行う旨の合意(民法151条)
例えば、催告(お金の支払いを請求する通知)があった場合には、催告があったときから6ヶ月経過するまで時効の期間が先延ばしにされることになります。
時効援用を失敗しないためには、時効期間が変わる事情がなかったか確認するようにしましょう。時効期間を誤解していると時効援用を失敗してしまいます。
(2)失敗例2:時効の援用を口頭でしてしまった
時効援用は、電話などで口頭で行うことができます。しかし、口頭では言った・言わないの水掛け論になってしまうおそれがあります。
例えば、あなたとしては「時効援用」を相手に言ったつもりでも、相手からは「支払う約束をしてくれた」と主張されてしまい、トラブルになってしまうのです。
そこで、時効を援用する場合には、内容証明郵便にて「時効援用通知書」を発送します。時効援用通知書とは、成立した時効を援用する旨の通知書のことです。
(3)失敗例3:支払うと約束してしまった
時効援用を行う前に、債務を認める行為(承認)を行ってしまうと、時効が中断されてしまいます。例えば、債権者に対して一部の返済を行ったり、返済計画を話し合ったりすると、時効期間がリセットされます。
時効の援用をするつもりで電話をしたのに、うまく言いくるめられてなぜか支払うと約束してしまう(債務の承認をしてしまう)というケースは実際に起こりえます。そうなると、時効期間が経過していても、時効期間がリセット(更新)されてしまい、時効の援用ができなくなります。
例えば、次のような発言をしてしまうと、「債務の承認」として時効期間がリセットされてしまう可能性があります。
- 全額または一部の金額を返済してしまう
- 「返済する」と連絡あるいは約束してしまう
- 返済期限の延長を求める
時効援用を失敗しないようにするには、お金を貸す側とのやりとりは慎重に行わなければなりません。
債務の承認のほかにも、他にも時効期間がリセットされる事由としては次のようなものがあります。
- 判決や裁判上の和解などによって権利が確定したとき
- 強制執行、担保権の実行などが終了したとき
例えば、時効の完成されるまえに、裁判を起こされた場合を考えてみましょう。この場合、訴えの提起で時効時期が先延ばし(時効の完成猶予)がされ、判決確定により、時効がリセット(更新)されることになります。
このように時効期間はケースバイケースで変わってきます。時効援用を失敗しないためには、弁護士などの専門家に相談してみるのがよいでしょう。
時効の援用に失敗した場合の対処法とは
時効援用に失敗してしまったら、他に支払いを免れられる理由のない限り、その請求されたお金(借金の元金+利息+遅延損害金)を支払わなければなりません。
請求金額を支払えない場合には、弁護士に債務整理を依頼することを検討することをおすすめします。債務整理をすることで、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることができる可能性があります。
債務整理には、基本的に任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産の3種類があります。
- 任意整理:利息のカットや原則3年間(場合によっては5年間)の長期分割払いの交渉をと行い、毎月の返済の負担を減らす手続
- 民事再生(個人再生):裁判所の認可のもとで住宅などの財産を維持したまま(※)、大幅に減額された借金を3年~5年で返済していく手続
- 自己破産:財産がないために支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上借金の支払義務を免除してもらう手続
※ 住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。
「自己破産すると人生の終わり」と考え、借金問題の解決に踏み出せない方もいらっしゃると思います。しかし、借金問題の解決は自己破産だけではありません。任意整理や個人再生といった手続きがあります。
また自己破産することになっても人生が終わるということはありません。むしろ人生を前向きなものにするための法的な手続なのです。
債務整理に興味がわいた方は、弁護士へご相談ください。あなたの借金問題を解決に一番適した方法を考えてくれます。また、弁護士へ依頼すると、難しい手続きも代わりにやってくれますので、失敗するリスクがありません。
【まとめ】時効援用は期間に注意!失敗を防ぐには弁護士へ相談を
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 時効援用の失敗例と回避策
- 失敗例1:時効期間を誤解➡時効期間が変わる事情を確認
- 失敗例2:口頭で時効援用➡内容証明郵便で通知書を送付
- 失敗例3:債務を認める行為(承認)➡債務を認める発言や行為を避ける
- 時効援用に失敗した場合には、請求された借金の元金、利息、遅延損害金を支払う可能性があります。お金が払えないという場合には、弁護士に相談して債務整理(任意整理・民事再生(個人再生)・自己破産)を検討しましょう。
長い間返済しておらず、連絡もなかった業者から突然督促されたときは、時効援用が可能かもしれません。
時効援用は専門家に頼らなくても行うことができますが、自己判断での手続はトラブルのもとです。連絡があっても、「わかりました、返します」というようなことは言わずに、弁護士に借金について時効援用が可能か相談するようにしましょう。
また、アディーレ法律事務所では、債務整理手続きを扱っております。アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております(※2025年3月時点)。
時効援用や債務整理に興味がある方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。