未成年の子がいる場合、離婚の際に夫婦のうちどちらが親権者になるのか決めなければなりません。
実際のところ、母親が親権者になるケースが多いのですが、父親が親権者になるケースもないわけではありません。
親権者の決定には、考慮される項目があります。
そのため、親権を獲得したいと考えているのであれば、あらかじめこの項目について知っておくことで、親権者を決める際の話し合いを少しでも有利に進めることができるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 父親(夫)が親権を獲得しにくい理由
- 夫が親権を得るにはどうすべきか
親権とは?
親権とは、「身上監護権」と「財産管理権」の2つの権利義務から成り立っています。
身上監護権とは、未熟な子どもを心身ともに健全な大人に養育するために認められる権利義務のことをいいます。例えば、親権者は、子どもと一緒に住み、日々子どもを養育し、ほめたり叱ったりして教育することで身上監護権を行使していることになります。
一方、財産管理権とは、子どもの財産を保護するため、子どもの法律行為の代理権や同意権を有しており、子どもの財産を管理する権利義務のことをいいます。例えば、親権者は子どもの財産に関する契約など、法律行為を代理することができます。
子ども自身が財産を持っているケースは多くはありませんが、祖父母等からの贈与・相続により得られた財産などが想定されています。
夫が親権を獲得しにくい理由とは?
親権獲得の問題ですが、やはり、母親の方が離婚時の親権獲得に有利であるというイメージがあります。
それは、なぜなのでしょうか?
一般的に、親権者決定の際に母親が有利になりやすい理由をご紹介します。
(1)母性を重視する傾向がある(母性優先の原則)

子どもにとって母親は不可欠であり、特に乳幼児の場合には親権者は母親にした方が望ましいという考え方があります。
これは、子の監護養育に関する考え方の一つであって、母性優先の原則といわれます。
これまでは、父親は家の外で仕事をし、母親は家で子育てをする、という家庭が多かったことから、ほとんどの場合、母親が親権者とされていました。
現在でも、主として母親が子を監護している家庭は多いですが、価値観の多様化と共に、家庭のあり方も多様化しており、主に育児を担っているのが父親である家庭も増えてきています。
そのため、親権者を父母のいずれとすべきかについては、必ずしも生物学上の母親を優先するのではなく、子の具体的な監護状況や子との精神的・情緒的な結びつきの程度などから、慎重に判断すべきであるとされています。
ただし、子どもが小さければ小さいほど、この原則が重視される傾向にあります。この原則によって、親権争いでは、一般的に母親よりも父親の方が不利になっていますが、常に母親が親権を得るとは限りません。
例えば、母親が何らかの理由で(病気、愛情の欠落、性格の問題等)子どもの世話してこなかったのであれば、これまで主体的に子どもの世話をしてきた父親が有利になることもあります。
(2)育児に時間をかけられることが多い
子どもが幼ければ幼いほど、女性は産休育休を取得するなどして育児に時間を費やしています。一方で、男性の多くがフルタイムで働いており、女性より育児にかけられる時間が短い傾向があるのが実情です。
親権者を決定する際には過去にどれだけ育児に貢献していたかが考慮されるため、離婚前は仕事に明け暮れており、ほとんど子どもと関わってこなかったような場合には、親権の獲得で不利になってしまうでしょう。
(3)前例にならう傾向が残っている
日本の裁判所は前例にならう傾向があるため、親権者を母親にすべきと判断するケースが多くなりがちです。
夫が親権を獲得するためのポイントとは?
昨今では、ライフワークバランスの考え方が広まったことから、子育てに主体的に参加する父親が増えたことから夫側が親権を獲得できるケースも以前と比較して増えてきています。
実際に親権を獲得するのに必要なのは、子どもの親権者にふさわしいといえることです。
(1)監護能力及び実績
育児に積極的に関わってきた実績と、今後とも養育にしっかり関わっていく意欲及び能力が考慮されます。
離婚後の監護能力としては、例えば、子育てにかけられる時間があるか、親族の協力が得られる見込みがあるか、子どもの病気の時などに柔軟に対応できるか、などが考慮されます。
監護の実績を主張するためには、今まで育児に積極的にかかわってきたことを示す客観的資料があると良いでしょう。
監護実績を証明する資料
次のような資料が、監護の実績についての証拠となり得ます。
実際に育児を主体的に行うと同時に、これらの証拠を保全しておくと良いでしょう。
- 母子健康手帳
同居中の監護者がちゃんと予防接種等を受けさせていたか、月齢に応じた健診をちゃんと受けているか、その健診時に問題がなかったか、問題を指摘されていたなら、それに対応していたか等を確認するために提出します。
- 診断書、お薬手帳
子供の健康状態の確認、及び子供の健康状態が良くないのであれば適した医療を受けさせていたかの確認が可能です。
- 保育園・幼稚園などとの連絡帳
- 学校の成績通知表
出席日数、休んだ場合の理由、子どもに関して気になるような内容の記載がないかの確認を行うことができます。
連絡帳には、送迎をどちらが行うかについても通常は記入欄があります。
- 写真、動画、音声記録
- 手紙、メール、SNSメッセージ記録
- 子の監護に関する陳述書
子どもの1日のスケジュール、そのスケジュールの中で誰がどう関わり合いを持っていたのか等を通じて、裁判所が子の生活状況を把握することが可能です。親の生活状況(仕事をしているなら、子どもの監護が必要な時間帯に帰宅しているか等)、親族などの監護補助者が継続的に手助けできるかなどの把握にも有効な場合があります。
子どもと過ごした記録や、子どもとの交信記録などは、今までの監護実績を示す証拠となりえます。
子どもと一緒に遊んだ際は、写真や動画を残すようにし、子どもとメールなどのやり取りをしているのであれば、それらを保存しておくと良いでしょう。
(2)子どもの意思
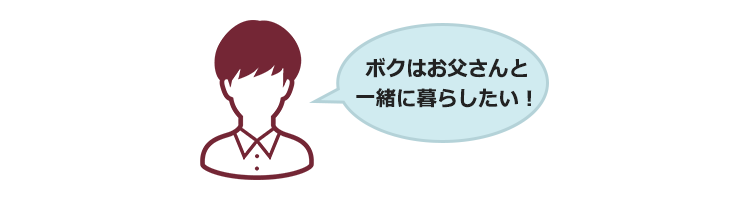
法律上、子どもが15歳以上の場合は子どもの意向を聞くことが義務となっています。また、15歳未満の場合でも、子どもが意思表示できる年齢に達していれば、その意思が尊重される傾向にあります。
子どもが幼少であれば、本人の意思より監護実績の方が重視される傾向があるので、具体的に育児を主体的に行うと同時に、先ほどご紹介したような証拠を確保しておくと良いでしょう。
(3)継続性の原則
子どもの生活環境がコロコロ変動してしまうのを避けるため、子どもの生活が落ち着いている場合は、現在子どもと同居している方が有利となります。
同居の他、引っ越しが不要など、子どもにとってこれまでと変わらない生活環境を用意できることも重要なポイントです。
継続性の原則の観点からとるべき行動
後に挙げる面会交流権も、継続性の原則に関連してきます。
また、子どもが一緒に暮らさない方の親と面会し続ける権利が重視されているため、相手方との面会に協力的であったことが親権獲得に優位に働いた裁判例(仙台高裁:平成15年2月27日)もあります。
もし、あなたが現在子どもと一緒に暮らしており、妻とは別居中なのであれば、妻と子どもの面会には協力的になった方が良いでしょう。(妻が子どもとの面会を望んでおり、子どもにとって悪影響があるなどの事情がない場合)
(4)経済的安定
経済的に豊かに生活ができることが、子どもの幸せにつながっていきます。
ただし、親権者の決定は養育費や児童手当などの福祉的給付もふまえて判断されます。
したがって、子どもの母親に収入が無かったり、少なかったりするからといって、それだけで多くの収入を得ている父親が有利になるとは限りません。
(5)面会交流への積極性
先ほども述べたように、面会交流権は子どもにとっても重要な権利であるため、面会交流に協力的であることは親権獲得に有利に働くことになります。
親権獲得時に考慮されないポイントとは?
親権獲得の決定の際には、判断のポイントになりそうな事柄でも直接考慮されない項目があります。
それが養育環境へ与える影響があれば、初めて考慮されることになります。
(1)離婚原因の有責性
不貞行為(いわゆる不倫)や暴力などが原因で離婚に至った場合でも、親権者を決定するにあたっては直接考慮されません。そのため、不貞行為や暴力をした側が親権者となることもあります。
親権者を決定するにあたっては、不貞行為のために子どもを外出させたのか、子どもが出かけている時に外出したのか、子どもの見ている前で暴力があったのか、子どもがいない時に暴力があったのかなど、不貞行為や暴力子どもへの影響が考慮されることになります。
ただし、子どもが暴力の被害を受けている場合や、DV加害者への拒否感を抱いている場合は、養育環境への影響があるとして直接的に不利になるでしょう。
(2)家事の実績
世間では「家事」と「育児」を一緒くたに考えることが多いですが、親権者の判断では明確に分けられることになります。
料理や洗濯などの家事をしないからといって、親権を得るのに不利とは限りません。たとえ母親が父親に対して料理をせず、父親の分の洗濯をしないとしても、子どもに対して食事や身の回りの世話などを行っていれば、育児をしていると考えられます。
ただし、子どもの食器を洗わない、不衛生な環境で生活させるなど、子どもの生活環境が脅かされるような状況の場合は、不利な要素となります。
父親が親権を獲得したい場合については、こちらの記事をご覧ください。
【まとめ】夫が親権を獲得するためには、監護能力や実績が大事!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 夫が親権を獲得しにくい理由としては、子どもにとって母親は不可欠であるという母性優先の原則や、男性の方が労働時間が長い傾向にあるという日本の労働環境、及び女性に親権を認めてきた前例が多いという前例主義によるものが考えられる
- 育児に積極的に関わってきた実績と、今後もしっかり関わっていく意欲及び能力
- 子どもの意思
- これまでと変わらない生活環境を用意できること
- 離婚の原因を作ったのはどちらか、ということは親権者をどちらにするかの判断のために直接は考慮されない
「育児は女性の仕事」といった性別による役割分担の意識は、以前に比べると大幅に薄れてきてはいますが、まだまだ離婚時の親権獲得においては妻に有利な状況です。とはいえ、個別の事情によっては夫が親権を獲得できる可能性が高いケースもありますので、親権を獲得したいとお悩みの方は、親権問題や離婚問題を取り扱っている弁護士にご相談ください。






















