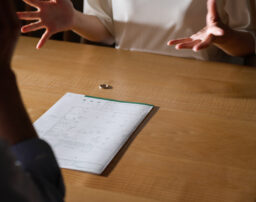離婚する夫婦は、通常、別居して別々に生活するようになりますが、何らかの理由で離婚後も同居を継続する夫婦もいます。
俗に、このような離婚後も同居する夫婦の状態を「離婚同居」という言葉で表されることがあるようです。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 離婚同居を選択する理由
- 離婚同居を選択した際に決めるべきルールや注意点
- 離婚同居に必要な手続き
ここを押さえればOK!
離婚同居のメリットには、子どもの精神的ダメージを抑えられる、生活環境の維持、周囲に離婚を知られにくい、生活費の分担、育児や家事の分担、復縁の可能性の維持、住宅ローンの返済中の住居維持などがあります。
一方で、離婚同居には注意点も存在します。偽装離婚と疑われるリスク、相手が同居をやめたくなる可能性、新たな恋愛や再婚の妨げ、ストレスの増加、扶養から外れることでの保険料負担の増加などが考えられます。
同居を継続する際には、生活費や家事分担のルール、同居期間などを明確に決めておくことが重要です。これにより後々のトラブルを避けることができます。離婚に際しては同居を続けるのか、親権者はどうするのか、財産分与はどうするのかなど夫婦で十分に話し合って決定することが求められます。
離婚問題でお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
自宅でらくらく「おうち相談」
「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」
アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!
離婚後も同居は可能?
婚姻中の夫婦は、民法上同居義務がありますが(民法752条)、離婚後の夫婦は、必ず別居しなければならないというルールはありません。
したがって、離婚後住居をどうするかについては、当事者が話し合って決めることになります。
離婚する夫婦の多くは、一方が出ていく形で別居します。同居していた家が広すぎたり、売却したりする場合には、双方が引っ越すこともあります。
また少数ではありますが、離婚後も同居を継続する元夫婦もいます。
離婚後も同居を継続するケースは、大きく次の二つに分かれますので、それぞれ説明します。
(1)単なる同居の場合
夫婦としての関係は解消しますが、すぐに引っ越し先を確保できないなどの理由で、単なる同居人として同居を継続する場合があります。
事実婚としての関係もありませんので、ルームシェアする同居人と変わりはなく、夫婦の協力扶助義務(民法752条)や婚姻費用を負担する義務も存在しません。
(2)内縁関係としての同居の場合
法律上の婚姻関係は離婚して解消したけれども、内縁関係は継続し、夫婦の実態を伴って同居を継続する場合があります。
内縁関係とは、双方が婚姻生活を送る意思を持ち夫婦として共同生活を送っているが、法律上の婚姻はしていない関係をいい、事実婚ともいいます。内縁関係の場合は、法律婚と同様に、夫婦の協力扶助義務や婚姻費用を負担する義務があります。
離婚同居を選択する理由(メリット)
離婚する多くの夫婦は離婚後別居しますが、離婚後も同居することを選ぶ夫婦も少数ですがいます。なぜ離婚後も同居するのでしょうか。離婚同居を選ぶ理由(メリット)には、次のようなものがあります。
(1)離婚による子どもへのダメージが少ない

子どもが幼い場合は、離婚により父母が別居する事実を理解できなかったり、理解しても精神的なダメージを負ってしまったりすることがあります。離婚同居は父と母どちらとも離れ離れにならずに済みますので、子どもが別居により精神的ダメージを受けることを抑えられる可能性があります。
また、離婚後遠方に引っ越すことになれば、子どもの転園・転校が必要になり子どもの生活環境も変わってしまいますが、離婚同居であれば子どもの生活環境を維持することができます。
(2)今まで通りの生活ができ離婚を周囲に知られずに済む
離婚後の夫婦の実態の有無にかかわらず、外形的には離婚後も同居を継続していますので、周囲には離婚したことが分かりにくいです。
また、引っ越しをする労力や費用も不要ですし、仕事や買い物、通院など、今までと同様の生活を送ることができます。
(3)住居費や家事育児を分担でき負担が軽くなる
一般的に、一人暮らしするよりも同居生活を送る方が、住居費や水道光熱費などの固定費を分担することができますので、一人当たりの生活費の負担は軽くなります。
また、離婚後別居すると、通常、親権を得た親が主に子どもと同居して子育てを担い、他方の親は養育費を支払って子どもには1ヶ月に1回程度会うだけとなります。一方で、離婚同居だと、話し合って家事や育児を分担することができますので、双方の親が育児にかかわることができます。
(4)復縁できる可能性が残る
同じ人と再婚するケースも、少ないですが実際に存在します。
離婚後別居すると、子どもの親としての関係は残りますが、基本的には他人としてかかわることなくそれぞれの人生を送ることになります。しかし、離婚後同居を継続することで、お互い夫婦としての愛情が残っていることを実感したり、関係が修復されたりして、復縁できる可能性があります。
(5)住宅ローン返済中の場合にメリットがある
住宅ローン返済中の不動産があり、オーバーローン(不動産の価値が住宅ローンの残額よりも低いこと)だと、売却しても借金が残ってしまうので、離婚時に売却して財産分与をするのが難しいケースがあります。
通常は、オーバーローンの場合でも、不動産への居住継続を希望する方が住宅ローンの残債も引き取りますが、夫婦双方が居住を希望するとなると、難しい話し合いとなるでしょう。
そのような場合には、離婚後同居を選択することで双方が希望の家に住むことができ、借金が残るのに無理に売却せずに済むというメリットがあります。不動産が双方の共有であれば、住宅ローン完済後に売却すれば、共有分に応じて売却利益を受け取ることもできます。
離婚同居をする場合に決めておきたいルールとは
離婚同居をする場合は、後々の誤解や争いを防ぐために、次のようなことを話し合ってルールを決めておくとよいでしょう。
- 家賃や水道光熱費などの負担割合をどうするか
- 家事や子育ての分担をどうするか
- どちらかが別居したくなった場合どうするか
- いつまで同居を続けるか
特に単なる同居人として同居する場合には、加えて、お互いの生活に必要以上に干渉しないことや、客を招いてよいのかどうかなどについて、事前に話し合っておくようにしましょう。
離婚同居についてのQ&A
離婚同居についてよくある疑問について、回答します。
(1)生活費は請求できる?
単なる同居人としての同居の場合は、お互いに扶養義務はありませんので、生活費を請求することはできません。したがって、話し合いによりますが、基本的には収入差があっても、固定費(家賃や水道光熱費など)は2分の1ずつ負担することになるでしょう。
内縁関係としての同居の場合は、法律婚と同様にお互いに扶養義務がありますので、収入の低い方は、収入の高い方に対して、一定の生活費(婚姻費用)を請求することができます。
(2)養育費はどうなる?
同居の有無とは関係なく、父母はそれぞれ子どもの養育費を負担する義務があり、離婚の際に子どもの親権者となり子を監護する側は、他方に対して養育費の支払いを求めることができます。
離婚の際に、親権者と養育費の額については話し合って取り決めておくようにしましょう。
養育費の相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」で知ることができます。
しかし、この算定表は、別居をして世帯が二分され、それぞれに独立した生活費がかかることを前提とした基準ですので、同居の場合はこの算定表より低額になると考えられます。
(3)浮気された場合に慰謝料を請求できる?

離婚後単なる同居人として同居する場合には、双方恋愛は自由にすることができます。
したがって、同居人が他の異性と性的関係を持っても、同居人や恋愛相手に慰謝料を請求することはできません。
一方、内縁関係としての同居の場合は、法律婚と同様に夫婦として貞操義務がありますので、肉体関係を伴う浮気は、不貞行為として不法行為に該当する可能性があります(民法709条)。不貞行為に該当する場合には、内縁関係にある配偶者及び不貞相手に対して、慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚同居をする場合に必要な手続きはあるのか
離婚する際には、次のような各種手続きが必要です。
- 離婚届の提出
- 財産分与の話し合い
※財産分与の話し合いがうまくいかない場合などには、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができますが、離婚後2年以内に請求する必要があります(民法768条2項)。 - 年金分割(離婚日の翌日から2年経つと請求できない)の話し合い
- 離婚で変更した氏(名字)をどうするか(婚姻後の氏を継続して利用したい場合には、離婚後3ヶ月以内に役所に届出をする必要がある)
- 保険や年金への加入手続き(事実婚でも配偶者の被扶養者となれますが、同居関係にすぎない場合には、自分で保険や年金に加入する必要がある) など
離婚を検討する前に知っておきたい基礎知識について詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
離婚後同居を継続する場合も、今ご紹介したような手続きが必要になります。離婚後に同居を選択するために、特に必要となる手続きはありません。
しかし、それぞれの状況に応じて、世帯分離の手続きや公的扶助の申請手続きをした方がよいケースがありますので、説明します。
(1)世帯分離の手続き
離婚届の提出により、戸籍には離婚をした事実が反映され、住民票上の氏は自動的に離婚後の氏に変更されます。
しかしながら、どちらかが住民票を移さなければ、離婚届を提出した後も、住民票上は同一世帯のままです。
したがって、離婚同居が単なる同居関係になる場合には、「世帯分離」という手続きを取った方が、メリットがあるケースがあります。
世帯分離とは、同じ住民票に同一世帯(同じ住所で生計を一緒にしている世帯のことで、血縁関係とは異なる)として登録されている世帯を、住所が同じでも生計を別々にしているとして、世帯を分離する手続きのことをいいます。
社会保険料や各種税金は世帯ごとに計算されます。世帯分離をすることで、世帯収入が低くなれば、国民健康保険料や介護保険料などが低額になり、所得制限により受けられなかった公的支援を受けられる可能性があります。
一方、双方に一定以上の収入がある場合には、世帯分離後に二人合わせた保険料や税金額が、世帯分離前よりも高額になる可能性もあります。
(2)公的扶助の申請手続き
離婚同居が単なる同居の場合には、世帯分離をしたうえで、自分の収入額によっては、児童扶養手当、児童育成手当、生活保護などの公的扶助を受けられることがありますので、必要に応じて申請手続きを行います。
しかしながら、離婚同居の場合、内縁関係のある同居とされて同居する元夫(妻)と生計が別々とは認められず、各種公的扶助の受給が認められないおそれがあります。
離婚同居をする場合に知っておきたい注意点
離婚同居には、メリットもありますが次のような注意点もありますので、それぞれ説明します。
(1)偽装離婚が疑われ、各種公的手当が受けられない可能性がある

離婚の際の財産分与は、相当な範囲であれば、金銭で給付される限り、分与する方にも分与を受ける方にも、税金は課されません。
しかし、離婚後も変わらず同居生活を送っている場合には、偽装離婚を疑われて、財産分与による財産移転に贈与税が課税されるおそれがあったり、配偶者の債権者などにより財産移転の効力を否定されたりするおそれがあります。
また、同居していることで、生計が同一で、かつ、事実婚であると判断され、母子家庭に支給される児童扶養手当などの各種公的手当が受けられないおそれがあります。
(2)相手が同居をやめたくなる場合もあり、不安定な立場になる
離婚時に、一定期間離婚同居をすることに同意していても、その後の状況や心境の変化で、相手が同居をやめたいという可能性もあります。
夫婦には法律上同居義務がありますが、単なる同居にすぎない離婚同居の場合には、そのような同居義務はありませんので、相手が同居を拒否した場合、法的にそれを阻止することは難しくなります。
(3)同居が再婚の妨げとなったりストレスを感じたりする場合がある
離婚したとはいえ、離婚同居は同居関係を維持しますので、外形的に離婚したことがわかりにくく、気持ちの上でも新たな恋愛に踏み出す決意がつきにくいことがあります。したがって、新たなパートナーとの恋愛や再婚のチャンスに気づかなかったり、気づいても前向きになれなかったりすることがあります。
また、離婚同居は、離婚したにもかかわらず、離婚前と同じように元配偶者と毎日顔を合わせることになり、それに想像以上のストレスを感じて心身に影響が出る場合があります。
(4)扶養から抜けなければならず保険料等の負担が増える
夫婦の実態を伴う離婚同居の場合は、離婚後も内縁関係・事実婚であると認められれば、継続して扶養に入ることができます。
しかしながら、単なる同居にすぎない離婚同居の場合には、相手方の扶養に入ることはできませんので、自分で社会保険や国民健康保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。
【まとめ】離婚同居をするべきか夫婦でしっかり話し合いを!
離婚同居は外形的に実態がわかりにくいのですが、離婚後の当事者の関係がただの同居人なのか内縁関係なのかによって立場や保険等が大きく異なります。
通常の夫婦は、離婚後は別居を選択しますが、それはやはり、デメリットがあるとしても、離婚後は同居せずに別居する方が当事者のためであるという判断に基づくものと考えられます。したがって、離婚同居を選択する場合には、本当に同居継続可能なのかどうかを二人で事前に話し合うようにしましょう。
離婚に際しては、同居するか別居するか以外にも親権者を誰にするか、財産分与はどうするか、養育費や生活費の分担をどうするかなど夫婦で決めるべきことがたくさんあります。離婚問題でお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたします。費用倒れになることは原則ありませんので、安心してご依頼いただけます(2025年4月時点)。
離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。