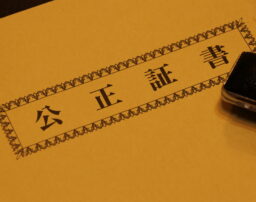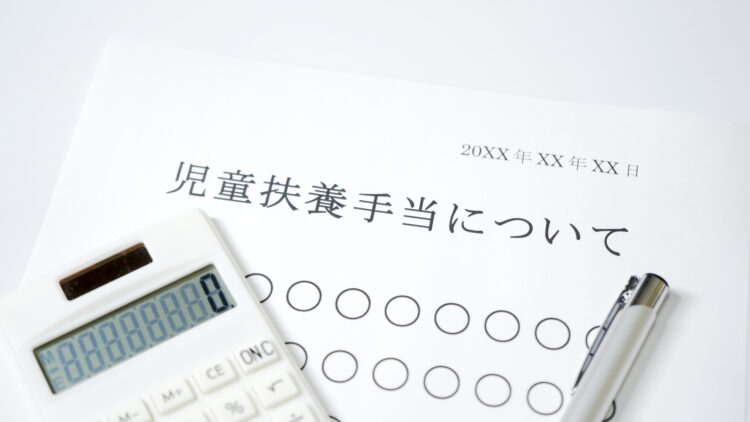「子どもは会いたがっているのに、会わせてくれない」
「面会交流に子どもの意思(気持ち)は反映されないのか」
など、面会交流についてお悩みはありませんか。
面会交流にあたっては、子どもの意思が反映される場合がありますが、子どもは親の影響を受けやすいため、一般的には10~15歳から子どもの意思が反映されることが多いようです。
もっとも、10歳未満であっても、家庭裁判所調査官が子どもの気持ちを調査することがあります。
この記事を読んでわかること
- 面会交流の決め方
- 面会交流に子どもの意思が反映される年齢
- 裁判所が面会交流について判断する際に考慮する要素
面会交流とは?

「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が、子どもと定期的・継続的に会って話したり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
さらに、監護親(子どもを養育している親)が子どもの写真や様子を送るということも「面会交流」にあたります。
「面会交流」というと離婚した後に行われるものという考え方が一般的ですが、離婚まで至らない別居の場合でも、「面会交流」が行われることがあります。
参考:面会交流|法務省
面会交流の決め方とは?
では、面会交流はどのように取り決めたらいいのでしょうか。
一般的に、次の方法で決めることになります。
- 夫婦間の話し合い
- 家庭裁判所に調停を申立てる
(1)夫婦間の話し合い

まずは、夫婦間での話し合いになります。
夫婦間での話し合いだと感情的になってしまうこともありますが、面会交流は子どものためのものですので、子どもの利益を最優先に考慮して、決めることが重要です。
面会交流については、次のこと決めておきましょう。
- 面会交流の可否
- 面会交流の場所
- 子どもの受け渡し場所
- 面会の頻度や時間
- 面会交流の方法
夫婦間における面会交流の取り決めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
決めた後は、あとでトラブルにならないように、きちんと書面もしくは公正証書の形で残しておくとよいでしょう。
※公正証書とは?
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことで、公証役場で作成することができます。
公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2) 家庭裁判所に調停を申し立てる

離婚後に、面会交流について元夫婦間で話し合うことが難しい場合、もしくは、話がまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます(なお、離婚前の別居中でも、「離婚調停」を申立て、そのなかで面会交流について話し合うことが可能です)。
「調停」とは、裁判官・調停委員が話し合いの間に入って、話合いを行うことをいいます。
面会交流調停でも話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が審判を行い、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流の可否や方法について判断することになります。
参考:面会交流調停|裁判所- Courts in Japan
面会交流についての調停や審判でできること
面会交流の調停や審判では、面会交流の話し合いのほかに、面会交流について親子にとってよい結果となるように、
- 家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)
- 試行的面会交流
が行われることがあります。
(1)家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)

家庭裁判官調査官とは、心理学、教育学、社会学などに関する専門知識をもった専門家のことです。
家庭裁判官調査官は、面会交流にあたって、子どもがどのような意見、気持ちを持っているのか、面会交流を実施するにあたり、子どもや監護親に与える影響などを調査します(なお、子どもが10歳未満であっても、自分の気持ちを表現できる年齢であれば、子どもが親に対してどのような気持ちを持っているのか調査します。)。
調査に際しては、年齢に合わせた方法を行い、子どもの心身状態に十分な配慮をします。
家裁調査官が行う調査としては、父母や子どもとの面接、家庭訪問(監護親と子の親子関係の調査)などを行うことがあります。
その後、家庭裁判所調査官の調査した結果は、調停委員が当事者を説得する材料や、裁判官が審判において面会交流の可否、その方法、回数、日時、場所等を判断する際に利用されることになります。
(2)試行的面会交流

「試行的面会交流」とは、子どもがどのように非監護親と接するかを見極めるため、面会交流をテスト的に行い、面会交流の場面における親子の交流状況を観察することをいいます。
この試行的面会交流は、家庭裁判所調査官の立会の下、裁判所内の「児童室」で行われます。絵本や玩具等が置いてある専用の部屋です。実際の面会交流において非監護親や子どもがどのような態度を取るかについて、ほとんどの児童室には隣接して観察室が設置されているため、観察室から児童室の様子を確認できる構造になっています。観察室から試行的面会交流の様子を見ることはできますが、児童室から観察室の様子は見えないようになっています(ワンサイドミラー)。
面会交流がうまくいった場合には、監護親にとって、その後の面会交流に対する安心感につながり、裁判官や調停委員にもいいイメージを与えることができ、スムーズな調停の成立が期待できるといえます。
ただし、試行的面会交流は、通常1回しか行われないため、試行的面会交流において親子間のコミュニケーションがうまくとれなかった場合には、スムーズな調停成立の妨げになる可能性もあります。
子どもが15歳以上である場合、必ず子どもの意見を聞かなければならない
家事事件手続法第152条第2項は、子どもの意思について次のように定めています。
家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第68条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(15歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
引用:家事事件手続法第152条第2項|e-Gov法令検索
面会交流の審判を行う場合、子どもが15歳以上である場合には、子どもの意見を必ず聞かなければならないと法律で定められています。
このことからも、裁判所が面会交流についての判断を行う際には、子どもの気持ちや意見が重要な判断要素とされていることがわかります。
15歳未満の場合であっても、監護親の影響を受けずに、自分の気持ちがしっかり言える年齢の場合には、裁判所は子どもの意見を重要視する傾向があります。
そのため、子どもが明確に面会交流を拒否している場合には、面会交流が認められないケースもあります。
裁判所が面会交流を判断するにあたって考慮する要素

裁判所が面会交流の判断を行う場合において、基本的に子どもの意見が考慮されることはこれまで説明したとおりです。
裁判所が面会交流の判断を行うにあたっては、子どもの意見以外にも次の要素を考慮することになります。
- 子どもに関する要素(子どもの生活環境におよぼす影響)
- 監護親に関する要素(監護親の意見、監護親の養育監護に対する影響)
- 非監護親に関する要素(非監護親の問題点)
- 夫婦の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係)など
(1)子どもに関する要素(子どもの生活環境におよぼす影響)
子どもが両親の離婚問題の影響で家庭内暴力をしたり、不登校になったりしたが、離婚したことでようやく子どもの気持ちが落ち着いてきた場合に、面会交流を認めることで、また子どもの気持ちが荒れてしまう場合があります。
このような場合、面会交流を認めることで、子どもの生活環境への悪影響が懸念されるために、面会交流が認められない可能性もあります。
(2)監護親に関する要素(監護親の意見、監護親の養育監護に対する影響)
子どもが乳幼児の場合、面会交流を実現するためには、(子ども一人では面会交流ができないため)監護親の協力が必要不可欠になります。
しかし、監護親が、別居や離婚に至った経緯から、非監護親と交流したくないなど面会交流に消極的である場合には、監護親の協力が得られないために、面会交流が認められない場合があります。
また、非監護親(面会交流を求める側)が監護親の教育方針に不満を抱いている場合には、非監護親が子との面会交流で、子に監護親の悪口を言ったり、教育方針に干渉したりするおそれがあります。
このようなおそれがあると認められた場合には、面会交流を認めることで、監護親と子どもの安定した関係を阻害するおそれがあります。
その場合、子どもが精神的に混乱し、監護親との信頼関係が破壊されてしまう可能性があるため、面会交流が認められないこともあります。
(3)非監護親に関する要素(非監護親の問題点)
非監護親に薬物使用の疑いがある場合や、子どもを連れ去る危険性が高い等、非監護親に問題行為・違法行為が存在する場合、面会交流を認めることによって、子どもに重大な危害が加えられる可能性があるため、面会交流が認められない場合があります。
(4)夫婦の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係)
別居・離婚に至った経緯が、非監護親の監護親や子どもに対する暴力である場合、別居・離婚後も、監護親や子どもが非監護親に対して強い恐怖心を抱いている可能性があるため、面会交流が認められない場合があります。
面会交流を第三者機関にサポートしてもらうことができる
子どもの意思や気持ちを考えて、面会交流を行うべきであるとわかっていても、「監護親が非監護親と連絡をとりたくない」、「非監護親に子どもを預けるのは不安」など親側の気持ちで面会交流に消極的になることがあります。
このような場合、例えば、第三者機関に面会交流に付き添ってもらう、日程調整などの連絡をとってもらうなどをサポートしてもらうことができる場合があります。
費用がかかることがありますが、第三者機関を検討するのも一つの手段でしょう。
【まとめ】法律上子どもの意見を聞く必要があるのは15歳以上だが、それより幼い場合も裁判所は子どもの気持ちを重要視する傾向がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話したり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流すること
- 面会交流は、一般的に、1.夫婦間の話し合い、2.家庭裁判所での調停で決める
- 面会交流の調停や審判では、家庭裁判所調査官による調査(調査官調査)が行われる場合がある
- 裁判所が面会交流の判断を行う際には子どもの気持ちや意見が重要な判断要素とされており、監護親の影響を受けずに、自分の気持ちがしっかり言える年齢であれば、子どもの意見が重要視される傾向がある
- 裁判所が面会交流の判断を行うにあたっての考慮要素
- 子どもに関する要素(子どもの生活環境におよぼす影響)
- 監護親に関する要素(監護親の意見、監護親の養育監護に対する影響)
- 非監護親に関する要素(非監護親の問題点)
- 夫婦の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係)など