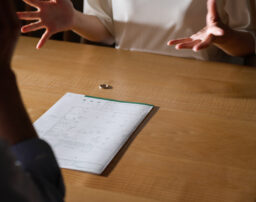親離れができないことで悩んでいませんか。
親からの自立は、経済的、心理的な要因が絡み合う複雑な問題です。
しかし、親離れを成功させるための具体的なステップと対策を知ることで、親離れをして自立した生活を送れる可能性があります。
本記事では、親離れできない原因を明らかにし、親離れできない影響や、具体的な対策について説明します。
この記事が、自立への第一歩を踏み出し、1人の人間として充実した人生を送る手助けとなれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 親離れとは
- 親離れできない原因
- 親離れできない影響
- 親離れのアプローチ法
ここを押さえればOK!
しかし、心理的要因、経済的要因、家庭の事情などが原因で親離れできない人もいます。
親離れするためのアプローチとして、心理的アプローチ(カウンセリングなど)、物理的アプローチ(親と物理的に距離を取る)、経済的アプローチ(経済的自立、生活スキルの習得)、受けられる支援の確認する方法があります。
カウンセリングや自己啓発書を通じて自己肯定感を高め、経済的に自立するための収入アップや生活スキルの習得を目指すことが重要です。
親離れとは
親離れとは、子どもが成長して、親を頼りにせずに自分の意思で行動できるようになることをいいます。自分の生活を自分で管理し、自立した生活を送れていれば、それは親離れできているといえるでしょう。
親離れをすることで、子どもはさらに自己成長を遂げ、社会でも自立した存在として認識されます。
一般的に、子どもの成長に伴い子どもは親に頼らず自分で判断して行動ようになり、親も関与する機会が減っていき、子どもが就職や結婚などで実家を離れるという成長のいずれかの段階で、親離れができていきます。
しかし、何らかの原因で大人になっても親離れできない人もいます。
親離れできない原因
親離れできない主な原因を3つ説明します。
(1)心理的要因
親離れできない主な原因の一つは心理的要因です。
幼い頃から親が何をするにも先回りして準備していたり、自分で選択する機会がなかったりして、自分で決めて行動することに自信がなく親への依存心が強い場合、親離れしにくいかもしれません。
また、親や周囲から褒められたり受け入れられたりする経験が乏しく、自己肯定感が低いと、親から離れることや失敗することへの不安が大きくなってしまい、親離れしにくいことがあるようです。
(2)経済的要因
経済的要因も親離れの大きな障壁です。
大多数の国民よりも少ない所得で暮らしている状態のことを「相対的貧困」ということがあります。この割合は、その国の経済的格差問題を示す数字として利用されています。
日本でも、長期的に見ると相対的貧困率は上昇しています。
非正規の仕事で給料自体が安い、正社員の仕事でもインフレに応じて給与が上がるわけではないなどという理由から、親と同居して生活費を節約する、というケースがあります。
このような経済的事情から、親元を離れることができず、親離れが遅れることがあります。
参考:相対的貧困率等に関する調査分析結果について|厚生労働省
(3)家庭の事情
家庭環境が子どもの自立した生活を許さない場合、親離れが難しくなります。
例えば、親や兄妹の介護など、家庭内での役割が固定されている場合、自立することの家族への影響を考えて自立をあきらめることがあります。
親離れできないことの影響
親離れできていないと、どのような影響があるのでしょうか。
親離れできないことは、個人の精神面に多くの悪影響を及ぼすと考えられます。
自立心や自尊心、自信の欠如やストレスの増加がその一例です。自立できないことで自己肯定感が低下し、「こんな自分はダメだ」と思ってしまうと、精神的な安定を得ることが難しくなります。
また、親に頼り続けることで、自分自身で考えて決断することで得られる体験をしないでいると、精神的・社会的成長が阻まれ、社会的なスキルや経験を積む機会が減少してしまいます。
親に精神的に依存し親離れできていないと、「親との関係が悪化する」ことに耐えられず、親は親、自分は自分という線引きが難しくなり、親の機嫌に振り回されてしまうかもしれません。
結果、ストレスが増加し、精神的な健康に悪影響を及ぼすことすらあります。
親離れするためのアプローチ
「自分は親離れできていないかもしれない」と思ったら、次に親離れするためのアプローチを紹介しますので、参考にしてください。
(1)心理的アプローチ(カウンセリング、自己啓発など)
心理的アプローチとして、カウンセリングや自己啓発が有効です。
カウンセラーなどの専門家の助けを借りることで、依存心や自己肯定感の低さを克服するサポートを受けることができるでしょう。
例えば、心理カウンセラーとのセッションを通じて、自分の感情や思考を整理し、親からの独立に対する不安を軽減することができます。
また、自己啓発書を読んだり、似たような状況にある人と話したりすることも有効です。様々な情報に触れることで、自分自身の成長を促し、自立への自信を持つことができるでしょう。
(2)物理的アプローチ(物理的に親と距離を取る)
親と物理的に距離を取ることも重要です。
例えば、経済的に可能であるのに親と同居している場合、思い切って1人暮らしをしてみます。
物理的に親と離れて、一人暮らしを始めることで、親とのかかわりを減らすことができます。これにより、精神的にも自立した生活を送りやすくなるでしょう。
別居が難しい場合には、身の回りのことは自分でやる、親に生活費を渡す、(いつもは親の言いなりだったが)自分のことについては自分で決断するなど、自分で自立して考えて生活できるようにしていくとよいでしょう。
(3)経済的アプローチ(経済的自立、生活スキルの習得など)
自分の経済的問題から親離れが難しいという場合、経済的自立を目指すことが重要です。
アルバイトや副業、資格取得や転職活動を通じて収入UPを目指しましょう。収入が上がることは、親離れだけでなく、長期的な人生を考えてもプラスです。
借金問題を抱えている場合には、債務整理により返済の負担を減らして生活を立て直すことができるかもしれませんので、債務整理を扱っている弁護士に相談しましょう。
また、独立後、自分で家事を行い、収入の範囲内で生活することも重要です。同居していても、料理や掃除などの家事を一通りできるようにして、家計簿をつけ、収入と支出を把握し、節約できる部分は節約しましょう。このような生活スキルを習得することで、自立した生活を送る準備を整えましょう。
(4)受けられる支援がないか調べる
受けられる支援があるかどうかの確認も重要です。
例えば、生活困窮者自立支援制度では、生活に困っている場合、その状況に合わせた様々な支援をうけることができます。
市区町村に相談窓口がありますので、一度相談してみましょう。
また、子どもがおり、ひとり親で自立が難しく実家に頼っている場合、ひとり親支援制度が使えるかもしれません。
こちらも地域別の窓口に問い合わせたうえで、受けられる支援がないか確認しましょう。
【まとめ】
親離れできない原因は心理的要因、経済的要因、家庭の事情が主なものです。
親離れできていないと感じる方は、自分は何が原因かを理解したうえで、具体的な対策を講じましょう。親離れすることで、自立した生活を送り、精神的な安定を得ることができるかもしれません。公的支援制度を活用することも、親離れをサポートする有効な手段です。
この記事が、自立への第一歩を踏み出し、充実した自分の人生を送るきっかけになれば幸いです。