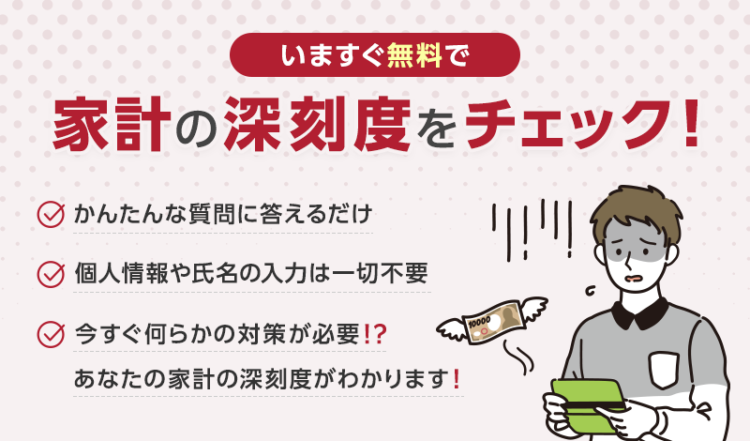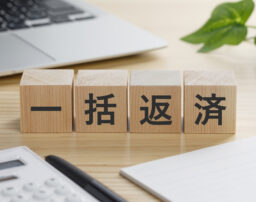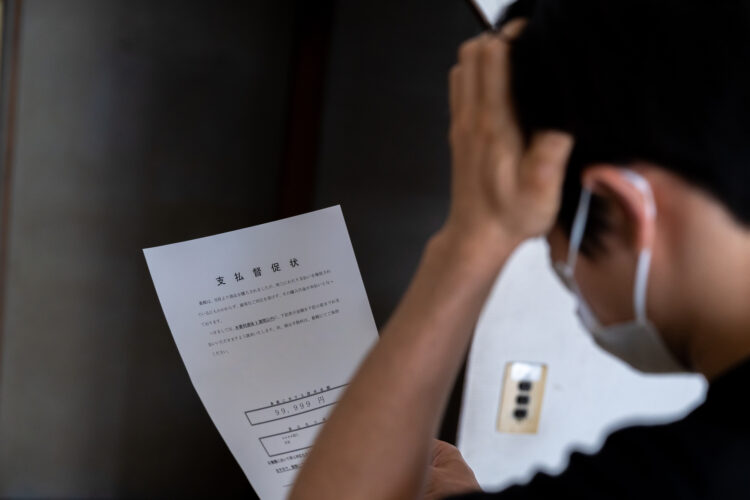「友人からお金を借りようと思うけど、個人間の借金の場合、時効はどうなるの?」
借金に関する時効について、正しい知識を持つことは重要です。
本記事では、時効の期間や起算点など、借金の時効に関する重要ポイントを弁護士が解説します。
借金問題の解決に役立つ情報を提供できれば幸いです。
ここを押さえればOK!
・2020年4月1日以降の借金の場合、個人間かそうでないかに関係なく、原則として5年
・トラブルを避けるには、契約書を作成し、きちんと返済計画をたてることが重要
借金の消滅時効とは
借金の消滅時効とは、簡単に言うと、債権者(お金を貸した人)が権利を行使できる状態だったのに権利を行使しなかった結果、権利を失うことを定めた制度です(民法第166条)。
では、借金は具体的に何年で時効になるのでしょうか。
貸主によって時効期間が異なる?
民法改正の影響で、借金の時効は、貸主が貸金業者か個人かによって異なることがあります。
具体的には、次のとおりです。
【2020年4月1日より前の借金】
- 貸主が個人:貸主が権利を行使できる時から10年
- 貸主が銀行や貸金業者:貸主が権利を行使できる時から5年
【2020年4月1日以降の借金】
次のうちいずれか早いほうです。
- 貸主が権利を行使できることを知った時から5年
- 貸主が権利を行使できる時から10年
したがって、2020年4月以降にお金を借りたのであれば、貸主が個人かそうでないかによって時効期間は異なりません。
個人間の借金の時効の起算点
次に、時効の起算点である、「貸主が権利を行使できる時」や「貸主が権利を行使できることを知った時」の具体的な意味を説明します。
(1)返済期限がある場合
2020年4月1日以降に個人からお金を借りた場合で考えてみましょう。
借金の場合、権利を行使できるのは、返済期限日からですが、民法には「初日不算入」というルールがあるため、返済期限日の翌日から時効のカウントダウンが始まります。
たとえば、2030年3月31日が返済期限日なら、時効のカウントダウンは2030年4月1日からです。
前述のとおり、時効は「権利を行使できることを知った時から5年」と「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうで成立します。
もっとも、具体的な返済期限を決めている以上、貸主が権利を行使できることを知らないということは通常考えられません。
したがって、「権利を行使できることを知った時」は、通常は「権利を行使できる時」と同じです。
(2)返済期限がない場合
返済期限が設定されていない場合、時効の起算点は原則として借金が発生した日(金銭を借りた日)からとなります。
これは、債権者がいつでも返済を請求できる状態にあるためです。
したがって、基本的に借金をした日の翌日から5年が時効期間となります(※)。
ただし、慣習などにより実質的な返済期限が存在する場合は、その日が起算点となることもあるので注意が必要です。
※2020年4月1日より前の個人からの借金である場合は、10年
時効の成立要件
借金の時効が成立するためには、以下の2つの要件が必要です。
- 債権者の権利不行使: 債権者が時効期間にわたって権利を行使しないこと。
たとえば、訴訟提起などの裁判上の請求が代表的な権利行使の例です。 - 債務者(お金を借りた人)の援用: 時効期間が経過した後、債務者が時効を援用(主張)すること。
時効の援用は債務者の権利であり、債務者が明確に時効を主張しない限り、返済義務が自動的に消滅するわけではありません。
これら2つの要件が揃って初めて、借金の時効が成立します。
つまり、単に時間が経過しただけでは時効は完成せず、債務者が積極的に時効を主張する必要があるのです。
しかし、時効の援用には落とし穴があり、かえって墓穴を掘ってしまうことも少なくありません。時効が成立しているのではないかと考えた場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
時効援用の失敗例について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
時効がリセットされる場合
時効期間が経過する前に、たとえば次のような事実があると、時効期間がリセットされることとなります。
- 全額または一部を返済した
- 「返済する」という意思表示をした
- 返済期限の延長を交渉した
これらの事実があると、「債務の承認」として時効期間がリセットされてしまう可能性があります。
また、次の事実があった場合にも、時効期間はリセットされることとなります。
- 判決や裁判上の和解などによって権利が確定した
- 強制執行、担保権の実行などが終了した
個人間の借金にも利息は発生する
個人間の借金でも、当事者間の合意があれば利息を付けることができます。
ただし、利息には法律による上限があり、これを超える利息は無効です。
利息制限法によると、利息の上限は次のとおりです。
- 借金の金額が10万円未満:年20%
- 借金の金額が10万円以上100万円未満:年18%
- 借金の金額が100万円以上:年15%
個人間の借金における利息について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
個人間の借金でトラブルを防ぐためのポイント
友人・知人や親族など、個人間の借金は感情的な問題も絡みやすいため、トラブルが起きやすい側面があります。
そこで、なるべくトラブルを回避するための方法について確認しておきましょう。
(1)契約書を作成する
個人間の借金トラブルを防ぐ最も効果的な方法は、詳細な契約書を作成することです。
契約書には、たとえば次のような基本的な条件を明記します。
- 借入金額
- 返済期限
- 返済方法
- 利息(設定する場合) など
両者が合意した内容を書面化することで、あとになって解釈の相違や記憶違いによるトラブルを防ぐことが期待できます。
契約書は2部作成し、貸主と借主がそれぞれ1部ずつ保管します。
(2)返済計画をたてる
借金をする際は、具体的な返済計画を立てることが重要です。
分割で返済する場合は、返済計画は借主の収入や生活状況を考慮し、無理なく継続できるものにする必要があります。
また、予期せぬ事態に備えて、余裕を持った計画を立てることも大切です。
これにより、返済の遅延や滞納といった事態を起こりにくくする効果が期待できます。
貸金業者からも借金している場合
個人間で借金を検討している方のなかには、すでに金融機関や貸金業者から借入れがある方も少なくありません。
複数の債権者からの借入れがある場合、個人間での新たな借金を重ねるよりも、債務整理を検討したほうがいいかもしれません。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがあり、個々の状況に応じて選択することができます。
このような複雑な金銭問題は、専門家のアドバイスが不可欠です。
弁護士に相談することで、現在の債務状況を客観的に分析し、最適な解決策を見出すことができるでしょう。
多くの法律事務所では初回相談は無料であることが多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
債務整理を行うことで、健全な金銭管理への道筋をつけることが期待できます。
個人間での新たな借金は避け、問題解決に向けて行動することが重要です。
【まとめ】個人間の借金であっても、時効は原則として5年
2020年4月1日以降の借金の場合、時効は基本的に5年です。
2020年4月以降にお金を借りたのであれば、貸主が個人かそうでないかによって時効期間は異なりません。
(2020年4月1日より前の個人間における借金の時効は10年)
もし、金融機関などからの借金が膨れ上がって返済が滞り、友人や知人などの個人からもお金を借りることを検討しているのであれば、少し立ち止まってください。
債務整理を検討したほうが根本的な借金問題の解決につながるかもしれません。
貸金業者からの借金問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。