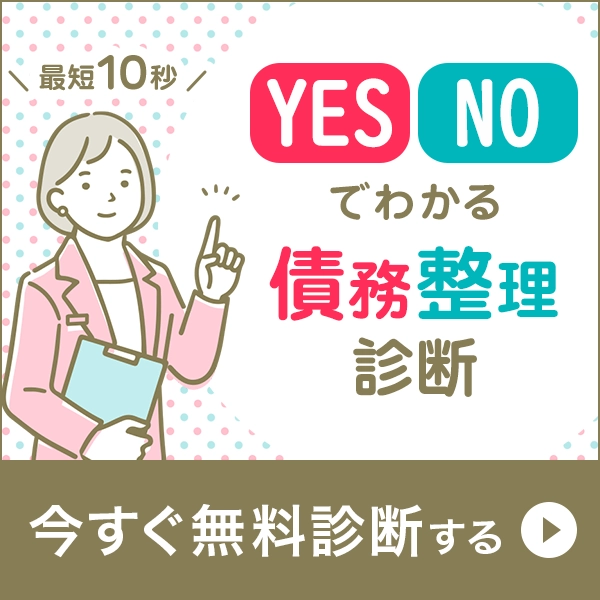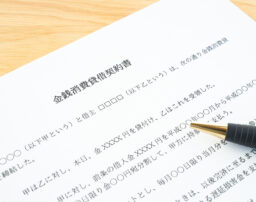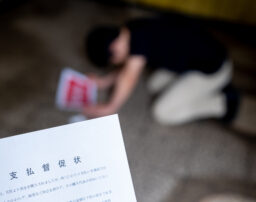「友人からお金を借りようと思うけど、個人間でお金を借りる場合も利息や遅延損害金って必要なの?」
家族や友人などの個人からお金を借りる場合、借りる金額にもよりますが、利息や遅延損害金(返済が遅れた場合に支払うお金)までは細かく定めず、契約書も作らずに口約束で済ませている場合も多いです。
ですが、実は、家族や友人などの個人からの借金であっても、事前に取り決めていれば、利息が発生します。
また、返済が遅れれば遅延損害金も発生します。
家族や親しい友人からの借金だからこそ、きちんと取り決めをしないと後から思わぬトラブルにつながる可能性があります。
そこで、今回は、家族や友人などの個人から借金をする場合の注意点などについて、弁護士が解説します。
この記事を読んでわかること
- 個人からの借金に利息や遅延損害金が発生する条件とその利率
- 個人から借金をする際の注意点
- 個人からの借金を返せなくなった際の対処法 など
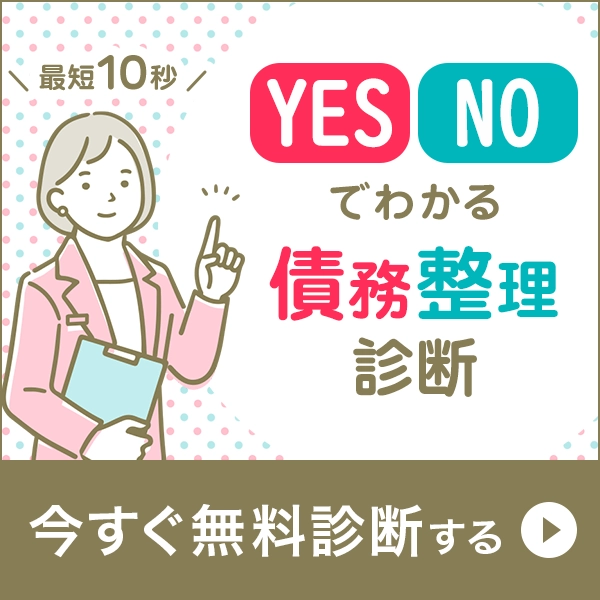
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
家族や友人などの個人からの借金も利息・遅延損害金は発生する?
まず、家族や友人などの個人からの借金で、利息や遅延損害金が発生する条件などについて解説します。
(1)個人からの借金も利息が発生する場合
「借金」は、法律上は「金銭消費貸借契約」(民法587条参照)と言い、有効に成立するには、次の要件を満たす必要があります。
- 借主がお金を返すことを約束すること
- 貸主がお金を渡し、借主がお金を受け取ること
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用:民法第587条
そして、民法では利息について次のように定めています。
第1項
引用:民法第589条
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
第2項
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
つまり、借金をする時に、貸主と借主の間で利息について定めておかないと利息は請求できませんが、定めがあれば利息を請求できるということです。
個人間の借金であっても、お金を借りる時に利息の支払いを約束していれば、基本的には利息を支払わなくてはいけないのです。他方、お金の貸し借りの際に利息について何も約束をしていなければ、利息を支払う必要はありません。
なお、個人間の借金について、お金を借りる時に利息について何も約束していなくても、貸主・借主の双方が合意をすれば、後から利息を発生させることは可能です。
借主が合意していないのに、貸主の一方的な請求で利息を発生させることはできません!
個人間の借金で利息をとる場合の上限金利は?
個人間の借金で利息を支払う約束しても、無制限に高い利息を設定できません。
まず、次を超える利息が契約で設定された場合、超過している部分は無効です(利息制限法第1条)。
| 借金の金額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
例えば、家族や友人から、年利20%の約束で15万円を借りた場合、上限である年18%をオーバーしている部分は無効です。借りた側は、年18%の利息を支払えばよいということになります。
なお、利息について定めた法律として、いわゆる「出資法」(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)があります。
出資法では、年109.5%を超えてお金を貸した場合、貸主は5年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方という刑事罰の定めもあります(出資法第5条1項)。
家族や友人からの借金で年利109.5%を超える高金利の利息を約束することは通常は考えられませんが、このような約束をするだけでも出資法違反になります。万が一、個人からそのような高金利でお金を借りて返済を迫られているという場合には、警察に相談することをお勧めします。
(2)個人間の借金でも、返済期日に遅れると遅延損害金が発生する
『遅延損害金』とは、返すと約束した日までに借金を返せなかった場合に生じる損害賠償金です。
いわば約束どおりに借金を返さないことに対するペナルティです。
約束した返済期日を過ぎてしまうと、返済期日の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金は利息と異なり、貸主と借主との間で支払う約束をしていなくても、発生します!
遅延損害金は利率を約束していればその利率で(※ただし、法律上の上限はあり)、何も約束していなければ法定利率で計算されます。
法定利率は、次のとおりです。
- 支払いが遅れた日が2020年3月31日以前 5%
- 支払いが遅れた日が2020年4月1日以降 3%(3年ごとに見直し)
この法定利率よりも高くする場合には、事前に貸主と借主の間で利率について定めておく必要があります。
もっとも、遅延損害金の利率はいくらでも高くできるわけではなく、利息と同様、次を超える利率で約束した場合、超過部分は無効です(利息制限法第4条1項、第1条)。
| 借金の金額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年21.9% |
さらに、年109.5%を超える利率で設定された場合には利息の場合と同じく、刑事罰の対象となります(出資法第5条1項)。
遅延損害金について詳しくはこちらをご覧ください。
友人から借金するときの注意点

利息や遅延損害金の他にも、友人間での貸し借りであること特有の注意点があります。
ここでは、リスクについて説明します。
(1)急に借金の返済を迫られる可能性がある
家族や友人など個人間の借金は、返済期日を定めていないことも多いです。その場合、貸主は「相当の期間」を定めて、「返還の催告」をすることができます(民法第591条1項)。
つまり、法律上はお金を貸した場合に返済期日を定めていない場合には、すぐに返せという請求はできず、相当の期間という猶予期間の間に返済することを求めることができるということです。
「相当の期間」とは、具体的にはどのくらいの期間ですか?
どの程度経過すれば「相当の期間」と言えるかは、返済すべき金額などによって異なります。ケースバイケースの判断になりますので一概には言えませんが、金額によっては、数日程度であっても「相当の期間」と判断される可能性があります。
家族や友人などの個人間の借金は、特に期限を決めずに貸した上で「そろそろ返して欲しい」などと言われることが多いです。
返済期日を決めずにした個人間の借金では、急に返済を迫られた場合の猶予は「相当の期間」だけです。
急に返済を迫られて焦らないためにも、家族や友人など個人間の借金であっても、少なくとも返済期日は決めておくことをお勧めします。
なお、返済期日を決めない個人間の借金は、貸主から返済を求められて「相当の期間」が経過すると、その時点から遅延損害金が発生します!
(2)友人からの借金には、取立方法に規制がない
貸金業者は、借主を威迫したり、私生活若しくは業務の平穏を害する言動での借金の取立てをしてはならないと定められています(貸金業法第21条1項)。
例えば、貸金業者が債務者等に電話をかけたり、債務者等の居宅を訪問したりすることについては、午後9時から午前8時までの間は禁止されています(※正当な理由がある場合を除く。同項1号、貸金業法施行規則19条1項)。
ですが、貸主が個人の場合、このような貸金業法に基づく取立方法への法規制はありません(※もっとも、貸主が借主を脅したり暴力をふるってお金を返済させるようなケースでは、刑法上の恐喝罪などが成立しえます)。
貸金業者以外による個人からの苛烈な督促で、事情を知らない家族等や勤務先を巻き込んだトラブルになるケースもあります。
よく知らない個人からの借入れやSNSでの借入れは、避けましょう。
(3)口約束は避ける
口約束のみでお金の貸し借りを行うと、合意内容が不明確になりトラブルになる危険性が高いと言わざるを得ません。
「いくら借りたのか」「いくら返すのか」「いつ返すのか」「返してもらってない」等で、争いになることが多いです。
家族や友人の間で、書面を作成するのは抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、後でトラブルになると、人間関係が壊れることになりかねません。
最初に「金銭消費貸借契約書」を作成することをお勧めします。
難しいようなら、メモ程度の「借用書」でも記録を残すこと、金銭の移動を「手渡し」でなく「銀行振込」にすることなど、客観的な証拠を残すことで、トラブルを減らすことはできます。
(4)消滅時効の完成
貸主が返済を請求する権利は、時効によって消滅する可能性があります。
貸金業者などではない個人の借金の場合、お金を借りた時期によって、次のとおり、時効期間が異なります。
| 借金の消滅時効 | |
| 2020年4月1日より前の借金 | 貸主が権利を行使できる時から10年 |
| 2020年4月1日以降の借金 | 貸主が権利を行使できることを知った時から5年 (又は権利を行使できる時から10年のうちの、早い方) |
「貸主が権利を行使できる時」というのは、貸主が借主に対して「貸したお金を返して欲しい」と言える時です。基本的には、返済期限を決めていれば返済期限から、返済期限を決めていないときにはお金を貸した日から消滅時効が進行します。
もっとも、法律上の一定の事由があると時効は完成しません。
「時効の完成猶予」(民法第147条1項、第150条1項等)の主な要因
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 内容証明郵便等での催促
「時効の更新」(民法第147条2項、第152条1項等)の主な要因
- 確定判決等によって権利が確定した時
- 債務者自身が、債務の存在を認めたり、債務の存在を前提とした言動をしたとき
債務の存在を前提とした言動とは、例えば催促に対して「もう少し待ってくれ」と言う場合や、債務の一部の返済を行った場合などが挙げられます。
個人間の借金について時効期間が経過した場合、時効を主張するかどうかは借りた側が選ぶことができます。時効が完成しても貸主との交友関係などから借りたお金を返すこともできます。ただし、もしも時効を主張したい場合には、債務の存在を認めるようなことをしないようにご注意ください。
消滅時効について、詳しくはこちらをご覧ください。
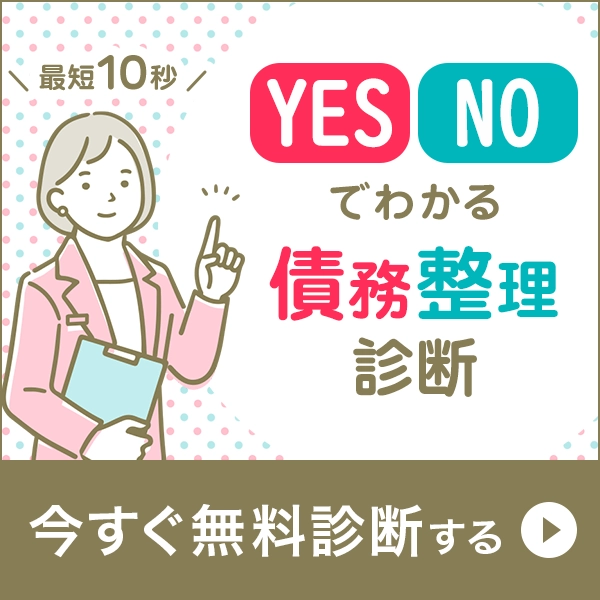
友人に借金を返せないときの対処法
友人への借金を返さないと、人間関係が壊れてしまいます。
(1)借金を返せない事情を正直に伝える
どうしても返せないという場合、お金を貸してくれていた友人には事情を誤魔化さず、正直に謝罪し、速やかに伝えるべきです(※消滅時効が成立して時効を援用するようなケースは別です)。
お金を借りた事実自体をうやむやにしようとする等、不誠実な態度をとるのではなく、正直に事情を伝えることで、友人も安心することができます。
今後も友人でいるために誠意をもって対応しましょう。
(2)どうしても返せないときは債務整理を検討する
債務整理とは、借金の返済の負担の減免につながる法的手続きです。
主に、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
の3種類があります。
「家族や友人など個人からの借金以外にも消費者金融などに借金があり、返済できない…」そうお悩みの方も多いです。
なお、個人再生や自己破産を検討している方は、消費者金融などには返済せず、家族や友人など個人の借金だけを優先して返済すること(「偏頗弁済」と言います)には注意が必要です。
個人再生の申立てにあたり「偏頗弁済」をすると、返済額が増えたり悪質な場合には裁判所が開始決定を出さない可能性がありますし、
自己破産の申立てにあたり「偏頗弁済」をすると、自己破産で免責されない(※全ての借金の支払義務が残ってしまう)などの可能性があります。個人間の借金がある方で債務整理を検討されている方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
偏頗弁済のリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】友人からの借金は、後から思わぬトラブルにつながる可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 友人からの借金であっても、取り決めがあれば利息が発生し、返済が遅れれば遅延損害金も発生する
- 友人からお金を借りるときであっても、急な返済を求められたり苛烈な取立てを受けるなどのトラブルが発生するリスクがあることに注意が必要
- 友人に返済ができなくなったときは、誠実に事情を説明する(※消滅時効を援用する場合は債務の存在を認めるような言動をしないようにすることに注意が必要です)
- 消費者金融などからの借金もある場合には状況次第では債務整理の利用も検討する
借金問題は放置すればするほど利息や遅延損害金で深刻になっていきます。
返済でお困りの方は早期に対処することをお勧めします。
借金トラブルでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。