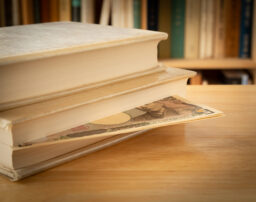老後の生活に不安を感じていませんか?
近年、「老後破産」という言葉をよく耳にするようになりました。これは、決して他人事ではありません。
しかし、適切な知識と対策があれば、老後破産のリスクを軽減することができます。
本記事では、老後破産の実態を解説し、具体的な予防法をお伝えします。
あなたの将来の経済的安定と、家族の幸せな生活のために、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 老後資産とは
- 老後破産の影響
- 老後破産の原因
- 老後破産しやすい人の特徴
- 老後破産しないための予防法
ここを押さえればOK!
老後破産の主な原因には、収入減少への対応不足、不十分な老後資金準備、退職後も続く住宅ローン返済、退職金の運用失敗、予想外の医療費・介護費負担増、子どもへの長期的な経済支援、高齢者を狙う詐欺被害などがあります。
老後破産のリスクが高い人の特徴として、支出管理ができていない、固定費が高額、貯蓄額が少ない、老後のシミュレーションをしていないなどが挙げられます。
対策としては、必要な老後資金を把握し計画的な資産運用と貯蓄を行うこと、家計の見直しと固定費削減、健康管理による医療費・介護費の抑制、年金の繰下げ受給の検討などが重要です。
早期からの計画的な貯蓄と家計管理が老後破産を防ぐ鍵となります。
借金問題がある場合は、老後まで持ち越さずに早い段階で解決することが望ましいので、一度弁護士に相談するようにしましょう。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

老後破産とは?破産者の約4分の1が60歳以上

老後破産とは、一般的に、老後に高齢者が経済的に行き詰まり破産手続きを行う状況、もしくは、破産やむなしという状況にあることをいいます。
近年、この問題が深刻化しており、多くの高齢者が将来の経済的不安に直面しています。
日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によれば、自己破産をした人のうち、60歳以上の割合は25.72%です。約4分の1が60歳以上です。
50歳以上も入れると47.17%で、半数近くにもなります。
特に70歳以上は、2002年の調査では2.73%に過ぎませんでしたが、2020年の調査では9.35%、もう少しで10人に1人の割合まで増えてきています。
参考:2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査(日本弁護士連合会)(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2020/2020_hasan_kojinsaisei_1.pdf )
老後破産するとどうなる?生活への影響と自己破産の流れ
老後の自己破産は、生活に大きな影響を与えます。
しかし、経済的な問題を放置せず、自己破産することにより、借金を清算して(税金など一部は返済を免除されません)新たなスタートを切ることができます。
ここでは、自己破産後の生活と自己破産の流れについて解説します
(1)自己破産後の生活:生活保護受給の可能性と条件
老後の自己破産後の生活では、収入を確保して収入の範囲内で生活していく必要があります。
もし働けない等の事情がある場合には、収入を確保するために生活保護の受給は重要な選択肢です。
生活保護は、最低限度の生活を保障する制度であり、受給のための主な条件は以下の3つです。
【生活保護の受給条件】
- すでに自身が持っている資産を使っている状況である
- 働いて収入を得ることができない状況である
- 親戚や親族からの援助が受けられない状況である
生活保護を受給すると、主に以下のような支援を受けられます。
- 生活扶助(食費、光熱費、衣服など)
- 住宅扶助(家賃)
- 教育扶助(子どもが義務教育を受けるために必要な費用)
- 医療扶助
- 介護扶助
ただし、生活保護は最後のセーフティネットですので、受給条件はしっかりチェックされますし、受給中は収入の状況を毎月申告する必要があります。
また、福祉事務所のケースワーカーが年数回訪問調査を行い、就労可能な人に対して、就労に向けた助言や指導をされます。その指導が不当なものでない限り、受給者は従わなければなりません。
生活保護費はあくまでも受給者の自立を促すものなので、経済的な自立を目指して頑張りましょう。
(2)自己破産の流れ:申立から免責許可決定まで
自己破産の手続きは、自己破産の申立てから始まり、免責許可決定の確定で終わります。
免責許可決定が得られれば、借金の返済義務から解放され(税金など一部返済義務が残るものもあります)、新たな生活を始めることができるでしょう。
自己破産の手続には、管財事件と同時廃止があります。さらに、管財事件には少額管財と通常管財の2つがあり、個人の破産手続が同時廃止とならない場合は、少額管財となることがほとんどです。
裁判所の基準を満たすような財産がなく、法的に借金が免除されることに問題がないことが明らかであれば、同時廃止手続となります。
2021年の統計で、破産手続が終了した総数74325件のうち、同時廃止手続きとなったのは43069件ありました。約6割が同時廃止手続きとなっています。
ここでは、同時廃止手続きの流れを説明します。
- 弁護士に相談・依頼
- 自己破産申立の準備 :債務の調査・計算、必要書類の収集、申立書の作成など
- 自己破産申立て :裁判所に必要書類を提出
- 破産手続開始決定&廃止決定 :裁判所が破産手続開始の決定と同時に廃止を決定
- 免責審尋 :裁判官が直接破産者に質問などを行う
- 免責許可決定 :裁判所が、非免責債権(税金など)を除いて支払い義務がなくなる旨の決定を行う
- 免責許可決定の確定
弁護士に相談・依頼してから、免責許可が確定するまでの期間は、人によって異なります。
弁護士に破産手続きを依頼する場合、破産申立てにかかる弁護士費用を貯める必要がありますが、数ヶ月で準備できる人もいれば、1年近くかかる人もいます。
また、破産申立てを行ってから、免責許可決定が出るのは、通常4~5ヶ月程度ですが、ケースによって早い遅いの違いはあります。
老後破産の7つの主な原因
老後破産には、通常複数の要因が絡み合っています。これらの原因を理解し、早期に対策を講じることが、将来の経済的安定と生活水準の維持につながります。
以下に、老後破産の7つの主な原因を詳しく解説します。
安心して老後を過ごすために、これらの知識を活用し、適切な対策を立てるようにしましょう。
(1)収入減少に対応できない生活レベルの維持
多くの人が直面する問題は、退職後の収入減少に生活レベルを合わせられないことです。
収入が減ったにもかかわらず、支出を見直さなければ、赤字となり、貯金などの資産を取り崩すことになります。
資産が潤沢にあればよいですが、あまりなければ借金をするようになって老後破産への道を進むことになる可能性があります。
【対策】
- 退職前から段階的に支出を減らす習慣をつける
- 固定費を見直して支出額を減らす(住居費、通信費など)
- 収入に見合った生活設計(娯楽や旅行、趣味など)を立てる
早めに生活スタイルの調整を始めることで、急激な変化を避け、スムーズな移行が可能になるでしょう。
(2)不十分な老後資金の準備
老後資金の不足は深刻な問題です。
金融広報中央委員会の2022年の調査によると、60歳代の世帯の貯蓄額の中央値は1270万円です。
しかし、「老後2000万円問題」で表面化したように、寿命が延びたことによる老後にかかる費用の増加、インフレなどが原因で、これでも十分な老後用資産とは言えない面があります。
【対策】
- 若いうちから計画的な貯蓄を始める
- 余剰資金で資産運用(投資信託、個人型確定拠出年金など)
- 退職金がある場合は、浪費せず有効活用
ファイナンシャルプランナーなどお金の専門家のアドバイスを受けながら、長期的な視点で資産形成を行うことが重要です。
参考:各種分類別データ(令和4年) ― 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和3年以降)|知るぽると
(3)退職後も続く住宅ローンの返済
晩婚化で、マイホームを買う年齢が遅くなったことなどもあり、退職後も住宅ローンの返済が続くケースが増えています。これは老後の家計を圧迫する大きな要因となります。
【対策】
- 退職前にローンを完済するよう計画を立てる
- 繰上げ返済を活用し、返済期間を短縮する
住宅ローンの返済計画は、老後の生活設計と密接に関連しています。早めの対策が重要です。
(4)退職金の運用失敗によるリスク
退職金は老後の重要な資金源ですが、すぐに使わないからという理由で、資産運用に回す人も多いです。しかし、知らず知らずのうちにリスクの高い商品を購入し、結果として大切な退職金が目減りしてしまうかもしれません。
【対策】
- 投資の勉強を行い、金融リテラシーを高める
- 分散投資によるリスク軽減
- リスクの高い商品は、きちんとリスクを理解したうえで投資する
退職金は一度きりの大切な資金です。慎重かつ賢明な運用が求められます。
(5)予想以上の医療費・介護費の負担増
高齢になるに伴い、ケガや病気が多くなり、予想以上に医療費や介護費の負担が増加してしまうことがあります。
【対策】
- 民間の医療保険や介護保険への加入を検討
- 健康維持のための日々の習慣(タバコ、食事、飲酒、運動など)に気を付ける
適切な健康管理と、保険加入を検討することで、将来の不安を軽減することができるでしょう。
(6)子どもの教育費や援助の長期化
多くの子どもが大学まで通う時代となり、学費や仕送りなど、子どもへの経済的支援が長期化し、老後の資金を圧迫するケースが増えています。
また、社会人となるのが遅かったり、何らかのきっかけで大人になってから引きこもって生活費が実家だよりになるケースもあり、子どものためにかかるお金が想像以上となってしまうこともあります。
【対策】
- 若いころから子どもの教育資金を計画的に準備する
- 子どもの自立を促す教育
- 援助の限度を事前に決めておく
子どもへの支援と自身の老後資金のバランスを考えることが重要です。
(7)高齢者を狙う詐欺被害の増加
詐欺は、時代の流れに合わせて、虎視眈々と消費者を狙っています。
特に、高齢者を狙った詐欺被害は多いです。被害者の割合は、60代以上が全体の約87%にも上ります(令和6年度上半期統計より)。
一度詐欺の被害にあってしまうと、老後資金を失うリスクがあります。
【対策】
- 「自分は大丈夫」と思わず、詐欺の手口や最新情報を学ぶ
- 家族や周囲の人との連絡を密にする
- 不審な電話や訪問者には即座に対応しない
実際の詐欺被害について学び、孤立せず周囲とのコミュニケーションを維持することで、詐欺被害にあうリスクを軽減できるでしょう。
参考:令和6年上半期における特殊詐欺の状況について|警視庁(https://action.digipolice.jp/files/15cc1537a0df7b599107a81e202984a3.pdf)
老後破産リスクが高い人の4つの特徴
老後破産のリスクは誰にでもありますが、特に以下の4つの特徴を持つ人は要注意です。
以下に、老後破産リスクが高い人の特徴とその対策を詳しく解説します。
(1)支出管理ができていない人
支出管理ができていない人は、老後破産のリスクが非常に高くなります。
主な問題点:
- 収入に見合わない生活習慣
- 衝動買いや無駄遣いが多い
- クレジットカードの過剰利用
これらの問題は、老後の限られた収入で生活する際に深刻な影響を及ぼします。
収入に見合わない支出を伴う生活を続け、借金を重ねて多重債務に陥った場合、任意整理や、自己破産などの法的手続きが必要になる可能性があります。
「借金返済が厳しいな」と感じたら、早い段階で借金問題を扱う弁護士に相談し、債務の整理や返済計画の見直しを行うことをおすすめします。
(2)固定費が高額な人
固定費が高額な人は、収入が減少する老後に経済的困難に直面するリスクが高くなります。
主な問題点:
- 高額な住宅ローンや家賃
- 複数の保険料や会費
- 高い公共料金や通信費
これらの固定費は、老後の年金収入での生活を圧迫する可能性があります。
(3)貯蓄額が少ない人
貯蓄額が少ない人は、予期せぬ出費や収入が少なくなる長期の老後生活に対応できず、破産のリスクが高くなります。
主な問題点:
- 老後の生活資金の不足
- 緊急時の対応が困難
- 資産運用の機会損失
貯蓄不足で借金で生活するようになったら要注意です。
債務が増えて返済が困難になった場合、任意整理や、個人再生、自己破産などの法的手続きが選択肢となります。早めに借金問題をあつかう弁護士に相談しましょう。
(4)老後のシミュレーションをしていない人
老後のシミュレーションをしていない人は、将来の経済状況を具体的にイメージできず、適切な準備ができないリスクがあります。
主な問題点:
- 必要な老後資金の把握ができていない
- 年金受給額の正確な理解がない
- 予期せぬ出費への備えがない
以上の4つの特徴が自分に当てはまるのかチェックし、該当する項目がある場合は次で説明する対策を講じることが重要です。

老後破産を防ぐ4つの具体的対策
老後破産を防ぐためには、事前の対策が重要です。
以下に、4つの具体的対策を紹介します。
これらの対策を実践することで、将来の経済的不安を解消し、自分や家族の生活水準を維持しつつ、安心して老後を過ごすことにつながるでしょう。
(1)必要な老後資金を把握し、計画的な資産運用や貯蓄をする
まず、ねんきんネットで将来の年金受給額を確認して、老後の収支を把握します。
収入だけで老後の生活が賄えないときは、取り崩す老後資金としてどの程度必要なのかを計算する必要があります。
シミュレーションできるアプリなどがありますので、そちらを利用したりファイナンシャルプランナーに相談したりして把握しましょう。
必要な老後資金の計画的な資産運用と貯蓄は、老後破産のリスクを軽減します。具体的な方法の例は以下の通りです。
- 積立投資の活用:
- 投資信託の定期買付
- ドルコスト平均法の利用
- 税制優遇制度の利用:
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- NISA(少額投資非課税制度)
- リスクの分散:
- 普通預金、定期預金
- 株式、債券、国債
- 不動産投資など
投資は自己責任です。投資を行う際は、そのリスクを十分理解したうえで、必ず余剰資金で行うことが重要です。また、「元本保証で必ず儲かる」的な詐欺的な投資勧誘に注意し、疑問がある場合はお金を渡す前に消費者センターなどに相談することをおすすめします。
(2)家計の見直しと固定費削減
現役世代の生活レベルが高い(支出が多い)まま老後を迎えると、急に生活レベルを下げることは難しいので、支出が重なって老後破産のリスクが高くなります。
現役世代に、できれば家計を見直して固定費を削減するなどして、支出を減らす努力をしておきましょう。家計見直しは、以下のようなステップで実践するとよいでしょう。
- 収支の可視化:
- 家計簿アプリの活用
- 3ヶ月分の支出を分析
- 固定費の見直し:
- 保険の見直し(不要・過剰な契約、特約の解約)
- 通信費の見直し(格安プランへの変更)
- 住宅ローンの借り換え
- 変動費の削減:
- 食費の見直し(外食を減らす、まとめ買い)
- 光熱費の節約(LED電球の使用、省エネ家電の導入)
(3)健康管理による医療費・介護費の抑制
老後も可能な限り健康で元気でいることが、医療費や介護費の抑制につながり、老後の経済的負担を軽減します。以下のような対策を実践しましょう。
- 定期的な健康診断の受診
- 生活習慣の改善:
- バランスの良い食事
- 適度な運動
- 十分な睡眠
- ストレスをためず適宜解消する
高額な医療費が発生した場合には、利用できる保険がないかどうか確認しましょう。また、高額療養費制度を利用することで自己負担額を軽減できます。また、介護が必要になった際には、ケアマネージャーに相談して、必要に応じて適切なサービスを利用することも重要です。
(4)年金の繰下げ受給のメリットとデメリット
年金の繰下げ受給(通常65歳から年金を受給できるが、受給開始を65歳以降に繰り下げること)は、老後の収入を増やす有効な手段です。しかし、デメリットもありますので、メリットとデメリットをしっかり理解したうえで、判断しましょう。
以下に主なメリットとデメリットを説明します。
メリット:
- 受給月額の増加(最大+84%)
- 長生きするほど有利
デメリット:
- 繰下げ期間中は年金を受け取れないので他で収入を確保する必要
- 早期に亡くなった場合、もらえる年金額が少なく通常受給に比べて損をする可能性
繰り下げ受給は、厚生年金で1.6%、国民年金で2.6%の人が選択しているにすぎません(2020年)。
慎重に検討するようにしましょう。
参考:[年金制度の仕組みと考え方]第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給|厚生労働省
【まとめ】老後破産を避けるためには、貯蓄を増やし支出を抑えるなど早めに対策を
老後破産を防ぐためには、早期からの計画的な貯蓄と家計管理が重要です。
具体的には、積立投資や税制優遇制度の活用、家計の把握、固定費の見直し、健康診断の定期受診などが効果的です。また、年金の繰下げ受給など、状況に応じた選択肢も検討しましょう。あなたの行動が、安心で豊かな老後への第一歩となります。
「借金返済で老後資金が貯められない」とお悩みの方は、まず借金問題を解決する必要があります。一度、借金問題を扱っている弁護士に相談してみてください。
アディーレ法律事務所は、借金問題を積極的に扱っております。
また、ご依頼いただいた所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2025年1月時点)
債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。