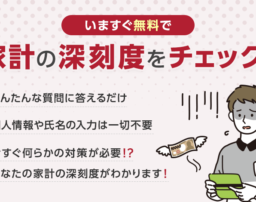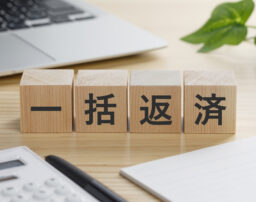最初は少し借りただけだったのに、いつの間にか返済のやり繰りが苦しくなっている……
こんなお悩みを抱える人も少なくないのではないでしょうか。
最初は自力で返せると思って借金を始めたものの、いつしか借金とその利息で返済額が膨大なものになり、借金苦を抱えてしまうことがあります。
ここを押さえればOK!
借金が返済不能な状態になったら、債務整理を検討することが解決への道となります。債務整理には主に3つの方法があります。
・任意整理: 債権者と直接交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延ばしたりして負担を軽減する方法です。
・個人再生: 住宅などの財産を維持しつつ、借金を大幅に減額してもらう方法です。安定した収入があることが条件となります。
・自己破産: 裁判所を通じて借金の支払い義務を原則免除してもらう方法です。浪費やギャンブルが原因でも、多くの場合「裁量免責」が認められる可能性があります。
弁護士に相談し、早期に適切な方法を選ぶことが、借金苦から抜け出すための最善策です。借金問題にお困りの方は、アディーレへご相談ください。
返済がつらい!借金苦に陥る主な理由
借金の返済がつらくなる、借入れを重ねることとなる主な理由として、以下のようなことが挙げられます。
これらの原因に心当たりのある人は、今後借金苦に陥る可能性がありますので、ご注意いただければと思います。
(1)生活費のための借金
借金をする理由の中で最も多いのが、生活費のための借金です。
低所得や収入の減少により、生活費が不足し、生活費の補填のために借入れを始めるという人が多いです。
逆に、収入は安定しているものの、結婚や出産、子供の学費などによって支出が増加し、生活費が不足して借入れを始める人もいます。
また、近年のキャッシュレス決済の普及も借金の遠因となっています。
その場で現金を手放さなくてよいキャッシュレス決済は、お金を使った感覚が分かりにくくついつい使い過ぎてしまうことにつながりやすいです。
そして、もともと生活費が不足しているため、自身の収入ではその返済ができなくなり、その支払日を乗り切るために借金やクレジットカードの分割払い・リボ払いをしていたら、いつの間にか返済すべき金額が膨らんでしまうこととなるリスクが高いです。
参照:金融庁委託調査 貸金業利用者に関する調査・研究<調査結果>|金融庁
(2)浪費・ギャンブル
買い物などによる浪費や、競馬などのギャンブルの資金のために借入れを始め、次第に浪費やギャンブルに依存するようになり、次々に借金を重ね、自力で返済できなくなることもよくあります。
クレジットカードの「キャッシング」は、気軽に借りられることで自分のお金であるかのような錯覚に陥りやすい一面があります。
一つの業者からしか借りていなかったものの、その業者からの借入れが限度枠いっぱいになり、別の業者から借入れをするということを行っていると多重債務に陥ります。
多重債務とは、消費者金融やクレジットカード会社など、複数の貸金業者から借金をしていることをいい、その借金の返済が困難になっている人を多重債務者といいます。
そして、各業者への返済が苦しくなり、新たなクレジットカードでキャッシングしたお金で他の業者への借金を返済するということを繰り返すうちに、本来可能な返済額をいつの間にか超えてしまってお金のやり繰りができなくなってしまうのです。
上記のようなケースでは、目安として、毎月の収入の3分の1以上を返済に充てなければならない状況となっていれば、もう自力での完済は困難な段階に来ていると考えた方が良いでしょう。
(3)返済や取立て
金融機関からお金を借りる場合には、必ず金利が付きます。貸付けの際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められていますが、消費者金融等の貸金業者は、「利息制限法」の上限に近い金利を定めている場合が多いです。
そのため、毎月借金を返済しているのに、返しても返しても利息しか支払えず、全く元金が減らないということがあり、その返済のためにまた借入れをするという状態が続けば続くほど借金は高額になっていきます。
そして、借金の返済が滞ってしまうと、業者から電話や書面で督促が来ます。それでも返済しないと「法的措置を執る」などと記載された書面が届くこともあり、そのような状況が続くうちにうつ病になってしまう人もいます。
数ヶ月に及ぶ返済の遅れがある人は、事故情報が信用情報機関に登録されることによって、通常の貸金業者からはお金を借りられなくなります。
借金苦から抜け出せない場合は債務整理
借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続で借金苦から救われる道があります。
債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるための手続のことです。
債務整理の方法には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。この項目では、それぞれの概要を解説します。
(1)任意整理
任意整理とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続です。
任意整理は、債権者との交渉によって、法定金利まで借金を減額し、これまでの遅延損害金、今後発生する金利をカットできる場合があります。
また、任意整理は各債権者との個別の和解ですので、例えば自動車のローンは任意整理をせず、これまでどおり支払い続けて、その他の借金を任意整理するというように、柔軟に債務整理をすることができる場合もあります。
ただし、任意整理は、借金が利息制限法で定められた法定金利まで減額されますが、自己破産や民事再生のように借金がなくなる、もしくは大幅に減額されるということはあまりありません。
(2)個人再生
個人再生とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。
数年間の支払が必要であるため、安定した収入があることが要件です。また、住宅ローンを除く負債が5000万円以下に収まっていることも要件となっています。
個人再生は、任意整理によっては返済が難しい場合に検討する手続です。
また、後述する自己破産とは異なり、借入理由がギャンブルや浪費によるものであったとしても直ちに支払義務が免除されないなどということはありません。
さらに、個人再生の場合は住宅ローンの残っている家を残すため、「住宅資金特別条項」を利用することで住宅ローンの支払はそのまま継続しつつ他の借金を減額することができる可能性があるのも大きな特徴です。
(2-1)個人再生の2つの方法
個人再生の手続には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
の2つの手続があります。
2つの手続は、個人再生で支払う金額の決め方が異なり、給与所得者等再生の方が支払う金額が高くなる傾向にあります。
ここでは個人再生で支払う金額の決め方を説明します。
(2-2)個人再生の支払額
小規模個人再生での支払額は、
- 現在ある債務の総額から、減額対象とならない債務額を除いた金額を法律に基づき減額した金額(最低弁済額といいます)
- 自己破産する場合に、配当に充てるため手放さなければいけない財産の価額(清算価値といいます)
を比較して高い方の金額です。
そのため、高額な不動産などの財産がなければ2の清算価値を低く抑えられ、支払総額を大幅に減額できる可能性があります。
なぜ2の清算価値が基準になるかというと、個人再生での支払額が自己破産の場合に債権者に配当されることとなる金額よりも低くなってはいけない、自己破産の場合よりも債権者が損することになってはいけないとする、「清算価値保証原則」があるためです。
一方、給与所得者等再生の場合には、さらに
- 可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分
という基準が加わり、1~3を比較して最も高い金額となります。
そのため、給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも支払わなければならない金額が高くなる傾向にあります。
それではなぜ支払額の高くなる傾向のある給与所得者等再生の方法が選択される場合があるかというと、債権者の反対により手続が頓挫することを避けられるからです。
小規模個人再生の場合、再生計画案について債権者による書面決議が行われ、再生計画案が裁判所に認められるためには、
- 債権者の数の2分の1以上の反対がなく
かつ
- 反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと
が必要です。
しかし給与所得者等再生の場合、債権者の同意は必要ありません。
そのため、再生計画案について反対しやすい業者からの借入額が全体の半分を超えている場合など、小規模個人再生がうまくいかないと見込まれる場合に給与所得者等再生の利用を検討することとなります。
(3)自己破産
自己破産とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。
自己破産手続には「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。
裁判所が破産管財人を選任して、財産の調査や債権者への配当、借入れの経緯や「免責不許可事由」などについて調査する管財事件が原則です。
管財事件となった場合には、管財人の報酬などの手続費用に充てられる「予納金」を納めなければなりません。東京地裁の場合、20万円以上とされています。
ただし、破産手続の費用を支払うに足りる財産がなく、特に管財人による調査の必要もない場合には、例外的に「同時廃止」という比較的簡便な手続を選択できる可能性があります。
免責不許可事由について
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますが、借金をした経緯に問題がある人や、破産手続に協力しない人は、免責が認められない場合があります。裁判所が免責を認めない事由として、免責不許可事由が定められています(破産法第252条1項各号)。
免責不許可事由とされているのは、例えば、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担したことや、破産手続で裁判所が行う調査について、説明を拒んだり虚偽の説明をしたことなどです。
免責不許可事由がある場合、免責が認められない可能性がありますが、たとえ浪費などの免責不許可事由があっても、破産手続に真摯に協力している限りは、多くの場合、裁判所による「裁量免責」(破産法第252条2項)によって免責が認められているのが実情です。
(4)過払い金請求
債務整理を行う場合、前提としていくら借入れがあるか正確に算出する必要があります。
そこで、利息制限法の上限利息に基づいて残債務の額を算出し、利息を払い過ぎていないかどうかを計算します(引き直し計算といいます)。
そして、もしも利息を支払い過ぎていたのであれば、その分その業者の借金の額を減額することができ、更に支払い過ぎていた金額が借金の元金を上回っているのであれば、その分を過払い金としてその業者に返還請求することができます。
また、過払い金は、既に完済した業者にも返還請求することができ、回収した過払い金を他の業者への借金の返済に充てれば、返済の負担を軽減することができます。
過払い金は、
- 2010年6月17日よりも前に借入れを開始していて
- 完済している場合には完済から10年以内
であった場合には回収できる可能性があります。
【まとめ】借金問題の解決のためには、早期に債務整理の検討を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 借金苦の原因には、主に生活費の不足や浪費・ギャンブル、金融業者への返済や業者からの取立てなどがある
- 借金苦から救われる方法として債務整理の手続があり、債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産があり、場合によっては過払い金を回収できる可能性もある
自力での借金返済が困難な場合、そのまま放置しては返済額が膨らむばかりで解決からはどんどん遠ざかってしまいます。借金問題についてお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。