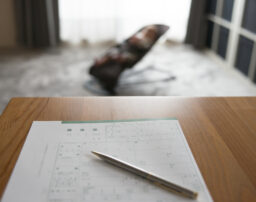「離婚して離れて暮らしている子どもへの養育費の支払いが厳しくなってきた…一度決めた額を減額することはできないだろうか?」
一度取り決めた養育費を減額するためには、まずは養育費を受け取っている側と話し合って、納得してもらう必要があります。双方が合意すれば、養育費の金額や条件はいつでも変更可能です。
また、話合いがまとまらない場合には、養育費減額調停を申し立て、家庭裁判所における調停や審判で減額が認められれば、養育費を減額することができます。
この記事では、どのような場合に家庭裁判所が養育費の減額を認めるのか、解説します。
この記事を読んでわかること
- 養育費を減額できる条件
- 一度決めた養育費が減額される流れ
- 養育費の減額についてよくある質問
ここを押さえればOK!
しかし、養育費を決めた時点では予見できなかった大きな事情の変化があれば、減額が認められる可能性があります。
養育費の減額を求める手続きは、まず当事者間で話合いを行い、合意が得られれば養育費の金額を変更できます。合意が得られない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立て、調停委員が双方の意見を聞きます。調停が不成立の場合は、養育費減額審判に移行し、裁判官が最終的な判断を下します。
養育費減額調停の申し立てには、申立書や収入関係の資料などが必要で、費用もかかります。調停では、収入の減少や扶養家族の増加などの事情を正確に伝えることが重要です。また、養育費の相場を事前に確認しておくことも必要です。
養育費を計算する際は「養育費算定表」をもとにしますが、裁判所は個別具体的な状況を総合的に考慮します。
弁護士なしでも調停は可能ですが、法律の知識や経験がないと不利になる可能性があるため、弁護士に依頼することが推奨されます。弁護士に依頼すれば、調停の場に同席してもらえ、精神的負担の軽減も期待できます。h2 養育費を減額できる条件とは?
そもそも養育費を支払う義務は、親の法律上の義務であり、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を子にも保持させる義務」(生活保持義務)であるとされています(民法第877条1項)。
したがって、特別な理由もなく一度決めた養育費の減額を求めても、認められません。
一般的には、養育費について取り決めた時点では予見できなかった大きな事情の変化があった結果、当初の金額が妥当ではなくなったと判断される場合には、一度決めた養育費の変更(減額や増額)が認められる、と考えられています。
それでは、減額が認められる可能性がある事情の変化とは、具体的にどのようなものでしょうか。
事情の変化が、養育費を支払う側・受け取る側のどちらに生じたのかに分けて、それぞれご説明します。
浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
養育費を減額できる条件とは?
そもそも養育費を支払う義務は、親の法律上の義務であり、「自分の生活を保持するのと同程度の生活を子にも保持させる義務」(生活保持義務)であるとされています(民法第877条1項)。
したがって、特別な理由もなく一度決めた養育費の減額を求めても、認められません。
一般的には、養育費について取り決めた時点では予見できなかった大きな事情の変化があった結果、当初の金額が妥当ではなくなったと判断される場合には、一度決めた養育費の変更(減額や増額)が認められる、と考えられています。
それでは、減額が認められる可能性がある事情の変化とは、具体的にどのようなものでしょうか。
事情の変化が、養育費を支払う側・受け取る側のどちらに生じたのかに分けて、それぞれご説明します。
(1)養育費を支払う側の事情の変化
養育費を支払う側の収入が減少したり、再婚して扶養家族が増えたりしたことは、減額が認められやすくなる事情の変化です。
具体的には、たとえば次のようなものです。
- 突然リストラされ、失業した
- 病気やケガなどが原因で、収入が減った
- 再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
- 再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組した
ただし、家庭裁判所は、それぞれの収入・支出状況や当初の養育費の金額などさまざまな事情を考慮し、最終的に判断します。
上記のような事実があれば、必ず養育費の減額が認められるものではない点にはご注意ください。
再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組しない場合であっても、状況によっては養育費の減額が認められる可能性があります。
(2)養育費を受け取る側の事情の変化
養育費を受け取る側の収入が増加したり、再婚などにより子どもを扶養する状況に変化が生じたりしたことは、減額が認められやすくなる事情の変化です。
具体的には、たとえば次のようなものです。
- 転職などにより、収入が大幅に増加した
- 再婚相手が子どもと養子縁組した
上記のような事実があれば、必ず養育費の減額が認められるわけではありませんが、養育費の減額について判断する際の重要な考慮要素であることは間違いありません。
再婚相手が子どもと養子縁組をしていない場合であっても、再婚相手が子どもの養育費など家族の生活費を負担しているなどの事情がある場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
養育費が減額されるまでの流れ
それでは、養育費が減額されるまでの手続の流れを見ていきましょう。
(1)当事者間での話合い

まずは養育費を支払う側と受け取る側で話し合います。話合いにより当事者が合意すれば、どんな理由であっても(特に理由がなくても)養育費の金額を変更することは可能です。
とはいえ、やはり納得してもらうためには、養育費を減額せざるを得なくなった事情を具体的に説明したほうがよいでしょう。
説得に自信がない場合や、元配偶者とやり取りする際に精神的な負担が大きいと感じる場合には、この段階から弁護士に依頼し、代わりに交渉してもらうこともあります。
合意が成立した場合には、あとになって「やっぱり減額には応じられない」と言われるなどして、トラブルが再燃しないようにするためにも、合意書の作成をおすすめします。
(2)養育費減額調停
当事者同士による話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることになります。
「調停」とは、簡単に言えば話合いの手続です。
調停委員が当事者の間に入り、双方の言い分を聞いてくれます。
養育費減額調停では、減額を必要とする事情について質問されるでしょう。
具体的には、現在の収入や取決め当初からの収入の変化、あるいは再婚(養子縁組)などによる扶養家族の変化についてです。
(3)養育費減額審判
養育費減額調停でも話合いがまとまらず、調停不成立となったら、「養育費減額審判」という手続に自動的に移行し、裁判官が養育費の減額を認めるかについて判断します。
この判断内容に不服がある場合には、不服申立てである「即時抗告」が可能です。
なお、即時抗告は2週間以内にしなければなりません。
養育費減額調停について

次に、養育費減額調停の詳しい流れと、申立てに必要な書類などについてご説明します。
(1)養育費減額調停の流れ
養育費減額調停は、相手方(この場合だと、養育費を受け取る側の元配偶者)の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
ただし、当事者双方がこれと異なる家庭裁判所で調停することに合意していれば、その合意した家庭裁判所でも調停が可能です。
【養育費減額調停の流れ】
養育費減額調停を申し立てる
第1回調停期日
第2回~数回の調停期日
調停成立or調停不成立
ケースバイケースではありますが、1回の調停期日にかかる時間は約2時間程度で、期日と期日の間は約1ヵ月となることが多いようです。
調停が成立すると、家庭裁判所が調停での合意内容を「調停調書」という書類に記載します。
調停が不成立になると、自動的に審判手続に移行し、審判の内容は「審判書」という書類に記載されます。
(2)養育費減額調停の申立てに必要な書類・費用
養育費減額調停を申し立てるために必要となる主な書類は、次のとおりです。
- 申立書およびその写し
- 対象となる子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入関係の資料(例:源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し) など
申立先の裁判所や具体的な事情によっては、ほかにも追加で書類の提出を求められることがあります。
また、申立てにかかる費用は次のとおりです。
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手(必要な金額・枚数は裁判所によって異なる)
申立費用のほか、戸籍謄本を取得する際の手数料や、調停調書などの交付手数料もかかります。さらに、弁護士に依頼すれば数十万円程度の弁護士費用がかかるでしょう。
(3)養育費減額調停のポイント
養育費減額調停において、押さえておきたいポイントは次のとおりです。
【現在の状況を正確に伝える】
→収入の減少や扶養家族の増加について正確に説明し、養育費が減額されるべきであることを伝えましょう。どの程度の減額を希望しているのかについて、具体的な根拠や金額を示すことがポイントです。
また、受け取る側の事情の変化も問題になるため、元配偶者の収入が大幅に増加した事実や、元配偶者の再婚相手が子どもと養子縁組をしたといった事実があれば、それも伝えるようにしましょう。
【養育費の相場を事前に確認しておく】
→養育費の一般的な相場を把握しておくことも必要です。
裁判所は、養育費を支払う側と受け取る側の収入、および子どもの人数・年齢に応じた養育費の目安を表(「養育費算定表」と呼ばれています)にして、公開しています。
たとえば、現在における双方の収入状況に照らせば、相場はもっと低い金額になることを示せるとよいでしょう。
養育費の減額が認められないケース
養育費の減額が必要な事情として、認められにくいものがあります。
たとえば、次のようなケースでは、減額は認められないでしょう。
- 面会交流に応じてくれない(または回数が少ない)ことを理由とするケース
- 自己都合により退職し、収入が減少した(または無くなった)ケース
- 当初合意した金額が相場よりも高いことを理由とするケース
養育費の相場を把握しておくことは大切ですが、当初合意した金額が相場よりも高いことは、減額が認められる理由にはなりません。
相場を知らずに合意してしまったのだとしても、具体的な事情の変化があったわけではないからです。
養育費の減額に関するよくある質問(Q&A)
(1)養育費を減額する際の計算方法は?
原則として「養育費算定表」をもとに計算します。
ただし、養育費算定表が絶対の基準となるわけではなく、裁判所では個別具体的な状況が総合的に考慮されることになります。
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
(2)養育費を支払わなかった場合はどうなる?
養育費についての調停が成立した場合(または審判があった場合)や、強制執行認諾文言を記載した公正証書を作成していた場合、強制執行の手続が可能になります。
強制執行とは、給与や預貯金などの財産を差し押さえる手続のことです。
調停や審判を経ていた場合は、強制執行の前に裁判所から履行勧告や履行命令を受けることもあります。
(3)弁護士なしでも調停は可能?
制度上、弁護士を立てなくても調停を申し立てることは可能です。
しかし、法律の知識や裁判手続の経験がない状態で調停に臨んでも、自分に有利な事情をうまく伝えられなかったり、減額の根拠となる事情について説得的な主張ができなかったりするリスクがあります。
また、弁護士に依頼すれば、調停の場に同席してもらえるため心強く、元配偶者との話合いにともなう精神的負担の軽減が期待できます。
【まとめ】養育費減額調停とは、家庭裁判所で養育費の減額について話し合う手続のこと
養育費を支払う側と受け取る側の合意さえあれば、養育費の金額はいつでも変更でき、理由は必要ありません。
当事者間で話合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。
調停でも合意できず調停不成立となったら、審判という手続に自動的に移行し、裁判官が養育費の減額を認めるかについて判断します。
裁判所で養育費の減額が認められるためには、養育費について取り決めた時点では予見できなかった大きな事情の変化が必要です。
たとえば、養育費を支払う側の収入が減少したり、再婚して扶養家族が増えたりしたことは、減額が認められやすくなる事情の変化です。
一方、養育費を受け取る側の事情の変化としては、収入が増加したことや、再婚相手が子どもと養子縁組をしたことなどが挙げられます。
もっとも、これらの事情は重要な考慮要素ではありますが、これらの事情があれば必ず減額が認められるわけではない点にご注意ください。
アディーレ法律事務所では、現在養育費を支払っており、その養育費の減額を求めたい方からのご相談を承っています。
養育費の減額請求は簡単に認められるものではありませんが、ご説明したように事情によっては認められるケースもあります。
一度弁護士に減額請求が認められる可能性があるのかどうか、聞いてみてはいかがでしょうか。
ご相談はお電話で可能ですので、お気軽にフリーコール0120-554-212までお問い合わせください。