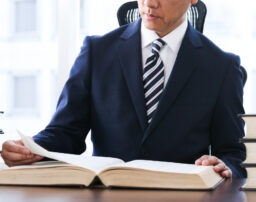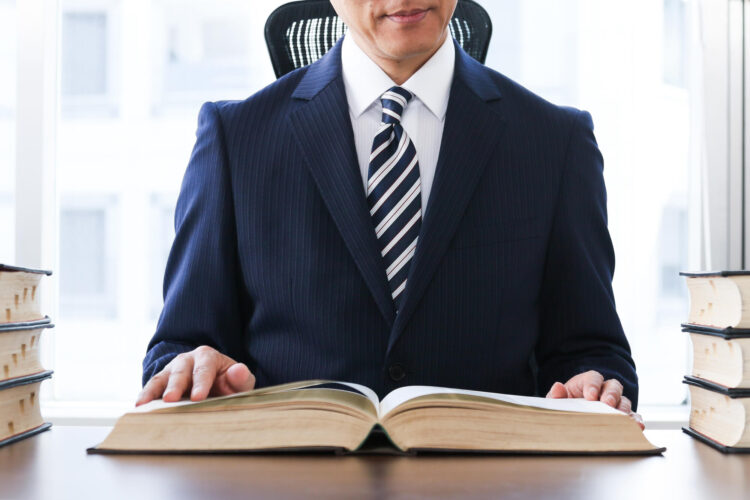「資金繰りが苦しく、もう借金が返せないかもしれない…民事再生を申請すれば、事業を継続できるって本当?」
経済的な困難に直面し、事業の継続が危ぶまれるなかで、民事再生法の利用を検討する方も多いでしょう。
民事再生は、事業を継続しながら事業や生活の再建を目指すための手段です。
しかし、その手続やメリット・デメリットを正しく理解していないと、適切な判断が難しくなります。
この記事が、事業の再建を目指すための第一歩を踏み出すために役立てば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 民事再生の概要
- 民事再生の申請手続の流れ
- 民事再生のメリット・デメリット
ここを押さえればOK!
この法律の主な目的は、事業や生活の再生を図ることです。
民事再生のメリットには、借金の大幅な減額、事業の継続、経営陣の交代不要などがあります。一方、デメリットとしては、担保権の実行リスク、信用の低下、再生計画の実行困難性などが挙げられます。
民事再生手続の流れは、申立て、再生手続の開始決定、債権者による債権届の提出、再生計画案の作成・認可、再生計画の実行といったステップを踏みます。
手続には申立手数料、郵便切手、予納金、弁護士費用などの費用がかかります。
弁護士に依頼しなくても民事再生の申請をすることはできますが、手続が煩雑で法律知識が必要であることから、一般的には弁護士に依頼することが多いです。
民事再生法とは?
民事再生法は、経済的に困難な状況にある企業や個人が、再生を目指して債務を整理するための法律です。
民事再生では、債務者が再生計画を立て、その計画に基づいて債務を返済します。再生計画は、裁判所に認可してもらう必要があります。
民事再生法の主な目的は、事業や生活の再生を図ることです。
これにより、債務者は経済的な再スタートを切ることができ、債権者も一定の回収を見込むことができます。企業だけでなく、個人も利用できるため、幅広い層に対応しています。
事業を継続しつつ借金を減らす制度には、ほかに「会社更生」もあります。
会社更生は、基本的に大規模な企業向けの制度であり、中小の企業や個人の場合には、民事再生が利用されることが一般的です。
民事再生と破産の違い
民事再生と破産は、どちらも債務整理の手段ですが、その目的や手続には違いがあります。以下の表で、主な違いをわかりやすく説明します。
| 項目 | 民事再生 | 破産 |
|---|---|---|
| 目的 | 債務者が自ら再生計画を立て、事業や生活の再建を目指す | 債務者の財産を清算し、債権者に分配することで債務を解消する |
| 債務者の状況 | 事業や生活を継続しながら再建を目指すため、一定の収入や資産があることが前提 | すべての財産を清算するため、事業の継続は困難 |
| 債務の扱い | 再生計画に基づき、債務の一部を減額・分割して返済 | 財産を清算し、残った債務は原則として免除される |
| 対象 | 企業および個人 | 企業および個人 |
民事再生は再建を目指す手続であり、破産は清算を目的とした手続であることがわかります。どちらを選ぶかは、債務者の状況や目的に応じて判断する必要があります。
民事再生のメリット
民事再生を申請することで、債務者には以下のようなメリットがあります。
(1)借金を大幅に減額できる
民事再生では、再生計画が認可されることで債務を減額することが可能です。
税金や養育費など一部の債務は減額の対象にはなりませんが、多くのケースでは借金が5分の1程度に減額されます。
ただし、どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によって異なります。
なお、借金の総額が100万円未満の場合、債務は減額されません。
(2)事業を継続できる
民事再生は、事業を継続しながら、事業を再建することを目的としているため、事業の継続が可能です。
再生計画に基づき、経済的な負担を軽減しながら事業を続けることができるため、従業員の雇用や取引先との関係も維持できる可能性があります。
(3)経営陣が交代しなくてもよい
民事再生では、経営陣の交代を必要としないため、現在の経営陣が引き続き事業を運営することができます。これにより、経営の一貫性が保たれ、再生計画の実行がスムーズに進むことが期待できます。
現在の経営陣の経験やノウハウを活かしながら、再建を目指すことができるでしょう。
民事再生のデメリット
民事再生を申請することで、債務者には以下のようなデメリットがあります。
(1)債権者に担保権を実行されるリスクがある
民事再生の手続中でも、担保権を持つ債権者はその権利を行使することができます。
これにより、担保として提供した財産が差し押さえられたり、競売にかけられたりするリスクがあります。
特に、重要な資産が担保に入っている場合、その資産を失うことで事業の継続が困難になるかもしれません。
なお、そのような場合でも、「担保権の実行手続の中止命令」の申立てなどにより、担保権の実行を防ぐ手段は存在します。
(2)世間や取引先などからの信用を失う可能性がある
民事再生手続を行うと、その情報が公にされるため、世間や取引先からの信用を失う可能性があります。信用の低下は、取引条件の悪化や新たな取引先の獲得が難しくなるなど、事業運営に大きな影響を及ぼすことがあります。また、従業員の士気にも悪影響を与える可能性があります。
ただし、そもそもの原因は経営状況の悪化であると考えられるため、必ずしも民事再生の申請をしたこと自体のデメリットとはいえないでしょう。
(3)再生計画の実行が難しい場合がある
再生計画が現実的でない場合や、計画通りに進まない場合、再建が失敗するリスクがあります。
特に、経済状況や市場環境の変化により、再生計画の実行が困難になることがあります。
再生計画の実行に失敗すると、最終的には破産手続に移行することになるかもしれません。
民事再生手続の流れ
民事再生手続は、以下のような流れで進行します。
(1)民事再生の申立て
債務者が裁判所に民事再生の申立てを行います。
申立てが受理されると、裁判所は手続の開始に向けた準備を進めます。
(2)再生手続の開始決定
裁判所が再生手続の開始を決定し、債権者に通知します。
申立てから2週間程度で、開始決定がなされることが多いようです。
(3)債権者による債権届の提出
通知を受けた債権者は、民事再生手続に参加するとともに債権届を提出します。
債務者はそれについて認否を行ったうえ、貸借対照表と財産目録を裁判所に提出します。
(4)再生計画案の作成・認可
債務者は、具体的な再生計画案を作成し、裁判所と債権者に提出します。再生計画案には、債務の返済方法や期間、事業の再建策などが含まれます。
債権者集会が開かれ、一定数の債権者の同意を得て再生計画案が可決されると、裁判所が再生計画案を認可します。
(5)再生計画の実行
認可された再生計画に基づき、債務者は返済を開始し、事業の再建を進めます。裁判所は、計画の進行状況を監督し、必要に応じて指導や調整を行います。
民事再生の申請に必要な費用
民事再生の申請には、たとえば以下の費用がかかります。
- 申立手数料(1万円程度)
- 郵便切手(数千円程度)
- 予納金
- 弁護士費用(弁護士に依頼した場合)
裁判所への予納金は、負債の総額に応じて金額が異なります。
たとえば東京地裁における法人再生の場合、負債総額が5.000万円未満であれば、予納金は200万円となります。
そして、民事再生は手続が煩雑なうえ、法律知識も必要なので、一般的には弁護士に依頼します。そのため、弁護士費用もかかると考えておいたほうがよいでしょう。
【まとめ】民事再生は、負債を減額しつつ事業の再建を図る手段のひとつ
民事再生は、経済的に困難な状況にある企業や個人にとって、債務を整理しながら事業や生活の再建を目指すために効果的な手段です。
この記事では、民事再生法の基本的な概要から申請手続の流れ、具体的なメリット・デメリットについて解説しました。
民事再生の申請は複雑で専門的な知識が必要となるため、専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
現実的な再生計画案を作成し、手続をスムーズに進めるためにも、民事再生を利用しようかお悩みの経営者の方は、企業法務を取り扱っている弁護士への相談を検討してください。
※現在、アディーレ法律事務所は法人に向けた民事再生のご相談・ご依頼を受け付けておりません。個人で民事再生を検討している方は「個人再生」のページをご覧ください。