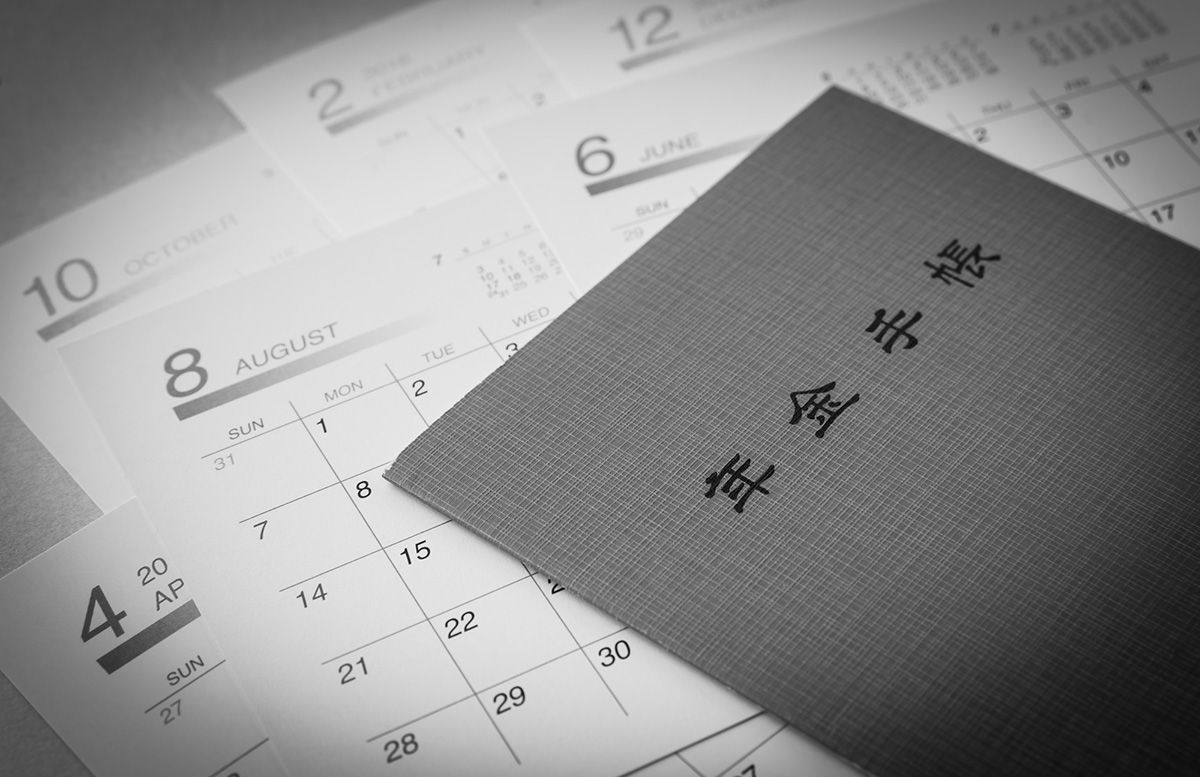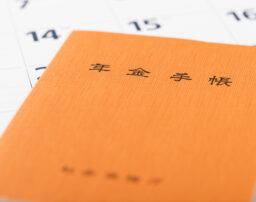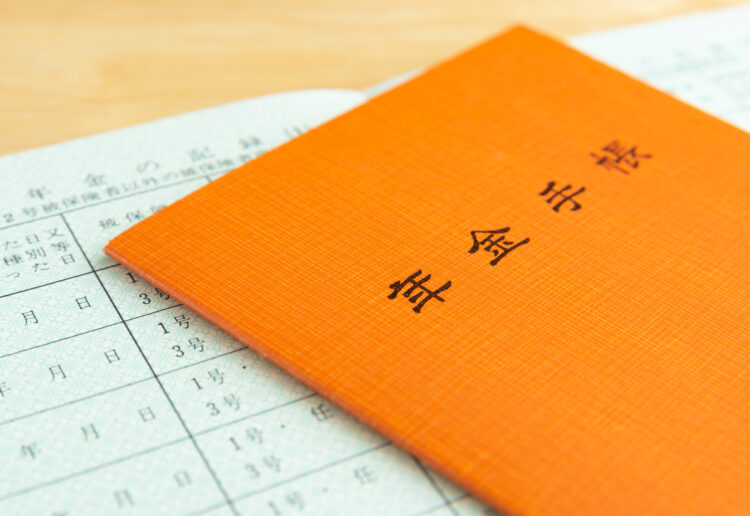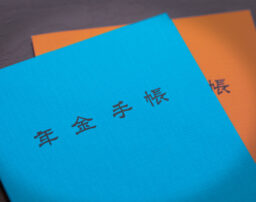国民年金保険料の滞納が続くと、将来の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
特に、差し押さえのリスクは避けたいものです。
この記事では、保険料を滞納した場合のリスクとその対策について詳しく解説します。
年金未納のリスクや、差し押さえを回避する具体的な方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読んでわかること
- 国民年金保険料を滞納することのリスク
- 年金保険料滞納による差押えの流れ
- 年金保険料滞納による差押えを防ぐ具体的方法
ここを押さえればOK!
また、滞納が続くと財産を差し押さえられる可能性もあります。これらのリスクを回避するためには、未納分の支払いを確実に行うことが重要です。
経済的な理由で支払いが困難な場合は、免除や猶予の制度を利用できる可能性があります。
借金問題を抱えている場合には、年金保険料の滞納を解消するためにも、債務整理を検討することが有効です。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
どの方法が一番適切かは人によって異なりますので、まずは弁護士に相談してみましょう。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

年金保険料を滞納するとどうなる?リスクを解説
国民年金の保険料を滞納すると、将来の年金受給資格を失う可能性や、受け取れる年金額が減少するリスクがあります。具体的には、加入期間が10年未満だと年金を受け取れない、将来受け取れる年金が少なくなる、遺族年金や障害年金を受け取れないなどの影響があります。
また、年金の滞納が続くと、財産を差し押さえられるおそれもあります。
これらのリスクを理解し、早期に対策を講じることが重要です。
(1)加入期間10年未満だと年金を受け取れない
老後の年金(老齢基礎年金)の受給資格を得るためには、保険料を納付していた期間や加入者であった期間などの合計が、一定年数=基本的には10年間の加入期間が必要です。
年金保険料を滞納して未納の期間が長いと、将来年金を受け取ることができないおそれがあります。
これにより、老後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があります。
最低限の加入期間を確保するために、未納分の支払いを早急に行うことが重要です。
(2)将来受け取れる年金が少なくなる
国民年金の保険料を滞納すると、65歳以上になったら受け取られる老齢基礎年金の額が減少します。
これは、老齢基礎年金の計算において、未納期間が反映されるためです。未納期間が長いほど、受け取れる年金額が減少します。
将来の経済的な安定を確保するためにも、未納分を早急に支払うことが重要です。
(3)遺族年金や障害年金を受け取れない
国民年金で受給できる年金は、老齢基礎年金だけではありません。
未納期間が長いと、老齢基礎年金だけではなく、遺族基礎年金や障害基礎年金を受け取る資格を失う可能性があります。
遺族年金や障害年金には、一定の納付条件があり、これを満たさない場合、受給資格を失ってしまうためです。
具体的な納付条件については、以下の通りです。
(3-1)遺族基礎年金の納付条件
例えば、国民年金の被保険者である間に死亡した時、その遺族に遺族基礎年金が支給されます。
しかし、死亡日の前日に、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が、国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日に、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
(3-2)障害基礎年金の納付条件
障害基礎年金を受け取るためには、原則として、障害の原因となる病気やけがの初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上である必要があります。
これを満たさない場合、障害年金を受け取ることができません。
参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
(4)滞納が続くと差押えされる可能性も
年金保険料を滞納したままでいると、財産(預金や給与、不動産など)を差押えされることがあります。
近年、日本年金機構は徴収体制を強化しています。日本年金保険機構の令和5年度の業務実績報告書によれば、「控除後所得が300万円以上かつ7ヶ月以上保険料を滞納している」場合には、強制徴収の対象となります。
差し押さえを回避するためには、未納分の支払いを行うことが重要です。
(4-1)国民年金保険料|滞納から差押えまでの流れ
国民年金保険料滞納を理由とした、差し押さえまでの流れは、以下の通りです。
- 催告状(納付督励)が届く
- 特別催告状が届く
- 差押予告通知が届く
- 差押え
これらのステップを経て、最終的に差押さえが実行されます。
(4-2)差し押さえの対象となるもの
差し押さえの対象となるものには、以下のものがあります。
- 給与のうち一定額
- 銀行預金
- 不動産
- 自動車
- 有価証券などの債権
一方、年金や生活保護費、家電や家具など生活必需品は基本的に差し押さえられません。
ただし、年金保険料を滞納した本人だけでなく、国民年金保険料の連帯納付義務者(世帯主や配偶者)の財産も差押えの対象となる可能性があります(国民年金法88条2項、3項)。
家族の財産が差し押さえられたら大変です。差し押さえされる前に、未納分の支払いを確実に行うことが重要です。
年金保険料を滞納している人が差押えされないための対処法
年金保険料を滞納している場合、差し押さえを回避するためには、未納分を速やかに納付することが重要です。
経済的な理由で支払いが困難な場合は、免除や猶予の制度を利用できる可能性があります。行うことができます。
また、免除や猶予制度が利用できなくても、未納分について、話し合いにより分割に応じてもらえることがあります。
大切なのは、放置せず滞納状態を解消するために行動することです。これにより、差し押さえのリスクを軽減することができます。
(1)未納分を納付する
未納分を速やかに納付することで、差し押さえのリスクを回避することができます。
年金保険料だけでなく、借金返済で生活が困難という場合には、すぐに債務整理を扱っている弁護士に相談しましょう。
任意整理などで家計を見直し、借金を整理することで、年金保険料を捻出できることがあります。
(2)免除や猶予制度の申請をする
まずは、日本年金機構の委託事業者から滞納分の保険料を支払うように電話や個別訪問経済的な理由で年金の支払いが困難な場合、免除や猶予の制度を利用できる可能性がありますので、国民年金の窓口で相談するとよいでしょう。
過去2年までさかのぼって申請可能です。
免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類あります。
これにより、差し押さえのリスクを回避できます。
ただし、免除を受けたままにしておくと、将来受け取ることのできる年金額が下がるので、経済的に余裕が出たら追納も検討しましょう(追納ができるのは過去10年)。
借金問題を抱える方は弁護士に相談を
国民年金の保険料を支払えない状態の方は、他に借金問題を抱えていて、返済に悩んでいるというケースも多いです。
その場合、年金保険料の滞納を解消するためにも、借金問題を解決する必要があります。
借金問題の解決方法としては、主に次の3種類あります
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
これらの債務整理により、生活を立て直すことで、保険料滞納を解消できるかもしれません。

(1)任意整理とは
任意整理では、借入先それぞれについて、まず、利息を支払い過ぎていないか、正確な負債の額を計算(払いすぎた利息があれば、その分負債の額を減らします)します。
そのうえで残った負債については、将来発生するはずだった利息をゼロにできないか、毎月の返済額を減らせないか、借入先と交渉します。
任意整理をすることにより、今よりも返済の負担が軽くなる可能性があります。
(2)個人再生とは
個人再生とは、返済できなくなってしまうおそれのある人が、裁判所の認可決定を得た上で、法律に基づき決まった金額を原則3年で分割して返済していく手続です。
ケースにもよりますが、任意整理よりも大幅に総支払額を減額できることがあります。
どのくらい減額されるかは、負債の総額や所持している財産などによって異なりますので、一度弁護士にご相談ください。
また、条件を充たしていれば、住宅ローンの残っている自宅を手元に残せる可能性があります。
なお、個人再生をしても税金など、減額されない負債が一部あります。
(3)自己破産とは
自己破産とは、財産・収入が不足し、負債を返済できなくなった場合に、裁判所から原則全ての負債について支払を免除してもらうこと(免責許可決定)を目指す手続です。
税金など一部の支払義務は、自己破産をしても支払義務が残ります。
一定の財産は処分しなければならない可能性がある、一定の職種については手続中は従事できなくなるなどの注意点はありますが、3つの手続の中で最も支払の負担を軽くできる可能性があります。
【まとめ】年金保険料未納は放置せずに対処を!
国民年金保険料の滞納がもたらすリスクには、受給資格の喪失、将来受け取れる年金額の減少、遺族年金や障害年金の受給できないおそれ、そして差押えの可能性があります。
これらのリスクを回避するためには、未納分の支払いを確実に行い、免除や猶予の申請を行うことが重要です。借金問題を抱える方は、弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。
債務整理をしても、滞納してしまった国民年金の保険料など公租公課の支払義務は、免除されません。
しかし、消費者金融等からの借金に関する負担は債務整理で軽減される可能性があります。借金が軽減されれば、その分年金保険料の支払が楽になる可能性があるのです。
アディーレ法律事務所では、債務整理を取り扱っており、債務整理についてのご相談は何度でも無料です。
また、ご依頼いただいた所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。(2025年1月時点)
債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。