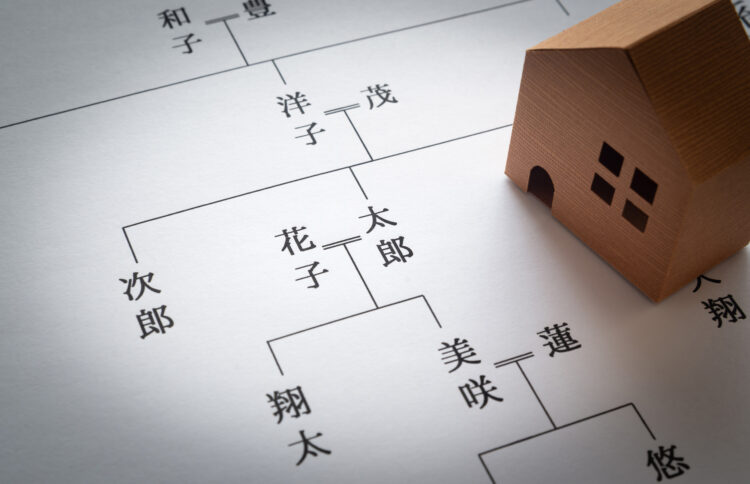「敷金から、ハウスクリーニング代とか、いろいろ引かれて敷金が返ってこなかったけど、納得がいかない。」
こんな体験をした方も多いでしょう。
2021年に、独立行政法人国民生活センターに寄せられた、原状回復や敷金のトラブルの相談件数は、1万2677件にも上ります。
このようにトラブルが多いにもかかわらず、これまで、原状回復や敷金に関するルールが、民法にほとんど定められていませんでした。
しかし、2020年4月に施行された民法改正により、原状回復や敷金に関する基本的なルールが明文化されました。
これにより、これまで曖昧であった原状回復や敷金の基本的なルールが、明確になりました。
ルールが明確になると、戦略を立てやすくなりますよね。
では、どのように民法改正されたのか、弁護士がわかりやすくご説明します。
原状回復義務の範囲の明文化
(1)民法上の規定
賃借人がどこまで原状回復義務を負うのかによって、返ってくる敷金の額や、手出しで払わなければならない費用の額が変わってきます。
今回の民法改正では、誰が原状回復の義務を負うのか、次のように明文化されました(民法621条)。
| 原状回復の範囲 | 賃借人が原状回復義務を負うもの(〇) |
|---|---|
| 1.通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗 | × |
| 2.賃借物の経年変化 | × |
| 3.賃借人に帰責事由がない損傷 | × |
| 4.1~3以外の、賃借物を受け取った後に賃借物に生じた損傷 | 〇 |
(2)ガイドライン
ただこの民法の規定だけだと、ちょっと分かりにくいですよね。
この点、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(2011年8月)に、誰が原状回復をすべきか詳しく記載されています。
このガイドラインは民法改正前に作成されたものですが、今回の民法改正と同趣旨の指針であるため、民法改正後も参考になります。
このガイドラインによりますと、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、化粧直し等のリフォームについては、「1.通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗」や「2.賃借物の経年変化」として、賃貸人の負担で行うべきものとなるのが通常でしょう。
また、地震や台風による損傷など、不可抗力による損傷は、「3.賃借人に帰責事由がない損傷」として、賃借人は原状回復義務を負わないこととなります。
他方で、たばこのヤニで壁紙が黄ばんだ、結露を放置しておいたらシミになったというような場合には、「4.1~3以外の、賃借物を受け取った後に賃借物に生じた損傷」として、賃借人が原状回復義務を負うことが多いでしょう。
(3)民法とは異なる特約の有効性
「誰が原状回復義務を負うか」を規定した、民法621条とは異なる特約を、賃貸人と賃借人の間で、結ぶこともできます。
しかし、あまりに賃借人に不利な特約内容である場合、その有効性には疑義が生じます。特に賃貸人が事業者、賃借人が消費者である場合には、消費者契約法10条に基づき無効となる可能性があります。
敷金の定義の明文化

今回の民法改正では、敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」と定められました(民法622条の2第1項)。
例えば、家賃や、原状回復費用の支払いを担保するために、賃借人が賃貸人に渡すお金が、敷金にあたります。
これによれば、賃貸人に渡すお金の名目が、「敷金」ではなく「保証金」であったとしても、上記の担保目的で渡しているとして、敷金として扱われることが多いでしょう。
他方で、「礼金」は、部屋を貸してくれたお礼として、賃貸人に渡すお金であることが多いので、敷金として扱われず、退去しても返ってこないお金であることが多いでしょう。
退去時に返ってくる可能性があるお金かどうかは、上記の担保目的があるか否かが重要です。契約書の記載をよく見てみましょう。
敷金の返還時期の明文化
今回の民法改正では、次のいずれかの場合に敷金を返す債務が発生すると明文化されました(民法622条の2第1項)。
1.賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
引用:民法622条の2第1項
2.賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき
多くの方が遭遇するのは、1の場面です。
1によれば、賃貸借の契約期間が満了しただけでは、敷金は返してもらえません。
敷金を返してもらうためには、賃貸物の返還までする必要があります。
なお、賃貸人に無断で、賃貸物件に荷物を残したまま、人間だけ退去したとしても、「賃貸物の返還」をしたとはいえません。
敷金が返ってこないどころか、新たに賃料が発生する可能性がありますので、注意しましょう。
敷金返還債務発生前の敷金の効力の明文化
今回の民法改正では、敷金を返す債務が発生する前でも、賃借人が、「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる(民法622条の2第2項)」と明文化されました。
例えば、賃貸中に家賃の支払いが滞った場合は、賃貸人は、その滞納家賃相当額を敷金から差し引くことができます。
これを読んで、「じゃあ、お金に困ったら家賃を滞納して敷金から引いてもらおう」と考える賃借人の方もいるかもしれません。
しかし、賃借人から賃貸人に対しては、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することはできません(民法622条の2第2項)。
【まとめ】民法改正で原状回復と敷金に関するルールが明文化
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 民法改正で原状回復義務の範囲についてルールが明文化された
| 原状回復の範囲 | 賃借人が原状回復義務を負うもの(〇) |
|---|---|
| 1.通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗 | × |
| 2.賃借物の経年変化 | × |
| 3.賃借人に帰責事由がない損傷 | × |
| 4.1~3以外の、賃借物を受け取った後に賃借物に生じた損傷 | 〇 |
- 民法改正で敷金の定義が明文化された
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」(民法622条の2第1項)。
- 民法改正で敷金の返還時期が明文化された
(民法622条の2第1項)
「1.賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき
2.賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき」
- 民法改正で敷金返還債務発生前の敷金の効力が明文化された
(民法622条の2第2項)
「賃借人が、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる」
以上のように、民法改正で、原状回復と敷金に関して基本的なルールが明文化されました。
とはいえ、今後も、どの損傷が賃借人の原状回復義務の対象となるのか、争いになることもあるでしょう。
どうしたらいいのか判断に困ったら国民生活センターや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。