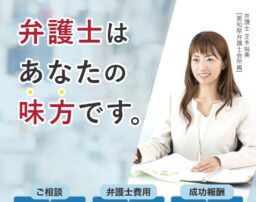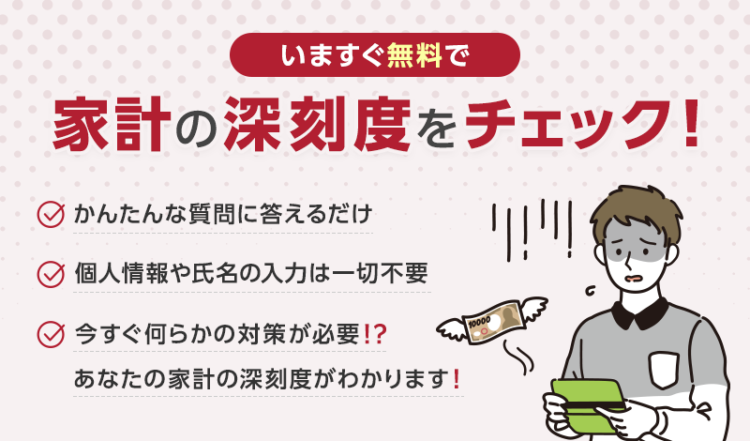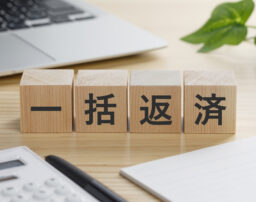「親からお金を借りたけど、返済義務はあるの?」
親子間の金銭トラブルは、家族だけにあいまいになりがちで、どう対処していいか分からず、精神的な負担も大きいものです。
感情的な問題に発展しやすく、親子関係にひびが入るケースも少なくありません。
この記事では、親子間の借金にまつわる法的なルールを弁護士がわかりやすく解説します。返済義務の有無から、借用書の書き方、税金の問題、さらには親(子)の借金を背負わずに済む方法まで、あなたの不安を解消するためのヒントをお伝えします。
ここを押さえればOK!
借用書がない場合でも、銀行振込の記録やメールなど、借金の存在を証明できる客観的な証拠があれば、借金の証拠となり得ます。
また、親子間の借金でも、出世払いなど曖昧な返済約束や、利息なしで高額な金銭を貸し借りすると、税務署から贈与と判断され贈与税の対象と判断されるおそれがあります。
もし親子間の借金返済が困難になった場合でも、話し合いや債務整理で解決できるかもしれません。
借金問題は一人で悩まずに、アディーレ法律事務所にご相談ください。
親子間の借金に返済義務はある?法的な解釈
親子間でお金の貸し借りをする際、「家族だから」という理由で返済義務はないと考えがちですが、法律上の返済義務は発生します。
法的には、親子間であっても、金銭消費貸借契約(借金の契約)が成立すれば、借りた側には返済する義務が生じます。
口約束でも契約は成立しますが、後々のトラブルを避けるためには、借用書を作成するなど書面で証拠を残すことが重要です。
親子間だからこそ、お金のやり取りを「なあなあ」にせず、法的なルールに則って行うことで、関係性を損なわずに済みます。
(1)親子間でも「借金」とみなされるケース
親子間でお金のやり取りをする場合、それが「借金」なのか「贈与」なのかが大きなポイントとなります。
例えば、親から子へのお小遣いを「借金」と考える人はいないでしょう。これは当然、親が子どもに無償であげる意思で子どもに渡し、子どももその意思を理解してもらうものですので、贈与になります。
このように、贈与であれば、親子間で金銭のやりとりがあっても返済義務はありません。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。引用:民法549条|e-gov
ただし、贈与は、年間110万円を超えると贈与税の課税対象になるので注意が必要です。
一方、返済の約束をしてお金を受け取った場合は、借金(金銭消費貸借契約)とみなされ、法的な返済義務が生じます。
口頭でも契約は成立しますが、「借りた借りてない」の不毛なトラブルを避けるためには、お金を貸すときには、親子であっても借用書を作成するとよいでしょう。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。引用:民法587条|e-gov
(2)借金と「贈与」はどう違う?
法律上、「借金」と「贈与」は明確に区別されます。
借金は「返済の約束がある金銭の貸し借り」であり、民法上の金銭消費貸借契約に該当します。これに対し、贈与は「返済義務のない、一方的な財産の譲渡」であり、民法上の贈与契約に該当します。
親子間で多額のお金のやり取りをする際は、それが借金なのか贈与なのかを明確に説明できるよう、客観的な証拠、つまり契約書面を残すことが大切です。
親子間の金銭トラブルを回避するポイント
親子間の金銭トラブルを避けるためには、親子間の借金であっても、口約束ではなく書面を作成しましょう。
(1)借用書作成の重要性
「親子だから信用できる」と考えて借用書を作成しないケースは多いですが、これがトラブルの原因になりがちです。借用書をきちんと作成するようにしましょう。
特に、親が亡くなった後、相続人同士でトラブルになることもあります。仮に、相続人の1人が親から借金をしていて返していないのに、その分をなかったこととして相続手続きをするとなれば、他の相続人が不公平と感じるのも当然です。
法的には、被相続人が特定の相続人に対して貸し付けていた未返済の借金(貸付金)は、被相続人の金銭債権として、遺産を構成します 。この金銭債権は、原則として「可分債権」と見なされ、相続開始と同時に、法定相続分に応じて各相続人に当然に分割承継されます 。つまり、被相続人から借りていた相続人以外の各相続人は、借金についてそれぞれの法定相続分に相当する額を、借りていた相続人に対して個別に請求できるということになります。
(2)借用書に記載すべき項目
借用書は、金銭消費貸借契約であることを明確にするために、必要な項目を正確に記載する必要があります。
具体的には、「誰が誰に」「貸した金額」「借りた側がお金を受け取ったこと」「返済期限」「利息の有無」「返済方法」といった点です。
【金銭消費貸借契約書の書式例】
第1条(金銭の貸付)
□□(甲)は◆◆(乙)に対し、□年□月□日、金〇円を利息なしで貸し付け、乙はこれを受け取った。
第2条(返済方法)
乙は甲に対し、前条の借入金全額を、□年□月□日までに、下記銀行口座に振り込む方法で返済する。なお、振込手数料は乙負担とする。
記
銀行名 〇〇
口座番号 〇〇
口座種別 〇
口座名義 〇
本契約を証するため、本書を2通作成し、甲および乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
□年□月□日
甲:
氏名:〇〇〇〇 印
住所:〇〇〇〇
甲:
氏名:〇〇〇〇 印
住所:〇〇〇〇
※きわめてシンプルな消費貸借契約書の書式です。分割払いにする、期限の利益喪失条項を加える、紛争になったときの合意管轄を定めるなど、契約書の内容は当事者の希望によって異なります。
(3)借用書がない場合のトラブル対処法
借用書がなく、親が貸したと考えているお金について、子が「あれは貰ったお金だ」という金銭トラブルが生じるかもしれません。
借用書がない場合でも、借金の存在を証明できる可能性はあります。
例えば、銀行振込の記録や、メール、SNSのやり取りなど、金銭のやり取りの事実、返済に関する合意があったことがわかる客観的な証拠を探しましょう。
メールで「この日、振り込んだお金は借金の一回目の返済分」といったやり取り、実際の振り込みの記録などがあれば、借金であることの証拠となり得ます。
ただし、証拠がなければ借金であることを証明することは難しくなるため、可能な限り借用書を作成しておくのが賢明です。
親子間の借金の税金問題
親子間のお金のやりとりでは、税金(贈与税)の問題も考慮する必要があります。
多額の金銭を、口約束で親が子に貸し付けて返済時期は「出世払い」などとあやふやにして返済を求めず、子どもも返済できていないようなケースを考えてみます。
このようなケースでは、税務署により、借金ではなく贈与とみなされ、贈与税の対象となることがあります。
借用書もないので、借金であると証明することもできません。
また、借金に利息を付けるかは当事者間の自由ですが、多額の金銭を利息なく貸し付けると、利息分について贈与と判断されるおそれもあります。
参考:No.4420親から金銭を借りた場合|国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm)
親子間の借金を返済できない場合はどうなる?
もし親子間の借金を返済できなくなった場合でも、法的な解決策は存在します。
債務整理
借金の返済が困難になった場合、親からした借金であっても債務整理は可能です。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類の方法があり、弁護士に相談することで、状況に応じた適切な解決策を提案してもらえるでしょう。
親に迷惑をかけたくないという場合は、他の借金について任意整理の手続きをとり、月々の返済負担の軽減を目指したうえで、親からの借金を返済するお金を確保するという方法もあります。
ただし、親子間の借金の場合、話し合いで解決を目指すケースも多いです。返済が難しくなったら放置せず、早めに親と話し合うことが大切です。
他の借金もあり返済が苦しいような場合には、1人で悩まず、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
親(子)の借金の肩代わりは義務ではない
親が借金を抱えており、その返済を肩代わりしてほしいと頼まれることもあるかもしれません。その逆もあるかもしれません。
しかし、法律上、親は子の借金返済義務は原則としてありません。子も、親がした借金の返済義務は原則としてありません。
親(子)が契約した借金は、親(子)自身の債務だからです。
例外的に、親(子)の借金を背負うのは、相続して借金も引き継いだケースや、(連帯)保証人になっているケースなどです。
親子であってもそれぞれ別の人格を有し、それぞれの人生があります。安易に借金の肩代わりをせず、まずは債務整理を扱う弁護士に相談することをお勧めします。
【まとめ】
親子間の借金には、たとえ口約束であっても法律上の返済義務が生じます。後々のトラブルを避けるためには、贈与と区別するためにも、借用書を作成し、金額や返済方法、利息などを明確にしておくことが重要です。
「借金問題を抱えてどうしたらいいか分からない」「法律の専門家に相談したい」そんな悩みを抱えている方は、一人で悩まずにぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。
「親からお金を借りたけど、返済義務はある?」と不安なあなたへ。親子間の借金でも、法的には返済義務が生じます。この記事では、借用書の書き方や贈与税の問題など、親子間の金銭トラブルの注意点を弁護士がわかりやすく解説します。