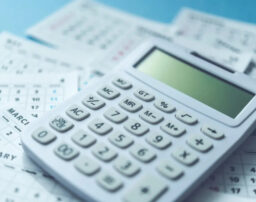「督促」という言葉を耳にしたとき、あなたはどのような印象を持ちますか?
単なる支払いの催促?それとも、何か重大な法的問題?
実は、督促に対して適切に対応しないと、訴えられて財産を差し押さえられるなど、深刻な結果を招く可能性があります。
本記事では、督促の意味、催促との違い、そして適切な対応方法まで、弁護士が分かりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
- 督促とは
- 催告書と督促状との違い
- 時効の完成を阻止する催告とは
- 督促の一般的な流れ
- 督促を放置したときの法的リスク
- 昔の借金について督促状が届いたときの対処法
ここを押さえればOK!
督促の一般的な流れは、電話やメールでの連絡から始まり、督促状の送付、最終督促へと進みます。
督促状を放置すると、期限の利益を喪失したり、法的手続きに発展する可能性があります。特に税金の督促は迅速な対応が必要です。
昔の借金について督促があった場合、消滅時効が完成している可能性があるため、債権者に連絡せずにまず弁護士に相談することをお勧めします。
また、支払いが困難な場合にも、1人で悩まずに早い段階で借金問題を扱う弁護士に相談しましょう。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

督促とは?
金融機関から借りたお金を返せなくなると、返済を求められます。
そのことを「督促」といいます。書面で送られてくると、その書面を「督促状」といいます。このように、督促は、債権者が債務者に対して行う支払い要求です。
無視して放置していると、訴えられたりして深刻な問題に発展する可能性があります。
(1)督促が行われる主な場面
督促は、支払を求める様々な場面で行われます。主に以下の3つのケースが多いです。
- 事業取引:
- 商品やサービスの代金未払い
- 金融取引:
- ローンや借入金の返済遅延
- 税金:
- 国税や地方税の滞納
特に税金の督促は、督促状を発してから10日経つまでに納付がなければ滞納処分(財産の差し押さえ)をしなければならないと法律で定められており(地方税法331条1項1号等)、通常の債権より速いスピードで差押えにつながる可能性があります。
督促を受けた場合は、適切かつ迅速に対応することが重要です。
(2)催促書との違い
「催告書」という名前で支払いを求める書面がありますが、督促状と法律的な違いはありません。
実務上は、先に督促状が送られてきて、返済がなければ催告書が送られてくる、という流れが多いようです。
時効の完成を阻止する「催告」とは
一方、民法には「催告」という制度があります(民法150条1項)。
貸金業者から借りたお金は、基本的に返済しないまま返済日や一括請求を受けた日等から5年を過ぎると、消滅時効が完成して返済義務を免れます。
債権者が、この消滅時効の完成を阻止するために行うのが「催告」です。催告をすると、1回だけ、消滅時効の完成を6ヶ月間先延ばしにできます。
催告をすることで、時効の完成を阻止して、余裕をもって裁判などの手続ができるようになるのです。
民法上の「催告」は、一定の様式が決まっているものではありません。そのため「貸したお金を返してください」という内容さえ含まれていれば、借主に送る書面がどのようなタイトルであろうとも構いませんし、電話やメールで行うことも可能です。
そのため、「督促状」という名前であっても法律上の催告に当たることがあります。一方で、「催告書」という名前であってもきちんと相手にお金を請求する旨が書かれていなければ法律上の催告に当たらない場合もあります。
督促の一般的な流れを理解しよう
督促は通常、次のような流れで段階的に行われます。
(1)電話やメールでの督促
督促について法律上の決まりはありませんので、金融業者各社によりやり方は異なります。伝える内容も定められておらず、統一的なものではありません。
ただ、最初の段階は、通常、電話やメール、ショートメッセージなどで丁寧な支払いのお願いから始まります。
この段階では、まだ友好的な解決の余地があることが多いです。債務者は誠実に対応し、支払い計画を提案するなどの対応が効果的でしょう。
(2)督促状送付の段階
電話やメールなどの手段で督促しても返済されない場合、次は督促状の送付段階に移ります。普通郵便ではなく、届いたことが分かるように配達証明付郵便などで送付されることもあります。
この段階では、債権者側の姿勢が少し厳しくなります。債務者は督促状を受け取ったら、内容をよく確認し、迅速に対応することが重要です。
1度督促状を送っても返済がない場合、複数回送られてくることがあります。
手元にお金がなく返せない場合には、なるべく早く借金問題を扱っている弁護士に相談して、債務整理を検討するようにしましょう。
(3)最終督促
最終段階として、「〇日までにご入金いただけなければ法的手段を検討せざるをえません」などという、法的手段を取ることを示唆した書面が届きます。
この段階に至ると、返済しないで放置すると訴訟など法的手続きに発展する可能性が非常に高くなります。
借金問題について弁護士に相談し、債務整理など適切な対応を取ることが強く推奨されます。

督促状を放置するとどうなる?法的リスクを解説
督促状を放置することは、問題の解決を先送りにするだけでなく、状況を悪化させるおそれがあります。
督促状を受け取ったら、速やかに対応することが重要です。
以下、督促状を放置した場合に生じる主なリスクを2つ説明します。
(1)期限の利益喪失のリスク
督促に対応せず返済しないでいると、期限の利益を喪失する可能性があります。
期限の利益喪失とは、分割払いなどの利益を失い、残債務全額の即時支払いが求められることです。
分割払いの返済を定めた貸付の契約では、通常、所定の回数分、返済の遅れが生じたときには、期限の利益を喪失すると定められています。
期限の利益を喪失すると、分割払いできるというメリットを失い一括払いしなければなりませんので、債務者に非常に重大な影響を与えます。できれば避けるべきです。
督促を受けたら適切に対応し、必要に応じて返済計画の見直しなどを債権者と交渉することが重要です。
(2)法的手続きへの発展可能性
督促状を放置し、一括請求されても返済しないでいると、通常、金融機関は裁判所を利用した解決方法を選択します。
主な裁判所の手続きは、支払督促、裁判、強制執行です。
まず、金融機関が訴訟の提起や支払督促の申立てを行い、裁判所での手続きが始まります。債務者側は、「訴状」や「支払督促」といった書面が届くことで、裁判所での手続きが始まったことを知ることができます。
訴状や支払督促は、必ず開封し、内容を確認しましょう。
特に支払督促は、受領日からこの2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者(貸主)の申立てにより「仮執行宣言付支払督促」が届きます。これにも異議申し立てをしないと、差押えが可能な状態となってしまいます。
支払督促が届いた場合、迅速な対処が不可欠ですので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
法的手続きに発展すると、解決がより困難になりますので、早期の対応が極めて重要です。督促状を受け取ったら、内容を確認して適切な対応を取るようにしましょう。
昔の借金について督促があったら
「最後の返済から長い間経っているのに督促状が届いた!これって連絡した方がいいの?」
基本的に督促状は、放置せずすぐに対応すべきです。
しかし、昔の借金について突然督促状が届いたときは別です。あわてて連絡したり、借金を返済したりせず、まず、消滅時効が完成していないかを確認します。
督促状にある約定返済日などの日付が5年以上前で、返済日から一切返済していない場合などは、消滅時効を援用して、返済せずにすむ可能性があります。
消滅時効を援用できるかどうかは、借りた金融機関ではなく、借金問題を扱っている弁護士に相談しましょう。金融機関は借金を返してほしくて督促状を送っているわけですので、「消滅時効援用できるのでは?」と質問しても、債務者に有利な説明をすることは期待できません。
弁護士に相談し、消滅時効の完成を主張できるのであれば、弁護士に依頼して時効の援用の手続きを行ってもらうとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
督促に関しては、債権者・債務者双方からよく質問が寄せられます。以下、特に重要な3つの質問について回答します。
(1)架空請求の督促状にはどう対応すべき?
メールで、架空請求の督促状を受け取ることもあるようです。見覚えのない会社や団体から督促を受けた場合には、詐欺である可能性もありますので、すぐに支払ったり、請求先に連絡したりすることは避けましょう。支払ってしまい、詐欺だと判明した場合、取り戻すのは一般的に困難です。
ネットで社名やメールの内容を検索すると、架空請求であるかどうかヒントが得られることがあります。
また、不安であれば消費者センターや警察に相談するとよいでしょう。
(2)税金の督促には特別な対応が必要?
税金の督促には、以下の特徴があります。
- 行政処分としての性質:督促は差押えの前提要件であり、行政機関による処分とされる。
- 滞納処分のリスク:一定の日までに完納しなければ、滞納処分(財産の差し押え)を受けるおそれあり。
- 延滞税の加算:納付が遅れると、遅れた日数分延滞税が加算される。
税金の督促は一般の債権よりも深刻な結果をもたらす可能性があるため、迅速かつ誠実な対応が極めて重要です。
すぐに役所の担当窓口にて、分割納付や、納税猶予制度の利用の可否などを相談しましょう。
【まとめ】督促への適切な対応で法的リスクを回避しよう
督促状を受け取ったら無視せず、内容を確認し迅速に対応することが重要です。
支払いが困難な場合は、誠実に交渉を行いましょう。必要に応じて借金問題を扱う弁護士に相談することも検討してください。
弁護士はあなたの借金問題を解決するために真摯に取り組みます。
アディーレ法律事務所では、債務整理についてのご相談を無料で受け付けております。
また、アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2025年1月時点)。
督促状を受け取って対応方法にお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。