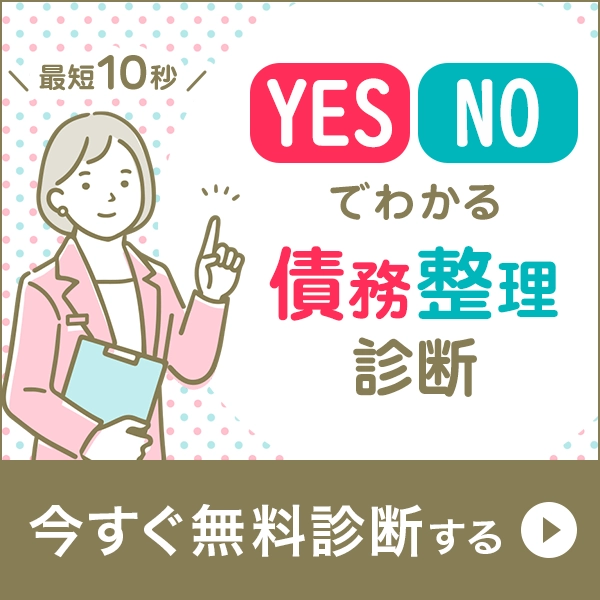不当利得とは、本来受け取るはずでない人が受け取った利益のことをいいます。
例えば、盗まれたお金や物、CMなどでよく耳にする「過払い金」なども不当利得に当たります。
盗まれたお金や物、過払い金を返してもらうことは、法律上認められた正当な権利です。
「不当利得について知りたい」「不当利得ってどうすれば返してもらえるの?」という方は、この記事を読んで、不当利得について勉強しましょう。
この記事では、次のことについて弁護士がわかりやすく解説します。
- 不当利得とは
- 不当利得の返還請求をするための要件
- 不当利得の返還を求める流れ
- 不当利得返還請求の時効
ここを押さえればOK!
不当利得の返還を求めるには、利益を受け、他人に損失を与え、その利益と損失に因果関係があり、利益を得たことに法律上の原因がないことが必要です。
不当利得を返してもらうためには、証拠を集めて請求し、交渉や訴訟を行い、差押えや強制執行をすることもあります。不当利得の返還には時効があるため、5年または10年以内に行使しなければなりません。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
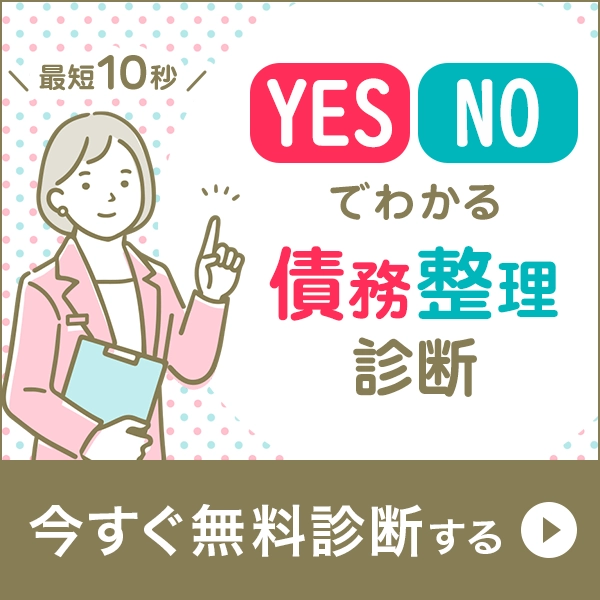
不当利得とは
不当利得とは、法律上受け取る権利がないにもかかわらず、他人の財産又は労務によって受けた利益のことです。
例えば、あなたがお金を盗まれたとします。この場合、盗まれたお金を民法上「不当利得」と呼び、盗まれたお金を犯人から取り戻す権利のことを民法上「不当利得返還請求権」といいます。
民法703条では、不当利得について、次のとおり定められています。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
引用:民法703条
不当利得にあたる4つの典型例とは
まず、不当利得になる4つの典型例をみて、「不当利得」と「不当利得返還請求権」のイメージをつかんでみましょう。
例えば、不当利得に当たる典型的なケースは、次の通りです。
- 口座を間違って振り込んでしまったお金
- 通販で商品を購入後にキャンセルした際、すでに払ってしまった代金
- 会社で経理担当者に不正な使い込みをされて、失ったお金
- 借金で利息制限法の上限を超えて払いすぎてしまった利息
「これらのお金を返してください」という権利が「不当利得返還請求権」ということになります。
そして、これらの不当利得返還請求のうち「『借金で利息制限法の上限を超えて払いすぎてしまった利息』を返してください」というのが、CMなどでよく耳にする「過払い金請求」にあたります。
不当利得請求権の4つの要件とは
不当利得返還請求をするためには、次の4つの要件を満たすことが必要です。
- 他人の財産または労務によって利益を受けること
- 他人に損失を及ぼしたこと
- 1.の利益と2.の損失との間に因果関係があること
- 利益に法律上の原因がないこと
くわしく見ていきましょう。
(1)他人の財産または労務によって利益を受けること
まず、「他人の財産または労務によって利益を受けること」が必要です。
例えば、他人のお金や他人を雇用関係なく働かせて、それによって得たお金などが当てはまります。
(2)他人に損失を及ぼしたこと
次に、「他人に損失を及ぼしたこと」が必要です。
例えば、お金が盗まれた場合を考えてみましょう。この場合、盗まれたお金が損失になります。
(3)利益と損失の間に因果関係があること
次に、「利益と損失の間に因果関係があること」も必要です。
例えば、Aさん(仮称)のお金が盗まれたという場合には、Aさんが受けた損失と盗んだ人が得た利益との因果関係は明らかといえます。
一方、Bさん(仮称)がある商品を売っていて、Cさん(仮称)がその商品と競合する商品を売っていた場合を考えてみましょう。
この場合、本来であればBさんの商品を購入していた客がCさんのところに行ってしまい、Bさんは損失を被っているとも言えます。しかし、それは、市場で競合している以上仕方のないことで、Bさんが受けた損失とCさん得た利益の間に因果関係があるというのは難しいでしょう。
(4)利益に法律上の原因がないこと
最後に、「利益に法律上の原因がないこと」も必要となります。
例えば、通販ですでに代金を払ってしまったが、その後に購入をキャンセルした場合で考えてみましょう。
この場合、購入をキャンセルする前は、店と客との間に売買契約が成立しているので、払ってしまった代金には法律上の原因があるといえます。
一方、購入をキャンセルした場合には、売買契約もキャンセルされ、法律上の原因がなくなっているので、払ってしまった代金には法律上の原因がないといえるでしょう。
「利益の存する限度で返還する」ってどういう意味?
民法703条の条文をみると、「利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」とありますが、これはどういう意味なのでしょうか。
不当利得の返還が求められた場合には、「現存利益」の範囲で不当利得を返還することになっています。
例えば、あなたの口座に間違ってお金が振り込まれたケースで考えてみましょう。
口座に間違ってお金が振り込まれていることを知らずに、そのお金を借金返済に充てたという場合には、これによってあなたは借金の返済を免れるという利益を得ています。そのため、借金の返済に充てたお金は「現存利益」として返さなければなりません。
一方、口座に間違ってお金が振り込まれたことを知らずに、そのお金をギャンブルに充てた場合には、すでにそのお金はなく、それによる利益は何も残っていません。そのため、「現存利益はない」とされ、ギャンブルに充てたお金は返す必要がないとされてしまうのです。
このように、不当利得の返還は、現在に残っている利益(現存利益)の範囲で返せばいいとされています。
利息まで請求できる場合とは?
不当利得と合わせて利息も請求できるケースがあると聞きました。どういう場合でしょうか。
確かに、不当利得の返還を求める場合に、不当利得だけではなく、利息まで求めることができる場合があります。
ここでは、あなたが間違った口座にお金を振り込んでしまったケースで考えてみましょう。
この場合に、相手が「間違えて振りんだお金だ」ということを知っていれば、間違って振り込んだお金と合わせて利息も請求できるのです。
この間違えて振り込まれたこを知っているにもかかわらず、お金を返さずにいる人を「悪意の受益者」といいます。「悪意」といっても、人をわざと困らせようとするなどといった意味とは違って、単に「そのお金が不当利得だと分かっていた」くらいの意味です。
このように、不当利得を得ていた人の中でも、「悪意の受益者」であれば、不当利得だけでなく、「利息」も請求することができるのです。
悪意の受益者に当たる場合には、現在残っている利益(現存利益)の範囲ではなく、不当利得全額と利息を支払う必要があります。
不当利得の返還を求める流れとは
次に、不当利得の返還を求める流れについてみていきましょう。
(1)相手が不当利得を得た証拠を集める
不当利得の返還を求める場合、これまで説明した4つの要件を証明する証拠が必要です。
例えば、過払い金の返還を求める場合には、お金を貸し借りしたことがわかる書類や利率や返還履歴がわかる取引履歴などが必要となります。
実務では、不当利得の返還を求める側が、証拠を集め、「私には請求する権利がある」ということを証明するのが原則です。そのため、不当利得の返還を求める場合には、証拠を集めることが重要になってくるのです。
(2)不当利得の返還を請求・交渉をする
証拠が集まったら、不当利得の返還を請求し、相手と交渉をすることになります。
不当利得の返還を求める場合や弁護士に依頼した場合、すぐに裁判というイメージがあるかもしれません。しかし、請求をしてすぐに返還に応じてくれたり、話し合いで解決したりする場合には裁判はしないことが多いです。
裁判所の手続きの一つではありますが、調停委員も交えて話し合う手続き(民事調停)を使うこともあります。
参照:民事調停|裁判所
(3)裁判所へ訴訟を提起する
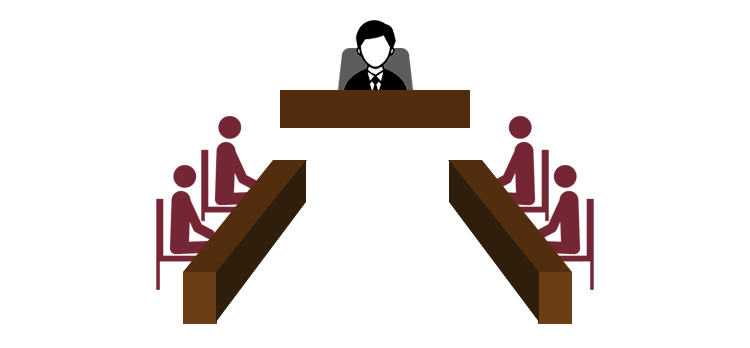
相手が交渉に応じない場合には、地方裁判所や簡易裁判所(※請求する金額によって異なります)に訴訟を提起することになります。
訴訟は「一度だけ開けば終わり」ではなく、一度で終わることはほとんどありません。月に1回程度裁判が行われ、平均審理期間(民事第一審)は10.5か月と解決までに時間がかかる傾向にあります(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)から引用)。
参照:裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)(令和5年7月28日公表)
参照:民事訴訟|裁判所
個人で訴訟をすることもできますが、訴訟には、お金がかかるのはもちろんのこと、定期的に裁判所に通ったり、提出する書類を作ったりと負担が大きいのが実情です。訴訟を起こす前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。
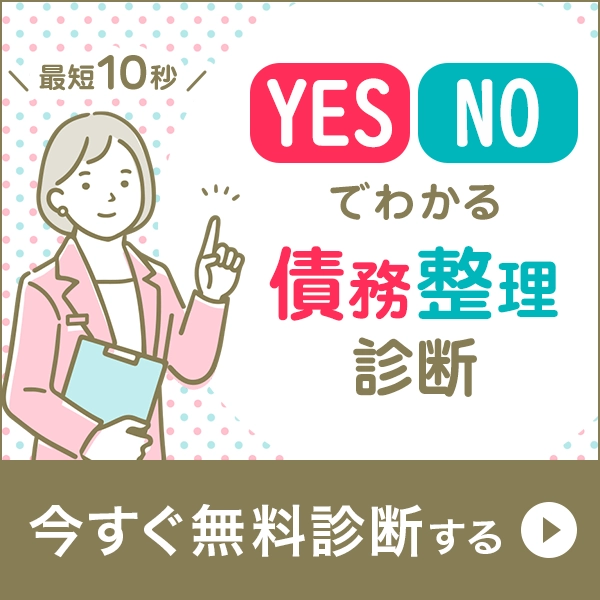
(4)差押え・強制執行をする
「裁判に勝てば、もう終わり」ではありません。お金を回収するためには、差押えや強制執行が必要な場合もあります。
裁判が終わり、判決が出て、すぐにお金を払ってくれる人であればいいですが、判決が出てもお金を払わない人います。こういう人には、相手の財産を差押えや強制執行をすることで、お金を回収します。
参照:民事執行手続|裁判所
不当利得の返還の時効はいつまで?
不当利得の返還は、いつまでも請求できるものではありません。
時効を迎えてしまうと、不当利得の返還を求めても、相手に「時効を援用する」と言われてしまえば、返還を求めることができなくなってしまいます。
時効は次の2つの基準によって判断され、いずれか早いほうで時効期間が満了します(※2020年4月1日以降に不当利得が発生した場合)。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
引用:民法166条1項
1.債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
2.権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
例えば、あなたが間違った口座にお金を振り込んでしまった場合で考えてみましょう。
この場合、間違って振り込んでしまったことに気づいた時から5年間、お金の返還を求めなければ時効になります。一方、間違って振り込んでしまったことに気付かなかった場合には、振り込んだ時から10年間、お金の返還を求めなければ時効となってしまいます。
このように、不当利得の返還はいつまででも請求できるというものではありません。不当利得の返還をしたいという方は、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
「時効についてもっと知りたい!」「時効にもうすぐなりそう…時効の中断方法は?」という方は、はこちらの記事もご覧ください。
【まとめ】不当利得とは法律上受け取る権利がないのに得た利益
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 不当利得を返還するよう求めるためには、次の4つの要件を満たす必要がある。
- 他人の財産または労務によって利益を受けること
- 他人に損失を及ぼしたこと
- 利益と損失との間に因果関係があること
- その利益に法律上の原因がないこと
- 不当利得返還請求権には次の2つの時点のいずれか早い時点で時効となる(※2020年4月1日以降に不当利得が発生した場合)。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
ここまで「不当利得」についてご説明してきましたが、特に過払い金請求は弁護士に依頼するのがおすすめです。
個人でやっても、消費者金融や銀行は相手にしてくれなかったり、証拠集めもなかなか難しかったりするのが実情です。
しかし、弁護士であれば、消費者金融や銀行も対応してくれ、過払い金の返還を実現できる可能性を高めることができます。
また、アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。
完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2024年5月時点。業者ごとに判断します)
「借金を長年してきたけど、過払い金がディーレ法律事務所にご相談ください。