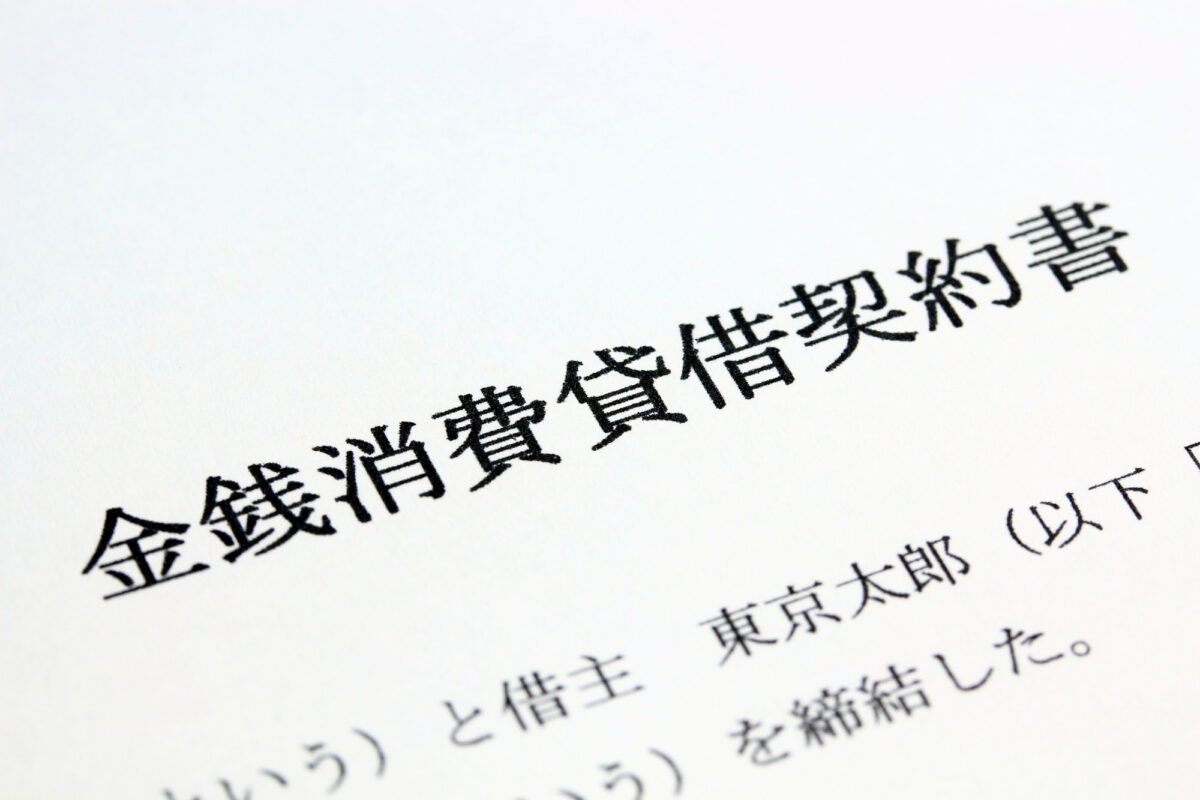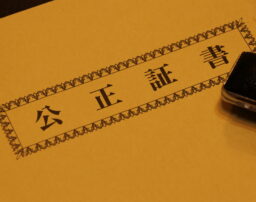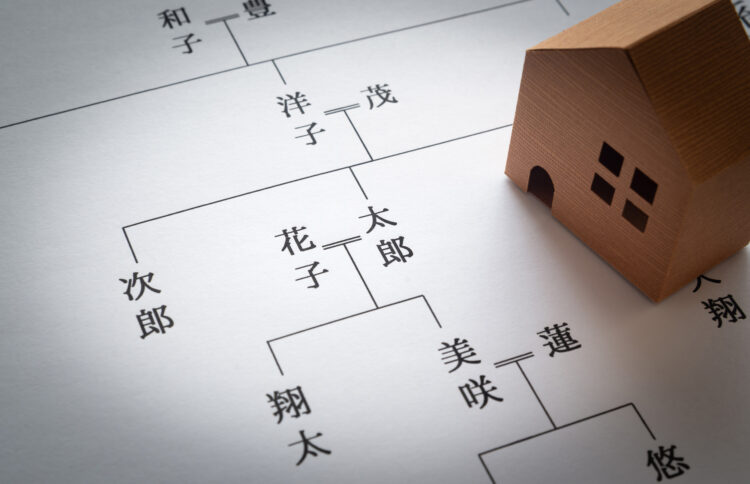飲食店にて、次のような会話があったとしましょう。
「ごめん、財布をデスクに置いて来ちゃったみたいでさ、ランチ代貸してくれない?」
「わかった。じゃあ1000円貸すね。どーぞ」
「(1000円札を受け取って)ありがとう」
このようなお金の貸し借り、よくありますよね。
このような貸し借りは、法律的には「金銭消費貸借契約」(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)と言います。
よく見られるランチのシーンですが、この2人の間では金銭消費貸借契約が成立しています。
このような知人間の少額の貸し借りではわざわざ契約書を作らないでしょう。
しかし、特に金額が大きい場合には、契約書を作ってお金を貸した証拠を残しておいた方が、後々トラブルになったときに安心です。
例えば、契約書を作っておけば、借主としては、約束していなかった利息を支払わされる事態などを避けやすくなります。貸主としても、「そもそもお金を借りてなどいない」と言われてしまう事態などに備えることができます。
この記事では、消費貸借契約の意味、金銭消費貸借契約の内容、契約書の作成方法などについて、弁護士が詳しく解説します。
ここを押さえればOK!
友人間の少額な貸し借りでは口約束でも成立しますが、高額な貸し借りでは、後々のトラブルを防ぐために契約書を作成することが重要です。
契約書には、借主と貸主の署名・押印、貸した金額、日付、返済方法、利息、遅延損害金などを明確に記載します。
契約書には、貸借する金額に応じた収入印紙の貼付が必要で、怠ると過怠税が課されます。また、公正証書にすることで、返済が滞った際に裁判手続きを経ずに強制執行が可能になる場合もありますが、借主にとってはリスクも伴います。
お金を借りる際、特に注意すべきは「期限の利益喪失条項」です。これは、分割払いの返済を一度でも怠るなど、特定の条件に該当した場合に、借主が期限の利益(返済期日まで支払いを待ってもらえる権利)を失い、一括返済を求められることを定めた条項です。
もし借金の返済が困難になった場合は、債務整理を検討することで、返済負担を軽減できる可能性があります。借金問題でお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!

費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意
国内65拠点以上(※1)
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応
消費貸借契約とは?
消費貸借契約とは、相手に同種・同質・同量のものを返すことを約束して、相手からお金や物を借りる契約です。
借りた物は使うとなくなってしまう(=消費)ことが前提で、借りた物そのものは返すことができない場合の契約です。
民法587条において、消費貸借契約は次のように規定されています。
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
引用:民法587条
先ほどの例において、借りた1000円はランチ代に消えていますので、借主が返すお金は、借りた1000円札そのものではなく、デスクに置き忘れられた財布に入った1000円です。
このように消費貸借では、借りたものをそのまま返すのではなく、同等の物を返すのが特徴です。
金銭消費貸借契約とは金銭の貸し借りに関する契約のこと
消費貸借のうち金銭消費貸借契約とは、お金を対象とした消費貸借契約、つまり「金銭」の貸し借り(借金)に関する契約のことです。
要は、金銭消費貸借契約とは、将来お金を返すことを約束して、お金を借りる契約のことです。
金銭消費貸借契約は、契約書がなくてもお金を受け取れば口約束のみで成立します。もっとも、売買契約のように物の受け渡しがなくても成立するわけではなく、お金が渡されて初めて契約が成立します。
また、金銭消費貸借契約では、利息を上乗せして返すのが一般的ですが、個人間の貸し借りでは、契約の時に定めていなければ利息は発生しません(民法589条1項)。
利息を返すことは定めたけれど、具体的な利率を定めなかった場合には、法定利率が適用されて一定の利息を請求することができます(民法404条 個人間の契約では年3%)。
※2020年4月1日以降の契約の場合。今後も見直される可能性があります。金銭消費貸借契約はどのような時に交わすのか?
お金を借りる事情はさまざまですが、代表的な場面をあげてみましょう。
- 銀行から融資を受ける
- 消費者金融から借入れをする
- 奨学金を借りる
- 住宅ローン、自動車ローンで融資を受ける
- 家族や親戚、友人・知人からお金を借りる
まとまったお金を借りるとなると、金融機関から借りることが多いのではないでしょうか。
金融機関からお金を借りる際には、通常、金銭消費貸借契約書を作成しますし、利息も発生します。
金銭消費貸借契約書とは
金銭消費貸借契約に際して作成する一般的な書面は、「契約書」と「借用書」の2種類です。
契約書や借用書に関する法律上の定義はありませんが、次のような商慣習が定着しています。
- 契約書:借主と貸主が署名捺印した契約書を2通つくる。各当事者が手元で保管する。
- 借用書:借主が貸主に宛てて1通作成し、貸主が保管する。
どちらも後々トラブルが生じたときに証拠として使えますが、同じ内容の書面が両者の手元に残る「金銭消費貸借契約書」を作成することが望ましいといえるでしょう。
借主が自分の手元で契約書を保管することで、貸主が借用書を偽造して借入金を増やしたが、自分の手元に本来の借入金を示す証拠がないという事態を防ぐことができます。
より安全な方法を選ぶのであれば、公証役場に行き、借用書や契約書を公正証書にしておくのが良いでしょう。
公正証書とは、法律に則って契約の条件などを記した公文書です。もっとも、一定の要件を満たした公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作成すると、返済が滞った場合に、裁判手続を経ずに強制執行される可能性があります。したがって、公正証書を作成することは、借主からみるとリスクもあります。
公正証書の種類や作成方法について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
参考:公証制度について|法務省
金銭消費貸借契約書の作成方法
金銭消費貸借契約書の作成方法や中身について解説します。
(1)金銭消費貸借契約書に記載すること
金融機関からお金を借りる場合には定型の契約書があるので、それを利用するのが一般的です。
一方、個人間でお金の貸し借りをする場合には、自分たちで契約書を準備する必要があります。
金銭消費貸借契約書の記載事項について法律上の定めはありませんが、一般的には次の事項を記載します。
<最低限記載しておくべきこと>
- 借主の氏名、住所、押印
- 貸主の氏名、住所、押印
- 貸した金額
- お金を貸した日付
- 借主がお金を返すことの合意
<できるだけ記載しておきたいこと>
- 契約書を作成した日付
- 返済方法(一括なのか分割なのか、分割だとすれば月々いくら返済するのか)
- 返済期日
- 利息の有無、利率
- 遅延損害金率
- 期限の利益の喪失条項
- 連帯保証人の氏名、住所、押印
- 合意管轄(争いとなったときにどこの裁判所に訴えを提起するか)
契約の内容は、貸主と借主が相談して決めることになります。お金を借りるときには、借主のほうが立場は弱いので貸主の意見が通りやすいといえますが、譲れない点は借主としてもきちんと主張するのが良いでしょう。
契約書を作成する際、インターネットで「消費貸借 契約書」と検索するといくつもひな形が見つかります。もっとも、利息や条件を付ける場合には後々にトラブルにならないか不安に感じることもあるでしょう。その場合には、弁護士に契約書の作成を依頼することをおすすめします。
(2)金銭消費貸借契約書に印紙代を貼る
金銭消費貸借契約書や借用書には貸借する金額に応じて、収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙代は、次の表のとおりです。
| 貸借した金額(記載金額) | 収入印紙代 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 1万円 |
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
収入印紙を貼り忘れても、契約が無効になることはありません。
ただし、支払義務のある税金を納めていないとみなされ、過怠税(かたいぜい)を支払わなければなりません。
過怠税とは、印紙税を納付しなかったことによる罰金のような税金で、印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額を支払います。
また、貼った印紙には消印をする必要があります。
参照:印紙の消印の方法|国税庁
(3)返済が遅れたら一括請求?期限の利益の喪失条項について
契約時には分割払に応じたとしても、貸主が後々借主の返済能力に疑問を感じて、一括で返済を求めたくなることがあるかもしれません。
そのような場合に備えて、分割払とするときには、「期限の利益の喪失条項」を入れておくのが一般的です。
「期限の利益」とは、返済期日まで支払を待ってもらえる、という借主にとっての利益のことです。
「期限の利益の喪失条項」とは、どのような場合に期限の利益がなくなり、支払いを待ってもらえずにすぐに支払わなければならないのかを記載した条項です。
契約書に別途定めなくても、民法で、期限の利益を失う3つの場合が規定されています(民法137条)。
- 借主が破産手続開始の決定を受けたとき
- 借主が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
- 借主が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
参照:民法|e-Gov法令検索
民法で規定されているのは、この3つのケースだけです。
しかし、貸主がお金を払ってもらえないのではないかと考えるケースは、他にもあります。そのため、実務では、「期限の利益喪失条項」を設けて、民法よりも広く期限の利益を喪失するケースが定められています。
期限の利益や、期限の利益喪失条項について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
期限の利益喪失条項があるかどうかの確かめ方
契約書に、次のような文章がないかを確認してみましょう。
乙(借主)が前項各号(解除事由)のいずれかに該当した場合、乙(借主)は、当然に期限の利益を失い、甲(貸主)に対して本契約に基づいて負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
そのような文章があれば、そこに書かれていることが期限の利益を喪失するケースです。
では、期限の利益喪失条項として定められていることの多い条項を2つご紹介します。
- 1:分割払の返済が遅れた場合
法律上は、返済が遅れても直ちに期限の利益を失うとは定められていません。
しかし、貸主が最初に慌てるのは「約束どおりに返済されない場合」でしょう。1度遅れた人がその後きちんと返してくれる保証はありません。
そこで、一般的な契約では「一回でも支払を怠ったとき」に期限の利益を喪失するとされています。
もっとも、何らかの手違いで数日遅れただけであれば一括請求しなくてもいいと考える債権者もいるはずです。事情次第で、そのまま分割払を完済まで続けられることもあります。
- 2:経済状況の悪化や虚偽が発覚した場合
貸主は、お金を貸したときの借主の経済状況を参考にして、お金を貸しています。
そのため、収入が大幅に減ったケースや申告した状況が虚偽であるケースでは、期限の利益を喪失するとされていることがあります。
【まとめ】金銭消費貸借契約とは、お金の貸し借りの契約
金銭消費貸借契約を結ぶ際、後々トラブルが生じるリスクを下げるためには、契約書をしっかりと作成することが必要です。不安な場合には、一般民事を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
また、金銭消費貸借契約で借りたお金を返すことが難しくなった場合には、「債務整理」をすることで、返済の負担を減らしたり無くしたりできる可能性があります。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております (2022年6月時点)。
債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。