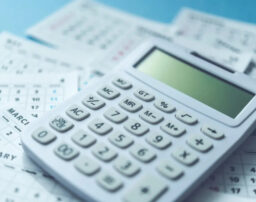「借金の連帯保証人になってしまったけど、やっぱりなかったことにしたい!」
このような状況に陥った場合、一体どうすれば良いのでしょうか。
基本的に、いったん連帯保証人になってしまった場合、一方的に契約をなかったことにするのは難しいでしょう。
ただし、一定の事情がある場合には、連帯保証契約の解除や、取消しを主張できる可能性があります。
この記事を読んでわかること
- 連帯保証人の義務
- 連帯保証人と保証人の違い
- 連帯保証契約の解除・取消しなどが認められるケース
連帯保証人とは?
そもそも、連帯保証人とは何でしょうか。
まずは連帯保証人の概要と、単なる保証人との違いをご説明します。
(1)連帯保証人の基礎知識
連帯保証人とは、簡単に言うと主債務者(借金の場合であれば、お金を借りた本人のこと)と同様の返済義務を負う保証人のことです。
連帯保証人も、単なる保証人も、主債務者が債務を返済できない場合、代わりに返済する義務を負いますが、連帯保証人は単なる保証人よりも重い責任を負うこととなります。
引き受けるべきかどうかは慎重に考慮するようにしましょう。
(2)連帯保証人と保証人の違い
連帯保証人と保証人は、どちらも主債務者が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負うという点では共通しています。
しかし、連帯保証人は、次の点で保証人よりも重い責任を負っています。
【1.「催告の抗弁」が認められない】
「催告の抗弁」とは、債権者がいきなり主債務者ではなく(連帯)保証人に対して請求してきた場合に、「まずは主債務者に請求してください」という主張のことです。
単なる保証人には催告の抗弁が認められていますが、連帯保証人がこのような主張をすることはできません。
【2.「検索の抗弁」が認められない】
「検索の抗弁」とは、主債務者に返済する資力があるにもかかわらず、債権者から代わりに返済するよう請求された場合に、「主債務者には資力があるので、まずは主債務者の財産に強制執行をしてください」という主張のことです。
単なる保証人には検索の抗弁が認められていますが、連帯保証人がこのような主張をすることはできません。
【3.「全額」返済する義務を負う】
(連帯)保証人が複数いる場合、単なる保証人であればその頭数で割った金額のみを返済すれば良い(「分別の利益」といいます)のに対し、連帯保証人であれば、他に(連帯)保証人がいたとしても、請求されたら債権者に全額を返済しなければなりません。
連帯保証人をやめられるケース
では、連帯保証契約の解除・無効など、契約を無かったことにできる(解消できる)ケースはあるのでしょうか。
家族や友人など近しい間柄ゆえに、連帯保証人を引き受けてしまうケースは少なくありません。
主債務者が滞りなく返済できれば問題ないのですが、主債務者が返済を怠ったことにより、債権者から突然返済を迫られてトラブルになることがあります。
特別の事情がある場合には、一度締結してしまった連帯保証契約の取消しなどを主張できる可能性もありますので、次でご紹介します。
(1)連帯保証契約の解除が認められるケースとは?
そもそも「解除」とは、契約当事者の一方の意思表示によって、契約の効力をさかのぼって消滅させることをいいます。
解除は、あらかじめ契約当事者間における合意がある場合か、法律で解除できることが定められている場合に限られます。
そのため、連帯保証契約を締結した場合に、連帯保証人による解除が認められるケースは考え難いでしょう(当該連帯保証契約において解除権が発生する条件が定められており、その条件を満たした場合を除く)。
契約「解除」など、「解除」は比較的よく聞く法律用語ですが、連帯保証人による連帯保証契約の「解除」が認められるケースは、なかなか想像し難いのが通常です。
(1-1)債権者の同意があった場合
一方的な意思表示である「解除」はなかなか難しいですが、当事者間で合意すれば、契約をなかったことにできる場合があります。
当事者間の合意により、契約の効力をさかのぼって消滅させることを「合意解除」、当事者間の合意により、将来に向かって契約の効力を消滅させることを「合意解約」と呼ぶことが一般的です。
しかし、いずれにせよ、契約関係を解消することに債権者が同意してくれる可能性は低いと考えられます。
例えば、借金のほとんどがすでに返済されていたり、(一定以上の資力がある)代わりの連帯保証人を立てられたりしたなどの場合でなければ、債権者の同意を得ることは難しいでしょう。
(2)連帯保証人の無効・取消しを主張できるケース
一般的に、法律上の「無効」と「取消し」の意味は次のとおりです。
- 無効:はじめから契約の効力が発生しないこと
- 取消し:何らかの問題があったことを理由に、契約の効力を初めからなかったことにする意思表示のこと
(2-1)無断で連帯保証人にされた場合
もし、無断で連帯保証人にさせられた場合、その連帯保証契約は基本的に無効です。
例えば、主債務者が本人の代理人であると称して、勝手に連帯保証契約を締結した場合などが考えられます。
そのような場合、当該連帯保証契約は無効であり、法律上、その効力は本人に対して生じません。
ただし、債権者に、自分が連帯保証人となっていることを事後的に認めるなど、当該連帯保証契約を「追認」したといえる場合には、もはや自分が連帯保証人でないと主張できなくなります(民法113条1項)。
無断で連帯保証人にされた場合の対処法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2-2)騙されて連帯保証人になった場合
騙されて連帯保証人になってしまった場合、契約を取り消すことができる可能性があります。
例えば、本当は借金の連帯保証契約であるにもかかわらず、賃貸借契約の連帯保証人になってほしい、などと騙されて、契約書にサインしてしまった場合などです。
ただし、騙されたことを示す証拠が必要になると考えられます。
また、たいていの場合、騙すのは主債務者であることが多いですが、債権者がその事実を把握できなかったような場合には、取消しが認められない可能性もあります。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
引用:民法96条2項
(2-3)強迫されて連帯保証人になった場合
強迫されて、仕方なく連帯保証人の欄にサインしてしまった場合などには、連帯保証契約の取消しを主張できる可能性があります。
ただし、例えばサインを迫られた際の会話の録音や、メールやメッセージの内容など、強迫を受けたという証拠が必要になるでしょう。
(2-4)勘違いで連帯保証人になった場合
契約内容の重要な部分について勘違い(錯誤)していた場合、契約の取消しを主張できる可能性があります。
例えば、実際に連帯保証した借金の額は1000万円であるにもかかわらず、100万円であると勘違いした場合などです。
ただし、連帯保証人に重大な過失(不注意の度合いが大きいこと)があった場合には、取消しが認められない可能性が高くなります。
連帯保証契約を解消したい場合の注意点
連帯保証契約が、無効と考えられる場合や、取消し事由があると考えられる場合など、連帯保証契約を解消したいのであれば、注意すべき点があります。
(1)連帯保証人として返済請求に応じない
自分が連帯保証人であることを認めた場合や、返済請求に応じたり、応じるような姿勢を見せたりした場合、たとえ先ほどご説明したような取消事由(詐欺や強迫、錯誤)があったとしても、当該連帯保証契約を「追認」したと評価される可能性があります。
取り消すことができる行為を追認した場合、もはや当該連帯保証契約を取り消すことができなくなってしまいます(民法122条)。
そのため、安易に連帯保証契約について認めたり、返済請求に応じる姿勢を見せたりしないように注意しましょう。
(2)連帯保証契約の合意解除・合意解約は債権者の判断に委ねられる
当事者間の合意によって、最初から契約の効力をなかったことにする合意解除にせよ、将来に向かってその効力を消滅させる合意解約にせよ、最終的には債権者がそれを受け容れるかにかかっていると考えられます。
そのため、債権者が合意解除・合意解約に応じてくれるようにするためには、別の連帯保証人を立てるなどの対策が必要になると考えられます。
なお、契約の無効、取消しは、法律上の要件を満たせば、債権者の同意がなくても認められます。
(3)連帯保証人の合意解約と無効・取消しは効力が異なる
連帯保証契約の合意解約は、将来に向かって契約の効力を消滅させます。
つまり、合意解約前に発生した債務については、返済する義務があります。
一方、連帯保証契約の無効や取消しが認められた場合、最初から契約の効力が生じなかったことになるため、返済義務は生じません(合意解除の場合も同様)。
(4)連帯保証契約を解消するための交渉は困難
連帯保証契約の無効や取消しなどを主張し、個人で債権者と交渉することは、大変難しいと考えられます。
債権者との交渉は、契約に関する法的知識を持つ弁護士に依頼することをおすすめします。
【番外編】連帯保証人だった親が亡くなった場合は、相続放棄という手段も
連帯保証人になるのは、自分自身が連帯保証契約を締結した場合に限られません。
借金の連帯保証人になっていた人が亡くなった場合、その相続人が連帯保証人の立場を相続するのが原則です。
しかし、相続放棄をすれば、連帯保証人の立場を相続することはありません。
(※相続放棄をすると、借金だけでなく、すべての財産を相続できません。)
また、相続放棄は、単に「相続しない」という意思表示をするだけでは足りず、家庭裁判所での手続が必要になります。
相続放棄についてはこちらの記事もご覧ください。
詐欺や強迫、錯誤によって連帯保証人となった人が亡くなった場合、その相続人は、当該連帯保証契約を取り消すことができます(民法120条2項)。
したがって、そのような事情があれば、相続放棄をしなくても、連帯保証契約を解消できる可能性があります(ただし、それらの主張が認められるためには、取消事由があることを示す証拠が必要となる可能性が高いでしょう)。
【まとめ】特別の事情がある場合は連帯保証契約の取消し等を主張できることがある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 保証人には認められる、催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益が、連帯保証人には認められない
- 連帯保証契約を解消するには債権者の同意を得るか、取消しの要件を満たすことなどが必要
- (取消事由があっても)自分が連帯保証人であることを認めたり、返済したりすると、連帯保証契約を追認したと評価される可能性がある
連帯保証契約を解消したいとお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。