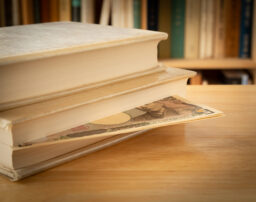自己破産を依頼された弁護士は、依頼者の方にいくつか禁止行為をお伝えしています。
- 受任後の借入れ、返済(携帯電話を使った後払いを含む)
- 自動車や住宅など財産の処分(適正価格での売却として弁護士の了承を得た場合を除く)
- 浪費、ギャンブルなど…
自己破産を依頼すると、多かれ少なかれ生活に変化が生じるため、不便を感じるでしょう。
しかし、これらは原則全ての支払義務を免除してもらう、いわば代償のようなものです。
これらの行為をしてしまうと、せっかく自己破産の手続きをしても、支払義務を一切免除してもらえないリスクや、「詐欺破産罪」などの犯罪が成立してしまうリスクがあるのです。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 自己破産の手続きをしても支払義務を一切免除してもらえない可能性がある「免責不許可事由」
- 免責不許可事由の中でも、裁判所での自己破産の手続きにおける義務違反
- 「詐欺破産罪」

自己破産が認められない「免責不許可事由」とは?
個人の
自己破産の手続きにおける最終的なゴールは、
裁判所から借金などの負債の支払義務を免除してもらうことです(ただし、税金など一部の支払義務はそのまま残ります)。これを「免責(許可)」と呼びます。
そして、免責不許可事由とは、免責が出ない可能性のある事情です。
自己破産の申立て
破産手続開始決定
免責許可
※ただし、「免責不許可事由」があると、免責許可が出ない可能性あり
例えば、自己破産の手続きを進めている債務者が財産隠しをすれば、その分債権者が配当で受け取ることのできる金額は減ってしまい、債権者の利益が害されることとなります。
このように、破産者(自己破産の申立てをして、裁判所から「破産手続開始決定」を出してもらった人)が一定の悪質な行為をした場合などが「免責不許可事由」として定められています。
裁判所は、免責不許可事由のない限り、免責許可の決定をしなければなりません(破産法252条1項)。
つまり、「基本的に自己破産を申立てれば借金の返済義務は免除される。一方、債権者に酷な行為をしたケースなど例外的に借金が免除されない場合があります」ということです。
破産法で定められている11の免責不許可事由
破産法252条1項では、次の11個の免責不許可事由が定められています。
- 不当な破産財団価値減少行為(1号)
…債権者の利益を害する目的で、破産財団を不当に減少させること - 不当な債務負担行為(2号)
…もう支払えない状況だと分かっているのに、破産手続開始を遅らせるために、著しく不利益な条件(高利など)で債務を負担することなど - 不当な偏頗行為(3号)
…特定の債権者にだけ利益を与える目的か、他の債権者の利益を損なう目的で、一部の債権者にだけ返済することなど - 浪費または賭博その他の射幸行為(4号)
…浪費や賭博などによって著しく財産を減らしたり、過大な負債を抱えること - 詐術による信用取引(5号)
…「自己破産の申立ての1年前の日」から「破産手続開始決定」までの間に、既に支払えない状況であることを隠し、相手をだまして借金をすることなど - 業務帳簿隠滅等の行為(6号)
- 虚偽の債権者名簿提出行為(7号)
- 裁判所への説明拒絶・虚偽説明(8号)
- 管財業務妨害行為(9号)
…財産調査や配当、負債の膨らんだ経緯の調査などを行う「破産管財人」が選任されたケースで、破産管財人の業務を妨害することなど - 7年以内の免責取得等(10号)
- 破産法上の義務違反行為(11号)
それぞれの免責不許可事由について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
この記事では、11号について詳しく解説します。
自己破産で絶対にやってはいけない3つの義務違反
破産法252条1項11号には、次のように規定されています。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
引用:破産法252条1項11号
第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
居住等の制限義務(破産者は、居住地を離れる際には裁判所の許可を得る必要があります。破産法37条1項)など、破産法に規定された義務に違反すると免責不許可となる可能性があります(「その他この法律に定める義務」への違反)。
特に気を付けなければならないのが、破産法252条1項11号で列挙されている、次の3つです。
- 説明義務(破産法40条1項1号)違反
- 重要財産開示義務(破産法41条)違反
- 免責手続における協力義務(破産法250条2項)違反
破産法による免責というメリットを得るためには、破産法上の制約も遵守しなければなりません。自己破産の手続きにおいて不誠実な対応をするのであれば、免責を許可する必要がないと考えられているのです。
(1)破産者の説明義務(破産法40条1項1号)の違反
まず、破産法40条1項1号をみてみましょう。
次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
引用:破産法40条1項1号
一 破産者
破産者は、 破産管財人などから、破産理由や財産状況などについて説明を求められた場合には、回答する義務がありますし、必要に応じて書面を提出しなければなりません。
合理的な理由なく説明を拒絶した場合には、免責不許可事由になるとともに、説明及び検査の拒絶等の罪(破産法268条、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいは懲役と罰金の両方)に問われるおそれがありますので、注意してください。
(2)重要財産開示義務(破産法41条)の違反
次に、破産法41条をみてみましょう。
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
引用:破産法41条
破産法41条は、破産管財人などからの求めがなくても、 破産者が自ら積極的に財産の内容を書面で開示しなければならないとし、説明義務を強化した規定とされています。
開示義務の対象となるものは、 破産手続開始決定の時点で、破産者が所有する財産です。破産手続後においても自身で保有できる自由財産を含めて、開示する必要があります。海外にあるもの、第三者が占有しているものも例外ではありません。
通常、破産申立てにあたって資産目録・財産目録を提出しますので、自己破産を依頼した弁護士を通じて、嘘偽りなく報告しましょう。
開示を拒絶した場合には、 免責不許可事由になるとともに、重要財産開示拒絶の罪(破産法269条、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいは懲役と罰金の両方)に問われるおそれがありますので、注意してください。
(3)破産者の免責調査協力義務(破産法250条2項)の違反
最後に、破産法250条2項をみてみましょう。
破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。
引用:破産法250条2項
例えば、次のようなことをすると、調査協力義務違反となります。
- 正当な理由なく審尋期日に出頭しない、あるいは、陳述を拒絶する
- 審尋期日において、虚偽の説明をする
- 裁判所からの質問に対して回答を拒絶する、あるいは、 虚偽の回答をする
- 裁判所や破産管財人から求められた資料を提出しない
- 正当な理由なく管財人面接に出席しない、あるいは、 管財人面接で虚偽の説明をする
免責調査に協力しない場合には、 免責不許可事由になるだけではなく、説明及び検査の拒絶等の罪(破産法268条)や破産管財人等に対する職務妨害の罪(破産法272条、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、あるいは懲役と罰金の両方)に問われるおそれがありますので、注意してください。

自己破産で絶対にやってはいけない詐欺破産罪とは?

最後に、破産犯罪の中で特に重要である「詐欺破産罪」(破産法265条)について解説しましょう。
(1)詐欺破産罪とは?
詐欺破産罪は、債権者を害する目的で次の行為をしたときに成立します(破産法265条1項各号)。
- 破産者が 自分の財産を隠し、またはあえて破壊した
- 破産者が自分の財産を第三者に譲渡し、または第三者から債務を負担したように見せかけた
- 破産者が自分の財産の価値を損なわせた
- 破産者が債権者に不利益になるように財産を譲渡し、または債務を負担した
「債権者を害する」とは、上のような財産隠しなどの行為によって、債権者への配当のための手続きである破産手続の適正さが損なわれてしまい、全ての債権者が損をするということです。
(2)詐欺破産罪に処されるとどうなるのか?
破産法による免責のメリットを受けられないばかりか、刑務所に入ることとなる可能性もあります。
具体的に、詐欺破産罪の刑罰は、次のとおりです(破産法265条1項本文)。
- 1ヶ月以上10年以下の懲役
- 1000万円以下の罰金
懲役と罰金が両方とも下される可能性もあります。
さらに、窃盗罪や横領罪、器物損壊罪など刑法上の他の犯罪も成立する場合には、さらに重い処罰が科せられるおそれもあります。
自己破産は生活に必要な範囲を超える財産をすべて手放す代わりに、原則全ての支払義務を免除してもらう手続きです。生活に必要な財産かどうかは法律や裁判所の判断によって決まります。そのため、財産を隠し持とうとすると逮捕・起訴される可能性があります。
(3)たとえ自己破産といえども、全ての財産が処分されてしまうわけではない
自己破産では財産が身ぐるみ処分されてしまうのではないか?と不安に思われている方は少なくありません。
しかし、自己破産といえども、一定の範囲の財産は手元に残しておけるようになっています。このような、手元に残すことのできる財産を「自由財産」といいます。
例えば、「破産手続開始決定の後」に手に入れた財産であれば、原則全て自由財産扱いとなります。
そのような意味では、早めに自己破産の申立てをして、早く破産手続開始決定を出してもらった方が、手元に残せる財産が増える可能性があります。
自由財産にどのようなものがあるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
義務違反行為では裁量免責も難しい?
免責不許可事由があっても、裁判所の判断で免責が許可される「裁量免責」という制度があります(破産法252条2項)。
そのため、免責不許可事由があっても、実際には裁量免責によって免責許可が下りるケースが少なくありません。
もっとも、免責不許可事由があっても裁量免責となるケースというのは、例えば、「浪費が原因で膨らんだ借金ではあるが、破産者はきちんと反省して浪費をやめ、家計を立て直すために真摯に手続きを進めているケース」などです。
一方、ここまで説明してきた 破産法252条1項11号の免責不許可事由というのは、「裁判所での自己破産の手続きが始まって以降も、義務違反という不誠実な態度を取っている」ことについてのものです。
裁量免責の可否の判断にあたっては、破産者の誠実性の有無・程度、免責不許可事由の種類・内容・程度が考慮されます。そのため、自己破産の申立てをして以降も破産法に違反する不誠実な態度をとったということで、免責不許可となる可能性が高いと言わざるを得ません。
免責不許可となった場合の対処法
免責不許可になってしまった場合には、次の対処法を採ります。
いずれの方法を採るにしても、専門家である弁護士に指示を仰ぎましょう。
(1)即時抗告をおこなう
免責不許可になった場合、その決定に対して異議申立てを行うことができます(即時抗告、破産法252条5項)。
即時抗告をするには、免責不許可決定が送達された日の翌日から1週間以内に行わなければいけませんので、注意が必要です。
ただし、明らかな免責不許可事由がある場合は、即時抗告しても決定が覆らない可能性が高いので、改めて民事再生の手続きをすることが考えられます。
(2)民事再生の手続きをする
免責が許可されなかった場合には、
免責不許可事由に当たる規定のない民事再生を検討します。
ただし、民事再生は大幅に減額される可能性があるとはいえ、基本的には数年間支払い続ける必要のある手続きなので、支払っていけるだけの収入がなければ厳しいです。
【まとめ】破産法に違反してしまうと、支払義務を一切免除してもらえないリスクがある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自己破産の手続きのゴールは、裁判所から「免責許可」を出してもらい、原則全ての支払義務から解放されること
⇔「免責不許可事由」があると、免責許可が出ず、支払義務が全てそのまま残るおそれがある - 免責不許可事由の中でも特に気を付けたいのが、破産法上の3つの義務違反(破産法252条1項9号)
⇒これらの義務違反については、「裁判所で自己破産の手続きが始まって以降も、不誠実な態度を取っている」ということで、免責不許可となる可能性が高い - 一定の財産隠しをすると、「詐欺破産罪」という犯罪が成立してしまうこともある
原則全ての支払義務から解放される可能性のある自己破産ですが、手続きにおける義務に違反すると、免責不許可となり、支払義務を一切免除してもらえないリスクがあります。
「自己破産となっても、今後の生活のために、何とかして財産は手元に残したい」などと思われるのは、法律違反かどうかはさておき、無理のないことではあります。
しかし、 「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断した結果、思わぬ免責不許可事由に当てはまってしまい、免責不許可となってしまうリスクもあるのです。
たとえ自己破産といえども、全ての財産を手放さなければならないわけではありません。 適法な範囲で財産を残しつつ、免責許可を獲得する可能性を高めるには、自己破産を取り扱っている弁護士に相談することがおすすめです。
アディーレ法律事務所では、万が一自己破産の事件で免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年10月時点)。
※ただし、免責不許可が、次のことに起因する場合などは、返金対象外です。
- アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
- 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合
自己破産についてお悩みの方は、自己破産を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。