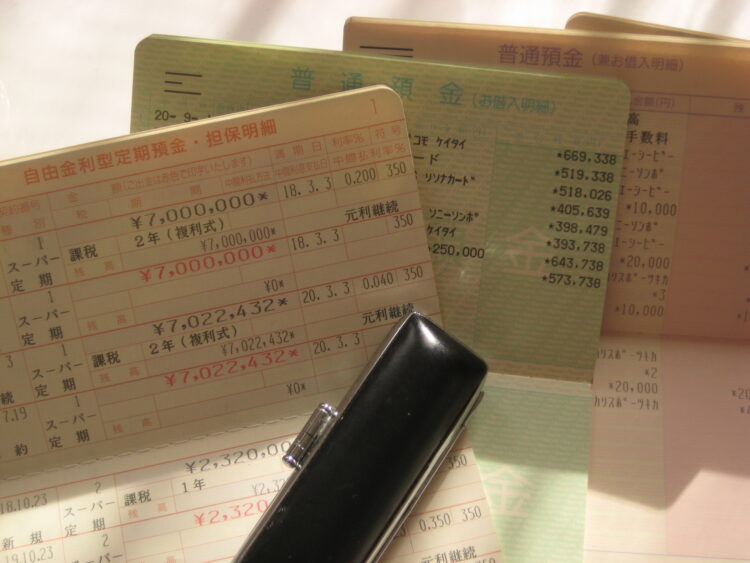「入院費用が払えない」という状況に直面したとき、誰もが不安を感じることでしょう。
しかし、適切な対処法や公的支援制度を知ることで、その不安を軽減することができるかもしれません。
本記事では、入院費用が払えない場合の具体的な対処法や公的支援制度について解説します。分割払いの方法から高額療養費制度、さらには生活保護まで、幅広い選択肢を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 入院費用がどれくらいかかるのか
- 入院費用の自己負担額を抑える方法
- 入院費用を払えないとどうなるのか
- 入院費用が払えないときの対処法
ここを押さえればOK!
入院費用には、個室の差額ベッド代など、保険適用外の費用も含まれます。これらの費用は全額自己負担となるため、事前に病院に確認し、どの費用が保険適用外でいくらくらいかかるのかを把握しておくことが重要です。
入院や通院の費用を抑えるためには、公的制度を利用することが有効です。主な公的制度には、高額療養費制度、高額医療費貸付制度、自立支援医療(精神通院医療)、傷病手当金、無料低額診療事業、医療費控除、生活保護などがあります。これらの制度を利用することで、自己負担を軽減することができる可能性があります。
もし入院費用が払えない場合、病院から督促を受けたり、保証人に請求が行われたり、弁護士から請求されることがあります。公的制度を利用してもどうしても入院費用が払えない場合は、病院に分割払いができないか相談しましょう。他の借金がある場合には、弁護士に相談して債務整理を検討することが有効です。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
入院費用はどれくらいかかる?
入院費用は病院の種類や治療内容によって異なります。
厚生労働省の調査によれば、2024年度の病院への入院一日当たりの医療費平均は、4万2697円です。そのうちの3割が自己負担となるとすると、1万2809円になります。
大学病院への入院だと一日当たり医療費平均は8万円を超え、個人の病院だと2万円強で、病院によって大きな差があります。1日8万円の医療費だと、保険で3割の自己負担に減ったとしても、1日2万4000円はかかることになります。何日も入院すると、かなり大きな出費になることがわかります。
病院に対して、入院費用はどれくらいになるのか事前に確認し、計画的に支払いの準備をすることが重要です。
保険適用外の費用もかかる
入院費用には、保険が適用される治療等の医療費だけではなく、保険適用外の費用も含まれます。例えば、個室の差額ベッド代、食事代、おむつ代、病衣等のレンタル、自由診療の診療代や薬代などが挙げられます。
これらの費用は公的医療保険が使えず、全額自己負担となるため、予想以上に高額になることがあります。
オムツなど自分で準備できるようであれば、自分で準備すると費用の軽減に役立つでしょう。
事前に病院に確認し、どの費用が保険適用外でいくらくらいかかるのかを把握しておくことが重要です。
入院費用の自己負担を抑える公的制度
入院や通院の費用を抑えるためには、公的制度を利用することが有効です。主な公的制度について紹介します。
また、公的制度の他にも、医療保険などに加入している方は、入院により保険金が受け取れるのかどうか、どれくらい受け取れるのかなどについて、確認するようにしましょう。
(1)高額療養費制度
高額療養費制度は、ひと月に一定額を超える医療費を支払った場合に、その超過分が支給される制度です。
所得や年齢に応じて自己負担限度額が設定されており、支給には申請手続きが必要です。
申請手続きは、自分が加入している公的医療保険に対して申請書を提出します。
世帯のうち一人だけでは高額療養費制度が使えなくても、複数人合算すれば制度が利用できるケースもあります。
自身の所得や年齢に応じた自己負担限度額はいくらになるのかは、厚生労働省のホームページや加入している公的医療保険の窓口でご確認ください。
参考:高額療養費制度を利用される皆様へ(平成30年8月診療分から)|厚生労働省
高額な医療費が予想されるときは、マイナ保険証を利用するか、限度額適用認定証を提出すると、支払が初めから高額療養費支給後の限度額とすることができます。
(2)高額医療費貸付制度
高額医療費貸付制度は、高額療養費制度の対象となる医療費が必要となる場合に、高額医療費が支給されるまで、一時的に無利子でお金を借りられる制度です。
借りられるお金は、高額療養費支給見込み額の8割相当額です。
高額療養費の支払いが困難な場合には、高額療養費の申請をするとともに、この貸し付けについても申請を行うとよいでしょう。
また、高額な医療費が予想されるときは、マイナ保険証を利用するか、限度額適用認定証を提出すると、支払が初めから高額療養費支給後の限度額とすることができます。
(3)自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患を持つ方が通院治療を受ける際に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
公的医療保険で3割負担のところ、この制度の利用により自己負担が1割になります。
また1割負担となっても、負担が過大にならないよう、世帯の所得に応じた上限額があります。
対象となる疾患は精神障害で通院治療の必要性がある場合に限られ、また診療内容に制限があります(入院は対象外など)ので、詳しくは厚生労働省のホームページや加入している公的医療保険の窓口でご確認ください。
(4)傷病手当金
傷病手当金は、在職中に病気やけがで4日以上(連続する3日間の休みを含む)働けなくなった場合に、給与の一部を補填する制度です。
健康保険から給付されますので、健康保険に加入していることが条件です。
1日当たりの傷病手当金の金額は、次の式で計算します。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の「標準報酬月額」を平均した額÷30日×3分の2
つまり、おおよそ給与(総支給額)の3分の2相当額の支給を受けられることになります。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
(5)無料低額診療事業
無料定額診療事業は、経済的に困窮している方が、世帯の収入等に応じて無料または低額で診療を受けられる制度です。対象となる医療機関で利用できます。
対象となる医療機関については、自治体のホームページなどで確認することができます。
(6)医療費控除
医療費控除は、年間の医療費が一定額(10万円※)を超えた場合に、所得額の一部を控除できる制度です。所得額控除により、所得税や住民税の負担を軽減することができるでしょう。
※所得合計額が200万円までの方はその5%
医療費控除を受けるためには確定申告が必要ですので、しっかりと領収証を保管して申告するようにしましょう。
(7)生活保護
生活保護は、経済的に困窮している国民が最低限度の生活を保障される制度です。
生活保護で支給される費用にはいくつか種類があります。そのうちの一つである医療扶助が受けられる治療であれば、その医療費は直接診療を受けた病院に支給されますので、本人の窓口負担はありません。
ただし、医療扶助の指定を受けた病院で診療を受ける必要があるなどのルールがありますので、注意しましょう。
入院費用が払えないとどうなる?
入院費用が払えない場合、以下のようなリスクがあります。
(1)病院から督促を受ける
未払いの医療費について、病院から電話や手紙などで督促を受けることになるでしょう。
(2)(連帯)保証人に請求する
入院時に(連帯)保証人を立てている場合、病院は、未払いの医療費を保証人に請求することがあります。
保証人にも経済的な負担がかかるため、注意が必要です。
(3)弁護士から請求される
病院から督促を受けても真摯に対応しなかったり、無視して支払わなかったりすると、病院は、未払いの医療費を回収するために、弁護士を通じて請求することがあります。
通常の封書ではなく、内容証明郵便で請求されることもあります。
弁護士からの連絡で驚くかもしれません。どうしたらよいか分からず連絡できずに放置する方もいるかもしれません。しかし、弁護士からの連絡を放置して対応しないでいると、裁判を経て、さらに差し押さえなどの法的措置をとられる可能性も高くなりますので、無視はしてはいけません。
入院費用が払えないときの対処法
公的制度を利用しても、どうしても入院費用が払えない場合、以下の対処法を検討してください。
(1)分割払いができないか相談する
まずは病院に相談し、分割払いが可能か確認しましょう。
病院によっては、患者の経済状況に応じて柔軟に対応してくれる場合があります。
(2)他にも借金がある場合は債務整理を検討する
他にもカード会社や銀行などからの借金もあって支払いの継続が難しい場合、債務整理を検討することが有効です。債務整理の中の任意整理という手続きにより他の借金を整理すれば、月々の支払いの負担を軽減できる可能性があります。
他の借金の支払の負担を軽減して余裕ができれば、そこから入院費用を支払うこともできるかもしれません。
「返済が苦しいな」と思ったら、一度弁護士に相談してみましょう。
【まとめ】
入院費用が払えない場合、まずは高額療養費制度や傷病手当金などの公的支援制度を活用できないか調べてみましょう。分割払いができないか病院に相談してみる方法もあります。
経済的問題は、対策をせず放置していると悪化するリスクがあります。他にも借金があり返済に困っている場合には、弁護士に相談しましょう。
アディーレ法律事務所では、任意整理についてのご相談は何度でも無料です。
また、任意整理をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所に、お支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております(2025年4月時点)。
任意整理でお悩みの方は、任意整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。