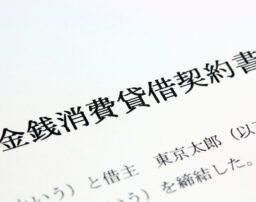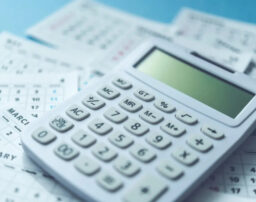「借金を返せないと、何かの罪になってしまう?」
借金をする時は、借入先に対して返済すると約束して借りることとなるので、返済を滞納してしまうとか、返済できなくなってしまうのは約束を破ることになります。
確かに、返済を滞納してしまえば「返す」という約束を破ることになりますが、必ずしも「犯罪」が成立するわけではありません。
借金を滞納し続けた場合は、裁判所での裁判などの手続きのうえ、最終的には財産を差し押さえられるというのが基本です。これは、「滞納」が「犯罪」として扱われているわけではなく、あくまでも「借金を返す」という民事上の義務を果たしていないことが原因です。
借金について詐欺罪などが問題となり、刑事事件になるのは「最初から踏み倒すつもりで借りた」などのごく例外的なケースにとどまると考えられます。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 借金滞納自体が「犯罪」になる可能性は基本的に低いこと
- 借金について、詐欺罪成立のおそれがある3つのケース
- 借金について、詐欺罪以外に成立するおそれのある犯罪

借金の滞納そのものが「罪」に問われる可能性は低い
まず、お金を返せないことによって起こりうる法的リスクをみていきましょう。
(1)基本的に、借金トラブルは民事事件
お金を借りるとき、私たちは「金銭消費貸借契約」という契約を締結します(民法587条)。
そして、約束した時期にお金を返すことができないことを、法的な義務(債務)の履行が遅れているという意味で「履行遅滞(りこうちたい)」といいます。履行遅滞は、債務を果たさない「債務不履行(さいむふりこう)」のうちの1つです。
※債務不履行には、履行遅滞以外にも「履行不能(りこうふのう)」「不完全履行(ふかんぜんりこう)」というものがあります。
履行不能とは、債務者がどう頑張っても債務の履行を果たせないことです。不完全履行とは、一応は債務が履行されているものの、十分に履行されているとは言えないことです。
債務不履行について、詳しくはこちらをご覧ください。
「金銭消費貸借契約」について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
民法415条1項では、次のように、債務不履行があった場合には原則として債権者から債務者に損害賠償を請求できると規定されています。
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
引用:民法415条1項
そのため、債務不履行となると、借主(債務者)は遅延損害金を支払わなければなりません。
でも、「債務者の責めに帰することができない事由」で債務不履行になっているなら、遅延損害金は払わなくていいんじゃないの?
確かに民法415条1項ただし書では、不可抗力による債務不履行の場合には損害賠償請求ができないと定められています。
しかし、借りたお金を返す債務など、金銭を支払う債務の場合には、たとえ不可抗力が原因で債務不履行になってしまった場合であっても、損害賠償責任を免れることができないのです(民法419条3項)。
そのため、災害などの天変地異による債務不履行だったとしても、遅延損害金を払わなければならないのです。
また、返済の遅れが続くなどして「期限の利益」を失うと、今までは分割払いでよかったところ、残っている債務を一括で支払わなければならなくなります(期限の利益というのは、期限が来るまでは返済を待ってもらえるという、借主にとっての利益です)。
「期限の利益」について、詳しくはこちらをご覧ください。
このような状況になると、貸主から裁判を起こされるリスクがありますし、貸主勝訴の判決が下されるなどすると、給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまう事態にもなりかねません。
借金を滞納した場合の差押えのリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。
このようにお金を返せないことによって、民事上の問題が生じることがあります。
(2)民事事件が刑事事件化することも……?
借金返済を滞納した(履行遅滞)からといって、それだけでは通常は犯罪とはならず、告訴などされることも通常ありません。
例えば、いわゆる「自転車操業」(あるところに返済するために、別のところから借りることの繰り返し)での借金を返済できなくなっても、借主が貸金業者を騙そうとして(偽った事実を申告するなどして)借入れを受けたのでなければ、詐欺罪に該当する行為がなかったということとなり、詐欺罪として告訴される可能性は低いと言えます。
ただし、借主が貸金業者を騙して借金した場合などは、借金の返還を求める訴えなど民事上の請求とは別に、詐欺事件として貸金業者に刑事告訴されたり被害届を提出されたりする可能性があります。
詐欺罪の成立があり得る具体例
それでは、借金関係で詐欺罪が成立する可能性がある場合の例をいくつかご紹介します。
(1)始めから返済の意思がないのに、借入れをした
このような場合は、返すつもりがないのに借りるということで貸金業者から金銭をだまし取ったとして、詐欺罪が成立する可能性が極めて高いです。
返済する意思があったと主張しても、もとから返済できる見込みが立たない状況で借入れをしたような場合、「このような状況では返済できないのは明らかである以上、返済の意思はなかったと考えられる」とみられて、詐欺罪が成立するおそれがあります。
(2)偽りの情報で契約を締結して借入れをした
例えば、次のような行為は詐欺罪における「欺く行為」にあたる可能性があります。
- 実際より高い年収を申し出た
- 退職済みの会社を勤務先とした
- 事業資金を補填するために借りるのに、書面上は「生活費」とした
詐欺罪における欺く行為とは、相手からお金などの財産を渡してもらうために、嘘をついたりすることです。
例えば、実際より高い年収を申し出れば、「それだけ年収があるなら、しっかりお金を返してくれるはず」と相手は誤認してしまい、お金を貸す可能性があります。
たとえ借金完済に至ったとしても、そもそも「借入れの時点で、詐欺的な行為をしてお金を受け取ったこと」が犯罪として問題となるため、詐欺罪が成立する可能性があります。
(3)偽りの理由で支払条件の変更を承諾してもらった
詐欺罪は、金銭や物品をだまし取らなくとも成立することがあります。
刑法246条2項では、次のように規定されています。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用:刑法246条2項
例えば、実際には浪費によって返済に窮しているのに、「家族の病気で入用になってしまった」などと嘘をついて支払条件の軽減に承諾してもらうことなども、欺く行為によって、経済的な利益(=財産上の利益)を得たものとして詐欺罪が成立する可能性があります。

借金問題で詐欺罪以外に考えられる犯罪について
借金問題が原因で成立する可能性がある、詐欺罪以外の犯罪の例について、いくつか紹介します。
(1)私文書偽造・行使罪
例えば名義を偽って借入れの申込書を作成したり、実際よりも収入が高いように見せるため、提出を求められた源泉徴収票などを偽造して提出した場合、私文書偽造罪(刑法159条1項)や同行使罪(刑法161条)が成立する可能性があります。
(2)詐欺破産罪及び詐欺再生罪など
詐欺破産罪とは、基本的に自己破産をする人が債権者を害する目的で一定の行為(財産を隠匿・損壊する行為など)をした場合に成立する犯罪です(破産法265条)。
このような行為をすると、刑事罰が科されるだけでなく、自己破産の手続きをしても支払義務を一切免除してもらえない(免責不許可)リスクがあります(破産法252条1項1号)。さらに、一旦は免責を得ていたとしても、免責が取消しになる可能性もあります(破産法254条1項)。
詐欺再生罪とは、基本的に個人再生をする人が債権者を害する目的で一定の行為(財産を隠匿・損壊する行為など)をした場合に成立する犯罪です(民事再生法255条)。
このような行為をすると、刑事罰の対象となるほか、個人再生の手続きをしても支払義務を減額してもらえない「再生計画不認可」となったり(民事再生法174条2項3号など)、いったんは認可された再生計画が取消しとなる可能性が高まります(民事再生法189条1項1号)。
自己破産や民事再生の手続きを行う場合には、破産法や民事再生法で定められた罰則がこれ以外にも存在しています。
【まとめ】経歴・年収について嘘をついて借金をしたり、返すつもりがないのに借金をした場合、詐欺罪が成立するおそれがある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 借金を返せない場合、基本的には「裁判→財産への差押え→滞納分の回収」という流れをたどることが多く、返せないというだけで詐欺罪などの刑事事件になることは少ない。
- 刑事事件になることが少ないとはいえ、次のような悪質なことをした場合には、詐欺罪が成立するおそれがある。
- 返済の意思がないのに借入れをした
- 偽りの情報で契約を締結して借入れをした
- 偽りの理由で支払条件の変更を承諾してもらった
- 偽りの情報を書いた借入れの申込書を作成、提出する行為に私文書偽造罪や同行使罪が成立するおそれもある。また、借金を返せなくなって個人再生や自己破産といった手続きをすることとなった場合、財産隠しなどの一定の悪質な行為をすると「詐欺再生罪」や「詐欺破産罪」が成立するおそれもある。
一般的に、借金を滞納したというだけでは詐欺罪は成立せず、逮捕・起訴などされる可能性は高くはありません。しかし、状況によっては刑事事件化する可能性がないとはいえません。
詐欺罪が成立しないようにするためには、借金をするとき、返すつもりで借りるのはもちろんのこと、年収などについて嘘をつかずに申し込むことが大切です。
もしも既に借金を抱えていて、「返済するためのお金は借金で調達するしかない。でも、年収や勤務先について嘘をつかないと、到底お金を貸してもらえなさそう」という場合でも、嘘をついて借金してはいけません。返済に困っている場合は、返済のために借金を増やすのではなく、今抱えている借金を解決する方向で検討するのがおすすめです。
具体的には、「債務整理」という、返済の負担を軽減するための方法があります。
債務整理には、主に次の3種類があります。
〇任意整理:返済期間の長期化による毎月の返済額の減額や、今後発生するはずだった利息(将来利息)のカットなどを目指して、個々の債権者と交渉。
〇個人再生:裁判所から認可を得て、基本的に大幅に減額された負債を原則3年間で分割払い。ケースにもよるが、任意整理よりも大幅に減額されることが多い。
〇自己破産:裁判所が「免責許可」を出せば、原則全ての支払義務が免除される。
※どの手続きをしても、税金など一部の支払義務は減らしたり無くしたりすることができません。
「債務整理をしてみようかな」と思われた方は、債務整理を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2022年10月時点)。
※ただし、自己破産で「免責不許可」となったり、個人再生で「再生計画不認可」となったことが、次の場合に起因する場合などは、返金対象外です。
- アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
- 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合
債務整理をしてみようと思われた方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。