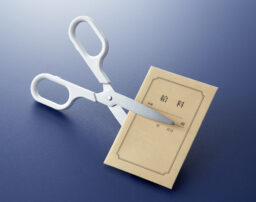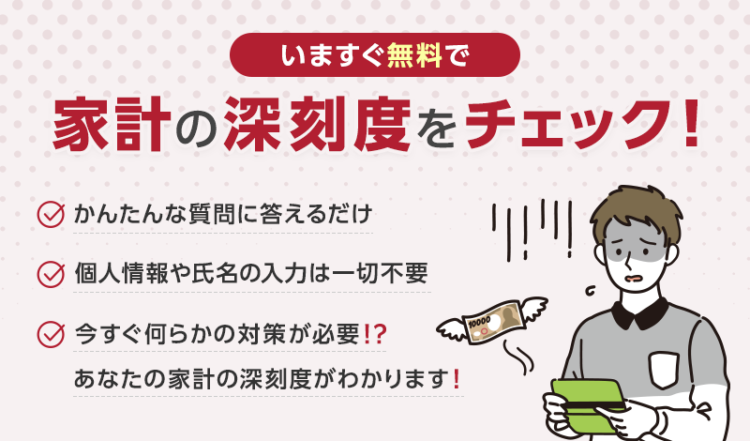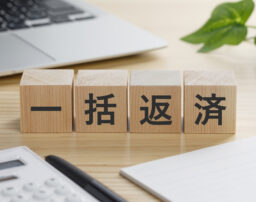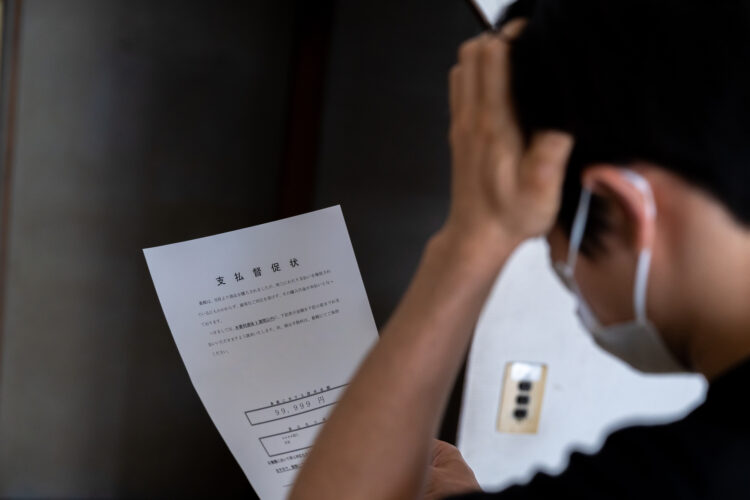「コロナの影響で失業してしまい、借金などの支払いができない。どうしたら良いだろう…。」
新型コロナウイルスの影響により、勤務先が倒産するなどして失業した方は少なくありません。
独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、「新型コロナウイルス」関連倒産は2020年度から徐々に増え続け、2022年8月の倒産件数492件のうち、193件を占めています。
コロナの影響で失業した方に対してはさまざま公的支援がありますが、今回の記事では、「失業保険」についてご説明します。
コロナの影響で失業した場合は、失業保険を給付する際に一般の離職の場合と比較して早めに給付を受けられるなどの制度があります。
このことを知っておけば、コロナの影響で急に失業して、他の支払いができないという事態を回避できる可能性が高まります。
今回の記事では、次のことを弁護士がご説明します。
- コロナの影響で失業した場合の失業保険の特例
- 失業保険の給付日数延長の特例
- 借金問題を解決する「債務整理」 など
参照:国内統計:企業倒産状況|独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)
コロナの影響で失業して、各支払いができない方への支援策
国は、コロナ対策として、コロナの影響で失業した方に対する各種の支援を行っています。もしもコロナの影響で失業し、各支払いができない場合には、活用できる支援を積極的に活用しましょう。
コロナの影響で失業した場合の失業保険の特例
失業保険とは、雇用保険から給付される基本手当です。
コロナの影響で勤務先が倒産するなど、本人には責任のない事情で失業してしまったような方は、とりわけ保護の必要性が高いと言えます。
そこで、コロナの影響で失業した方は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当し、次のような点で、一般の離職に比べて手厚い保護を受けることができる可能性があります。
【受給資格について】
一般の自己都合などによる離職の場合は、失業手当の給付を受けるには、離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があることが必要とされます。
これに対し、特定受給資格者・特定理由離職者の方が失業手当の給付を受けるには、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があることが必要とされ、失業手当の受給資格要件が緩和されています。
【所定の給付日数について】
自己都合などによる一般的な離職の場合、失業手当の所定給付日数は90~150日(被保険者期間による)となっているのに対し、特定受給資格者と一部の特定理由離職者は年齢によって90~330日となっています。よって、一般的な離職の場合に比べて日数の上限が拡大されており、より長い期間にわたって給付を受けることができる可能性があります。
(※被保険者であった期間が短い場合、通常の離職者と変わらないこともあります)
【給付制限日数について】
やむを得ない正当な理由とはいえない自己都合によって退職する場合など、一般的な離職の場合は、離職票をハローワークに提出してから、7日間の待期期間及びそれに加えて給付制限期間(2020年9月30日までに離職した場合は3ヶ月、2020年10月1日以降に離職した場合は5年間のうち2回までは2ヶ月)を経て、失業手当の支給が開始されます。
他方、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合には、このような給付制限期間がなく、待期期間7日間の翌日から給付が開始されます。
特定受給資格者・特定理由離職者について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(1)コロナの影響による失業が「特定受給資格者」に該当する場合とは?
前提として、特定受給資格者とは倒産や解雇などの理由で、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた場合です。
さらに、「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例」により、2020年5月1日以降、次の理由により離職した方についても「特定受給資格者」に該当するとされました。
- 本人の職場で感染者が発生したこと
- 本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
- 妊娠中であること
- 高齢(60歳以上)であること
「基礎疾患」とは、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などのほか、透析を受けている方や免疫抑制剤及び抗がん剤などを利用している方が含まれます。
上記のようなコロナの影響で失業した方で、特定受給資格者として失業保険の給付を希望される方は、次の確認資料を準備の上、ハローワークにお問い合わせください。
- 新型コロナウイルスに感染したことや基礎疾患のあることが分かる医師の診断書、医療明細など
- 同居の家族の状況が分かる世帯の住民票など
- 妊娠の分かる母子手帳など
- 職場で感染者が発生したことが分かる事業主の証明書 など
参照:ハローワーク|厚生労働省
(2)コロナの影響による失業が「特定理由離職者」に該当する場合とは?
前提として、特定理由離職者とは、次のようなケースに該当する場合です。
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことにより離職した場合(※本人が契約更新を希望していた場合に限ります。)
- 体力不足、心身の障害、疾病、妊娠・出産・育児などにより離職した場合や、父母の死亡、疾病、負傷に伴う父母の扶養のために離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変したことにより離職した場合など、正当な理由により離職した場合
さらに、「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例」により、2020年2月25日以降、次の理由により離職した方も「特定理由離職者」に該当するとされました。
- 同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要になったことから自己都合離職した場合
- 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
(※2020年2月25日から同年4月30日までの離職について。上記理由で同年5月1日以降に離職した場合には、先ほどご説明したとおり「特定受給資格者」に該当します。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要になったことから自己都合離職した場合
さらに、2022年5月1日以降、次の理由により離職した方についても「特定理由離職者」に該当するとされました。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業(※)し、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったこと
(※部分休業を含みます。また、休業手当の支払いの有無は問われません)
なお、シフト制で働いている方については、コロナによりシフトが減少して(本人が希望して減少したケースは除きます)、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、2021年3月31日以降に離職した場合には「特定理由離職者」になります。
もっとも、この特例は2023年5月7日をもって終了しています。そのため、2023年5月8日以降に離職した方は、「特定理由離職者」には該当しなくなります。
参照:新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します|厚生労働省
これらの理由により離職した場合には、自己都合であっても「特定理由離職者」に該当しますので、失業保険の受給資格が緩和されるなどの厚い保護が受けられます。
もしも、ご自身が該当するようでしたら、必要書類などはハローワークにお問い合わせください!
失業保険の給付日数の延長に関する特例について
さらに、コロナの影響で失業された方は、今後、コロナ禍での求職期間が長引く可能性があることに考慮して、次のとおり、失業保険の給付日数の延長が認められる可能性があります。
【対象者】
住んでいる住所地における緊急事態措置実施期間の末日の翌日から起算して、1年以内に基本手当の所定給付日数を受け終わる(受け終わる認定日がある)方で、次の1~3に該当する方。
(※2022年3月31日以前に発令された緊急事態宣言については、2022年10月1日までに受け終わる(受け終わる認定日がある)方も含みます。)
| 離職日(※) | 対象となる方 |
|---|---|
| 1.緊急事態措置実施期間前 | 全受給者(離職理由は問わず) |
| 2.緊急事態措置実施期間中 | 特定受給資格者+特定理由離職者 |
| 3.緊急事態措置実施期間後 | 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者+特定理由離職者(雇止めの場合に限る) |
(※お住まいの地域によって異なります)
(就職困難者の方は、当初から給付日数が長いため対象になりません)
参照:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について|厚生労働省
本来の失業保険の給付日数は、基本的には次のとおりです。
【失業保険の給付日数】(2017年4月1日以降に離職した場合)
| 退職理由 | 年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
| 特定受給資格者 ・特定理由離職者 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 自己都合 退職(原則) |
65歳未満 | - | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
上記給付日数の延長が認められると、次の方を除いて、基本的には上記の表から給付日数が60日延長されます。
- 35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方は30日延長(➡300日まで)
- 45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方は30日延長(➡360日まで)
コロナによる給付日数の延長の対象となる方は、各ハローワークで基準に照らし延長を判断・処理しますので、別途申請などは必要ありません。
もっとも、所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合など、延長の対象とならないケースがあります。もしもご自身のケースで延長がされていないようでしたら、各ハローワークにお問い合わせください。
以上のとおり、コロナの影響で失業した場合、自己都合の離職であっても、特定受給資格者や特定理由離職者に該当して7日間の待期期間後に失業保険を受け取ることができますので、急な失業により支払いができないリスクを減らすことができます。
失業保険の給付を検討されている方は、ぜひ、今回の特例に該当しないかご確認ください。
さらに、コロナの影響で、給料が支払われないまま勤務先が倒産した場合には『未払賃金立替払制度』が利用できるケースもありますので、併せてご確認ください。
未払賃金立替制度について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
公的支援を受けられないときは「債務整理」の検討を

コロナの影響で失業したけれど十分な公的支援が受けられず、借金などの支払いができないという場合には、「債務整理」をご検討ください。
借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金の負担を軽くするための手続きを『債務整理』と言います。
『債務整理』には、主に『任意整理』『民事再生』『自己破産』があります。
債務整理のうち、どの方法が一番いいかは、家計の状況(毎月いくらまで返済に回せるか)や、今後の収入の見込み、極力手放したくない財産の有無などによって変わってきます。
債務整理についての相談は無料という法律事務所も少なくないので、まずは気軽に弁護士に相談してみることをおすすめします。
早めに踏み切るほど、日常生活への影響が小さい方法にできる可能性があります。
また、いろんなところから借金をしていて、一見、もうどうにもならないと思われる状態であったとしても、中には、利息を払いすぎている場合(いわゆる過払い金)があって、計算し直すと借金が大幅に減る方がいらっしゃいます。
その結果、計算し直した後の借金を「任意整理」などで返済していくことが可能となるケースがあります。
コロナの影響で失業し、借金などの支払いができないという場合には、借金問題の解決方法につき、まずは、弁護士にご相談ください。
【まとめ】コロナの影響で失業した場合、失業保険の「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当しないかご確認ください
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- コロナの影響で失業した場合、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当する可能性がある。
- 「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当すると、失業保険の給付を受ける際、通常の離職者と比べて、次の点で厚い保護が受けられる可能性がある。
- 受給資格の要件が緩和される
- 所定の給付日数が長くなる
- 7日間の待期期間の翌日から給付が受けられる
- コロナの影響で勤務先が倒産し、未払いの給料がある場合には、未払賃金立替制度を利用できないか検討すべき。
- 公的支援では、借金の支払いができない場合には、債務整理を検討すべき。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続きの場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2022年11月時点)
コロナの影響で失業し、借金などの返済にお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
失業保険についてお悩みの方は、ハローワークにお問い合わせください。