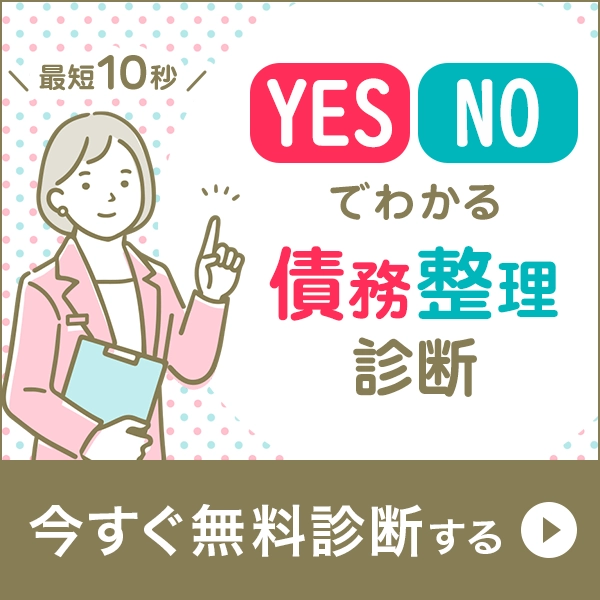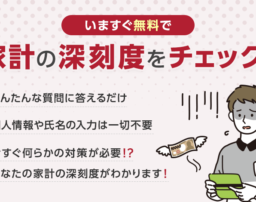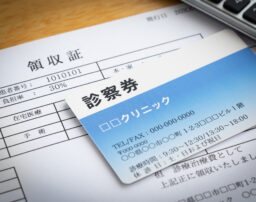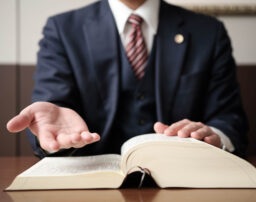「親が借金を返せないとき、子供がその借金を肩代わりすべき?」
かつて日本では「親の面倒を子供がみる」との考え方が支配的でした。
そのためか、悪質な貸金業者が親の借金の返済を子供に迫ることもあります。
果たして親の借金を子供が肩代わりする義務はあるのでしょうか。
結論から言えば、親の借金はあくまでも親の借金ですので、原則として子供が肩代わりする義務はありません。
ただし、子供が親を相続した場合など限定的なケースでは子供が親の借金を肩代わりしなければしない可能性もあります。もし親の借金を肩代わりしなければならなくなる状況になりそうであれば、その回避方法も知っておきましょう。
この記事を読んでわかること
- 親の借金の有無を調べる方法
- 親の借金を子供が肩代わりしなければならないケース
- 肩代わりする必要のない親の借金返済を迫られた場合の対処法
- 親の借金の肩代わりを回避方法
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
ここを押さえればOK!
・子供名義で親が借金をし、子供が承諾していた場合
・親が亡くなり、借金が相続される場合
・子供が親の借金の保証人・連帯保証人である場合
肩代わりを避ける方法として、(1)相続放棄や(2)限定承認、(3)自己破産が挙げられます。相続放棄は全ての財産を放棄し、限定承認はプラスの財産の範囲内で借金を相続するものです。自己破産は返済困難な場合に借金をゼロにする方法ですが、信用情報に影響が出ます。親が存命中であれば、借金の債務整理をしてもらうことも考えられます。
親の借金を調べるには、抵当権の確認や郵便物・通帳のチェック、信用情報機関への開示請求が有効です。親の借金の有無を知っておくことは、相続の際の選択肢を考える上で重要です。
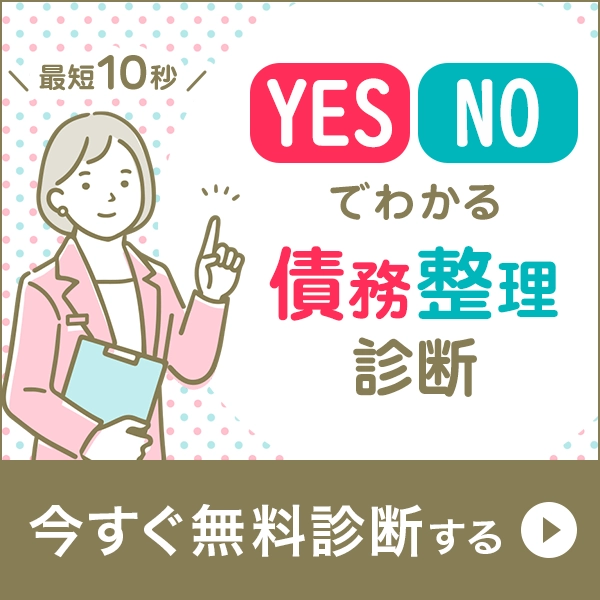
「親の借金を子供が肩代わりする必要はない」のが原則!
親の借金は、原則子供が肩代わりする必要はありません。
借金を返済しなければならないのは、あくまでも借主本人もしくは保証人です。
親が作った借金だからといって、子供が肩代わりしなければいけないわけではありません。
肩代わりする必要のない借金を取り立てられた場合の対処法は?
肩代わりする必要のない借金であっても、「親の借金なのだから、子供が払うべき」と借金の取り立てにあうこともあるかもしれません。
しかし、 貸金業者が債務者以外の第三者に返済を請求することは違法です(貸金業法21条1項7号)。
そのため、返済義務のない親の借金の返済を求められたら、きっぱりと断るようにしましょう。
返済の取り立てがしつこい場合には、脅迫罪や強要罪に当たる可能性もあります。そのような場合には、警察や弁護士に相談するのもおすすめです。
親の借金を子供が返済しなければならないケースとは?
一方で、親の借金を子供が肩代わりしなければならないケースもあります。
実は、次のようなケースでは、子供の希望とは関係なく、原則として、子供が親の借金を肩代わりする必要があります。
- 「子供の名義」で親が借金をしていた場合
- 借金を完済する前に親が死亡した場合
- 子供が親の借金の保証人になっていた場合
それでは、具体的にみていきましょう。
(1)「子供の名義」で親が借金をしていた場合
「子供の名義」で親が借金をすることを子供が承諾していた場合、子供は親の借金であっても肩代わりする必要があります。
例えば、審査が通らずに借りられないなどの理由で、親から「お金を借りて欲しい」と頼まれて「名前ぐらい貸してもいいか」と思い、承諾してしまうケースなどです。
一方で、子供の承諾が全くないままに、子供名義で親が勝手に借金を借りていた場合は、子は返済する必要はありません。
(2)借金を完済する前に親が死亡した場合
借金のある親が亡くなった場合、その借金は子供に相続され、子供が親の借金を肩代わりしなければなりません。
「相続」というと財産をもらえるイメージがあるかもしれませんが、借金も相続の対象です。
例えば、父親の200万円の借金を母親と子供2人(息子・娘)で相続した場合を考えてみましょう。この場合、遺言などがなければ、法律の定める相続分に応じて財産を相続することになります。
亡夫 200万円の借金
➡妻 法定相続分1/2を相続する 借金100万円
➡息子 法定相続分1/4を相続する 借金50万円
➡娘 法定相続分1/4を相続する 借金50万円
もし既に両親がともに亡くなっていれば、財産を子供間で均等に分配します。
(3)子供が親の借金の保証人になっていた場合
子供が親の借金の保証人や連帯保証人になっている場合にも、子供が親の借金の肩代わりをしなければなりません。
既に保証人や連帯保証人なのであれば、親がきちんと返済できているかを把握しておくことが大切です。
2020年4月1日以降に締結した保証契約であれば、債権者は保証人や連帯保証人から残債務などについて問い合わせに必ず回答しなければいけないことになりました。
まずは、債権者に確認してみましょう。
そして、すでに返済に困っているようであれば、弁護士に債務整理を相談することを検討しましょう。
親と子供が保証人の関係にある場合、親と子供双方の債務整理が必要になることがあります。詳しくは債務整理を扱う弁護士にご相談ください。
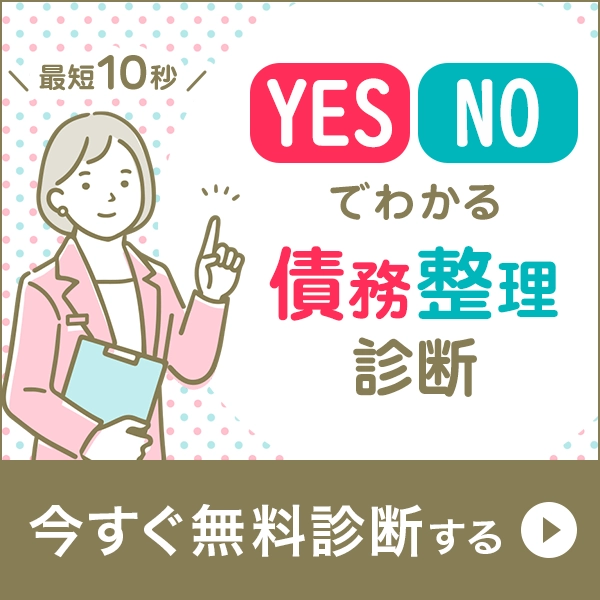
親の借金の肩代わりを回避する方法とは?
親の借金を相続してしまいそうな場合には、相続放棄・限定承認・自己破産をすることで親の借金の肩代わりを回避することができる可能性があります。
また、親が存命中であれば債務整理をしてもらうことで、借金額をゼロにできたり、減らしたりすることができます。
(1)相続放棄する
相続する財産が銀行預金や不動産のようなプラスの財産よりも借金のほうが明らかに多い場合には、「相続放棄」を検討しましょう。
相続放棄とは、相続する権利を全て放棄することです。つまり、相続放棄をすると借金だけでなくすべての財産を相続できなくなります。
相続放棄をするには、親の死亡を知ってから原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄をしたからといって、親の借金がなくなるわけではありません。
相続放棄をすると、相続をする権利は次順位の相続人に移ります。
相続放棄についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(2)限定承認を行う
どうしても相続したい財産がある場合には、「限定承認」を検討しましょう。
限定承認とは、プラスの財産の限度で、借金を相続することです。
例えば、300万円の資産、700万円の借金がある場合には300万円分の資産と借金をそれぞれ相続することになります。
相続人が複数いるときには、相続人全員で限定承認をする必要があります。相続放棄と同様、親の死亡を知ってから原則として3ヶ月以内に、限定承認の申述審判申立書等を家庭裁判所に提出することになります。
(3)自己破産をする
子供が保証人・連帯保証人となっていた場合や相続を避けられなかった場合など、子供が親の借金の肩代わりをしなければなりませんこともあるでしょう。
しかし、借金額が高額で払えない場合には、「自己破産」を検討しましょう。
自己破産をすると、支払いができないことを裁判所に認めてもらえれば、法律上、借金をゼロにしてもらうことができます。
ただし、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されたり、車や不動産を差しさえされたりする可能性があるので、注意しましょう。
払えないほどではないが、返済が厳しいということであれば、任意整理や個人再生を検討しましょう。任意整理や個人再生をすることで借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりできる可能性があります。
(4)親に債務整理をしてもらう
まだ親が生きている場合には、親に債務整理を進めてもらうことも一つの方法です。
親が債務整理をすれば、親の借金を減らしたり、無くしたりできる可能性があります。
どうも親が借金をしているようだという方は、まずは借金額などを調べた上で、良い債務整理の途がないか、弁護士などに相談されることをお勧めします。
親が古くから借金をしている場合には、思わぬ「過払い金」が発生していることがよくあります。
そして、過払い金があれば、親の手元にお金が戻ってくることもあります。
まずは、借金の借入・返済時期などを調べてみてください。
親の借金の調べ方とは?
親として弱みを見せたくないという思いから、借金の有無を子供に教えないということがあります。
しかし、子供として親の借金を知っておくことは大切です。親の借金の有無を知っておけば、親の生活の立て直しに向けて行動を起こすこともできますし、相続をするのかどうかも考えておくことができます。
ここでは、親の借金の有無を調べる方法を紹介します。
(1)抵当権を調べる
親が生きており、建物や土地を所有している場合には、抵当権が設定されているかを調べてみましょう。
インターネット上の「登記情報提供サービス」や「登記・供託オンライン申請システム」で簡単に登記情報を調べることも可能です。
抵当権が現存している場合には、かなり高い確率で借金があります(ただし、住宅ローンであることも多いです)
(2)郵便物や通帳をチェックする
親が生きている場合はなかなか確認しにくいでしょうが、親の同意を得て郵便物や通帳をチェックするのも親の借金を知る有効な手段です。
債権者からの督促状や裁判所からの書類が届いているかもしれません。
また通帳をみることで、毎月債権者からお金を引き落とされているのがわかるかもしれません。
(3)信用情報機関に情報開示請求を行う
親が亡くなった場合には、信用情報機関に信用情報の開示請求を行うのが良いでしょう。
信用情報を見れば、親がどの貸金業者から借り入れをしていたのかなどを知ることができます(ただし、契約終了から一定期間経った取引は記録が削除されています)。
信用情報機関は、次の3つです。3つ全てに開示請求するのが良いでしょう。
- シー・アイ・シー(CIC)
- 日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター
ただし、友人や知人等、信用情報機関に登録していない者から借りていた場合には信用情報からは借金を把握できないので、注意してください。
【まとめ】親の借金は子供が肩代わりする必要はないのが原則
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 親の借金はあくまでも親の借金であって、基本的には子供に返済義務はない。
- 子供が親の借金を肩代わりしなければならないケース
- 「子供の名義」で親が借金をしていた場合
- 借金を完済する前に親が死亡した場合
- 子供が親の借金の保証人になっていた場合
- 親の借金の肩代わりを回避する方法
- 相続した場合には相続放棄又は限定承認をする。
- 自己破産をする
- 親に債務整理をしてもらう
「親の借金を相続したくない」方は、相続放棄を検討してください。
相続放棄は親の死亡を知ってから原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりませんので、早めに行動するようにしましょう。
アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料です。
相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談ください(2024年10月時点)。
また、親が生きている間に借金についても話し合い、返済が難しいようでしたら、早めに債務整理をすることをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2024年10月時点)。
債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。