自転車事故の場合には、自動車事故とは違い、十分なお金を受けとれない可能性があります。
なぜなら、自動車とは違い、保険の加入が強制されておらず、自転車保険(もしくは自転車事故に対応する保険)が未加入なケースがあるからです。
そもそも自転車事故であっても自動車やバイクが相手の場合には、相手の自動車保険などから補償(お金)を受けとることができるのが原則です。
一方、歩行者対自転車や自転車対自転車の事故の場合には、相手が自転車保険(もしくは自転車事故に対応する保険)していない限り、相手の保険から補償(お金)を受けとることができません。
相手の保険会社から補償(お金)を受けとることができない場合には、加害者に対して直接治療費といったお金を受けとるか、もしくはあなた自身の保険から補償(お金)を受けとる必要があります。
相手が未保険の場合に知らず知らずのうちに損をしてしまうことを防ぐために、未保険によって受けてしまう影響について知っておきましょう。
そこで今回の記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 自転車事故の被害者が保険会社から受けられる補償(お金)
- 保険未加入の場合の3つの影響
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
自転車事故の被害者が保険会社から受けられる補償(お金)
自転車事故の被害者が受けられる補償(お金)について、次の2つのパターン別で見ていきます。
- 自転車が自動車・バイクと事故に遭った場合
- 歩行者が自転車と事故に遭った場合
- (自転車対自転車との事故に遭った場合も含む)
それぞれのパターン別に、どのような保険からどのような補償が受けられるのかを解説します。
(1)自転車が自動車・バイクと事故に遭った場合

あなたが自転車、相手が自動車・バイクの事故の場合は、基本的に自動車・バイクの相手が加入する自賠責保険と任意の自動車保険から補償(お金)を受けとることができます。
なぜなら、加害者が自動車・バイク(原付含む)の場合、法律で加入が強制されている自賠責保険(※)があり、加害者が任意の自動車保険に未加入の場合であっても、最低限、自賠責保険から補償(お金)を受けることができるからです。
(※)自賠責無保険の状態で自動車、バイク(原付)を運転する(運行させる)と、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という罰則があります(自動車損害賠償保障法第86条の3第1号)。
ただ、ここで注意してほしいのは、あなた側(自転車)の事故の過失割合が多く、かつ、あなた側(自転車)の被害が少ない場合には、逆に自動車やバイクの相手に対して賠償金を支払わなければならない可能性があることです。
あなた(自転車)から自動車やバイクの相手に対して賠償金を支払わなければならない場合には、次の保険を利用することができれば、自分や相手にかかる治療費などを支払うことができます。
- あなたが加入する「自転車保険」
→あなたや相手にかかる治療費などが支払われる - あなたが加入する自動車保険に付帯する「人身傷害保険」
→あなたのケガの治療費などが支払われる - あなたが加入する自動車保険に付帯する「個人賠償責任保険」
→相手にかかる治療費などが支払われる
保険の名称は保険会社によって異なりますし、具体的なケースにおいて保険が利用できるかどうかについては契約内容によって異なりますので、保険会社に問い合わせて確認するようにしましょう。
(2)歩行者が自転車と事故に遭った場合

あなたが歩行者で相手が自転車の事故の場合や、自転車対自転車の事故に遭った場合は、基本的に自転車である相手が加入する自転車保険か自動車保険の特約から補償(お金)を受けることになります。
自動車であれば強制加入させられる自賠責保険は、自動車・バイクが関連する事故のみが対象となります。
そのため、自転車対歩行者、自転車対自転車の交通事故の場合(自動車やバイクが関連しない事故の場合)には、被害者は、加害者加入の自賠責保険からは補償を受けることができず、自転車保険や自動車保険に対応する特約から補償を受けることになるのです。
ただし、自転車である相手が自転車保険未加入の場合や自転車事故に対応する自動車保険の特約を付帯していない場合には、相手が加入する保険からは補償(お金)を受けられない可能性があります。
しかし、自転車保険を義務化(罰則なし)する地方自治体が増えていることもあり、自転車保険から補償(お金)を受けることができるケースが多くなってきています。
保険未加入の場合に自転車事故の被害者が受ける3つの影響
自転車に乗る加害者が、自転車事故に対応する保険未加入の場合には、被害者は次のような影響を受ける可能性があります。
- 保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとれない
- 示談交渉が難しい
- 後遺症の損害賠償請求が難しい
それぞれどのような影響を受けるのかについて説明します。
(1)保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとれない
加害者が保険に未加入ですので、加害者の保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとることができません。
このような場合には、基本的に、被害者が受けた損害は、保険会社ではなく加害者に対して直接、請求することになります。
もっとも、自転車と歩行者の事故であっても、歩行者が死亡したり重篤な後遺症が残ったりするなどし、賠償額は何千万~1億円程度になることもあります。
このように高額な賠償額になった場合には、保険未加入の加害者が支払える資力があるとは考えにくいのが実情です。
このように加害者が支払うことができない場合には、被害者は自分が加入する保険から補償を受けられないかどうかを検討する必要があります。
あなたが医療保険や傷害保険に加入している場合には、あなたが加入する治療費、入院給付金、お見舞金、後遺障害保険金(傷害保険算定)などが、支払われることになります。
(2)示談交渉が難しい
加害者が保険未加入の場合には、示談交渉が難しくなる可能性があります。
そもそも、車やバイクが当事者となる交通事故では、一般的に、任意の自動車保険会社の担当者が、当事者の意見を聞きながら、当事者代わりに解決のための示談交渉を行います。
また、自転車対自転車、自転車対歩行者の自転車事故でも、示談交渉サービスが付帯された自転車保険や個人賠償責任保険に加入している場合には、保険会社の担当者や弁護士が当事者の代わりに示談交渉を行います。
しかし、加害者が保険未加入の場合には、このような示談交渉サービスも利用することはできませんので、保険会社の担当者ではなく加害者本人と直接示談交渉する必要があります。
ただし、加害者との直接の示談交渉は、交通事故に関して素人同士の話し合いになりますので、「自分は悪くない」「過失割合はそちらが多いはずだ」などと、感情的な言い合いになってしまい、示談交渉がうまく進まない可能性があるのです。
感情的な争いで示談交渉が決裂してしまうと、精神的なストレスに加えて時間や労力もかかります。最終的に訴訟による解決を選択せざるを得なくなり、解決までにさらに時間がかかります。
(3)後遺症の損害賠償請求が難しい
自転車事故(自転車対歩行者、自転車対自転車)で後遺障害が残った場合には、自賠責保険と異なり後遺障害の認定機関がないため、後遺症による損害賠償請求が難しくなる可能性があります。
そもそも、自動車・バイクが関連する事故の被害に遭い、後遺症が残った場合には、自賠責保険による後遺障害等級認定を受けることで、後遺症についての損害賠償金(逸失利益や後遺症慰謝料など)を加害者側に請求することができます。
例えば、後遺障害には1~14級があり(後遺障害1級が一番重い等級)、後遺障害1級が認定された場合には後遺症慰謝料2800万円(相場)など高額な損害賠償金が認められやすくなります。
一方、自転車事故(自転車対歩行者、自転車対自転車)の場合には、このような後遺障害等級認定制度が存在しません(※)。
そのため、加害者も被害者も何ら保険に入っていない場合や保険会社独自の等級認定の手続きが存在しない場合(労災保険も利用できない場合)(※参照)は、被害者が、自分で医療記録や診断書を準備したうえで、「自分に残った後遺症は、後遺障害等級の〇級相当である」ことを証明する必要があります。
そして、加害者側が被害者のその主張を受け入れればよいのですが、後遺障害の有無や等級の妥当性について争ってくる可能性もあり、話し合いで決着がつかないこともあります。
そうすると、最終的にはやはり訴訟による解決を目指すことになってしまいます。
(※)なお、任意保険会社によっては後遺障害等級について認定を行う制度が存在している場合があります。その場合は、保険会社に対して後遺障害申請手続きを行い、等級を認定してもらうことによって、認められた等級を前提に示談交渉を行うことができる場合があります。
また、事故状況によっては労災保険を利用することが出来ます。労災保険においても後遺障害の認定を受けることができるため、労災保険を利用して後遺障害の等級認定を受け、その等級を前提に示談交渉を行うことができる場合もあります。
労災の後遺障害について詳しくは、こちらをご覧ください。
自転車事故の問題を弁護士に相談すべき2つの理由
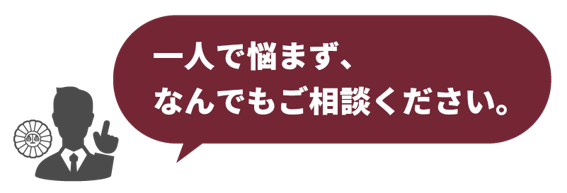
自転車事故であっても、交通事故に変わりはありません。
自転車事故の被害に遭った場合に、交通事故の対応をしている弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットがあります。
- 示談交渉がスムーズになる
- 損害賠償が受けやすくなる
それぞれ説明します。
(1)示談交渉がスムーズになる
弁護士は交渉のプロですので、依頼者の意図や希望を聞きながら、法的知識や経験に基づいて、冷静に加害者側と交渉をすることができますので、弁護士なしで交渉するよりもスムーズな示談交渉が期待できます。
弁護士は必要な資料や書面の作成も行いますので、被害者の負担を減らすこともできます。
また、加害者本人と直接話すことはストレスになることがありますが、弁護士に依頼すれば加害者本人と接触する必要はありませんので、ストレスを回避することもできます。
(2)補償(お金)を受けとりやすくなる
弁護士に相談・依頼することで補償(お金)が受けとりやすくなる可能性があります。
自転車事故の当事者同士で示談交渉すると、感情的な諍いで示談交渉が長引いたり、決裂しまったりすることがあるのは説明した通りです。
ただ、示談による解決は、双方にとって早期解決ができるというメリットもあり、実際に多くの交通事故は示談で解決していますので、まずは示談による解決を目指すべきです。
そこで、依頼を受けた弁護士が交渉することで、法的な根拠のある金額を提案し、冷静に相手方と話し合い説得を試みることができますので、相手方も感情的にならずに、こちらの話を理解して納得する可能性が高まります。
弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の心配なし?
弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の心配なく、弁護士に依頼することができる可能性があります。
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯されている、保険会社が弁護士費用を負担する制度のことをいいます(限度額あり)。
今のところ、自動車保険の通常の弁護士費用特約は、加害者か被害者のどちらかが車・バイク(原付)のケースのみ利用できることになっている商品がほとんどのようです。
したがって、残念ながら、歩行中のご家族が加害者の自転車に大けがをさせられたり、自転車同士で衝突して双方ケガをしたような場合には、自動車保険の通常の弁護士特約は使えないケースが多いと言えます。
ただし、「日常生活弁護士費用特約」を付帯させている場合には、自動車事故以外の日常生活における事故の解決を弁護士に依頼する際の弁護士費用が補償されます。
なお、弁護士費用特約は、あなたが加入している場合だけではなく、あなたの家族が加入している場合も利用できることがあります。あなたの加入する保険に「弁護士費用特約」が付いていない場合にもご家族の加入する保険についていないかをチェックしてみましょう。
弁護士費用特約についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
【まとめ】自転車事故の加害者が保険未加入の場合には十分な補償を受けられない可能性あり
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自転車利用者は、保険に未加入の場合が多い。
- あなたが自転者で相手が自動車・バイクの場合には、基本的に自動車・バイクの相手が加入する自賠責保険と任意の自動車保険から補償(お金)を受けとることができる。
- 一方、あなたが歩行者で加害者が自転車の場合には、相手方が自転車保険や自転車事故に対応する自動車保険の特約に加入している場合には、その保険により補償を受けることができる。
- 加害者の自転車が自転車保険や自転車事故に対応する自動車保険の特約に未加入な場合の3つの影響
- 保険会社から慰謝料などの補償(お金)を受けとれない
- 示談交渉が難しい
- 後遺症の損害賠償請求が難しい
- 自転車事故の加害者が保険未加入の場合、自身加入の保険で被害回復できないかを検討する必要があります。
- 弁護士に依頼することで(1)示談交渉がスムーズにいく、(2)補償(お金)を受けとりやすくなるなどのメリットがある。
- 「日常生活弁護士費用特約」がある場合は、自転車事故でも弁護士特約が使える。
自転車事故の被害にあい、補償が受けられるのか不安な方は、自転車事故を扱う弁護士への相談をおすすめします。



















