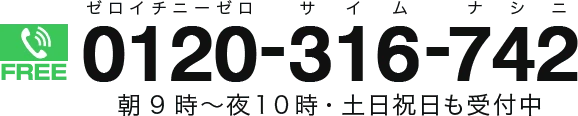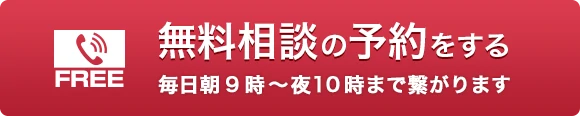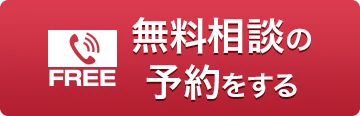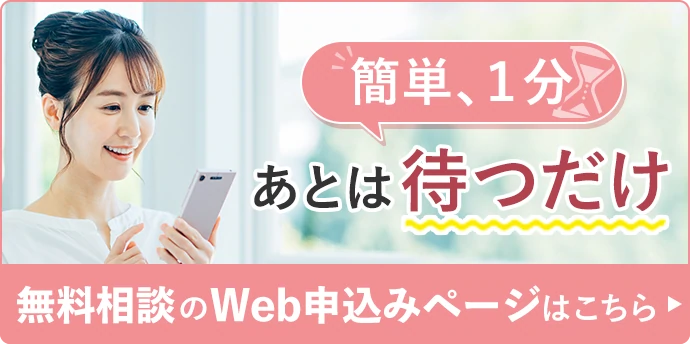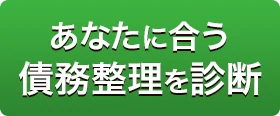免責不許可事由とは?該当すると自己破産できないって本当?

「自己破産をしても、借金がなくならないこともあるって聞いたけれど、それって本当?」
個人の自己破産手続における最終的なゴールは、借金の返済義務を免除してもらうことですが、法律上は「免責(許可)」と呼びます。
「免責不許可事由」とは、裁判所が原則として免責を認めないと法律が規定する事情のことです。
実は、自己破産を申し立てる方のうち、免責不許可事由がある方も少なくありません。
本ページで、免責不許可事由の正しい知識を得て、自分が該当するかどうか確認しておきましょう。
借金問題についての
無料相談ならアディーレ!

0120-316-742
【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります
免責不許可事由とは?
免責を認めない場合として法律上明記されているのが「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」です。
裁判例が免責を認めた場合、お金を貸した側(債権者)からみると、貸したお金を返してもらえず泣き寝入りするしかありません。そのため、債権者にとってあまりに不公平な場合などは、裁判所は免責を認めません。
基本的に自己破産を申し立てれば借金の返済義務は免除されますが、債権者に酷な行為をしたケースなど、例外的に借金が免除されない場合があるのです。
免責不許可事由の種類
免責不許可事由については、破産法第252条1項で次のとおり定められています。
債務者の財産を不当に減少させる行為
破産法第252条1項1号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
引用:破産法第252条1項1号
本来債権者に分配する資金となる財産(破産財団)の価値を減少させると、免責されないリスクが生じます。
逆に債務者が自由に処分できる財産(自由財産)を処分したり、不注意でその価値を損なったりしても、免責不許可事由には該当しません。
どのような場合が該当する?
たとえば、次のケースが「債務者の財産を不当に減少させる行為」にあたります。
車が大好きで借金を作ってしまったA(仮名)さん。お気に入りのフェラーリは中古価格でも数百万円を下らない車種でした。そのため、このフェラーリを処分されないようにするために、自分の彼女に10万円で売却しました。
本来、自己破産をすると、高価な財産は売却されてお金に替えられます。
そして、そのお金は債権者に公平に分配(「配当」といいます)されます。
ですから、自己破産をする場合には、一定の価値のある財産を手元に残しておくことができません。
しかし、だからといって、誰かに自分の財産を安く売却してはいけません。
安く売却すると、その分、債権者は本来受けられるはずであった配当を受けられなくなってしまいます。
高価な資産は、破産手続に則って処分されなければならないのです。
不当な債務負担行為
破産法第252条1項2号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
引用:破産法第252条1項2号
たとえば、次のケースが「不当な債務負担行為」にあたります。
- 違法な高金利(ヤミ金)でお金を借り入れた
- クレジットカードのショッピング枠で新幹線のチケットやゲーム機を購入して購入価格よりも随分と安い価格で売却した(換金行為)
一般的な金融機関がお金を貸してくれなくなったあとでこれらの行為を行う人は少なくありません。
しかし、本来であれば、借入限度額に達して、そのままでは返済の見込みが立たないとわかった段階で破産を検討すべきです。
そのため、借入限度額に達したあとで、これらの行為をすると「破産手続の開始を遅延させる目的」があったと認められるおそれがあります。
特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
破産法第252条1項3号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
引用:破産法第252条1項3号
たとえば、次のケースが「特定の債権者に利益があるように支払いをする行為」にあたります。
弁護士に自己破産を依頼して、貸金業者の借金の督促から免れたB(仮名)さん。自己破産の手続は終わっていませんが、お金を貸してくれていた勤務先の社長に10万円全額を返済しました。
このBさんの行為は、債権者のなかでも勤務先の社長だけに優先して返済をする行為ですから、偏頗弁済(特定の債権者にだけ返済する行為)にあたります。
本来、すべての債権者は公平に扱われなければならず、特定の債権者だけを優先することは許されません(「債権者平等の原則」といいます)。
浪費やギャンブルによる借金
破産法第252条1項4号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:破産法第252条1項4号
趣味などに収入に見合わない支出をした結果、またはギャンブルや投資で多額の借金をした結果、破産をしようとしてもスムーズには認められません。
どのくらいの支出をすれば免責不許可事由にあたるかは、収入や借金の総額などにもよるため、弁護士にアドバイスを求めるのがよいでしょう。
詐術による信用取引
破産法第252条1項5号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
引用:破産法第252条1項5号
たとえば、次のケースが「詐術による信用取引」にあたります。
200万円の年収なのに1,000万円もの借金を作ってしまったC(仮名)さん。さらにお金を必要としたCさんは、これまで取引のなかったクレジットカード会社で収入、氏名、借金の有無を偽ってクレジットカードを作り、ショッピングに利用しました。それから、4ヵ月後、弁護士に自己破産を依頼しました。
このCさんのような行為が「詐術による信用取引」です。
悪質なケースでは、詐欺罪という犯罪が成立する可能性もあります。
帳簿を隠す
破産法第252条1項6号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
引用:破産法第252条1項6号
隠すだけではなく、自分に作成権限のない帳簿を作ると、文書偽造罪も成立する可能性があるため絶対にやめてください。
うその債権者名簿を提出する
破産法第252条1項7号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
引用:破産法第252条1項7号
「債権者名簿」とは、自己破産の申立てのときに提出しなければいけない書面です。債権者名や住所、借入時期、現在の残高、借入金などの使い道、最終返済日などが記載されています。
この債権者名簿にうそを書くと、「債権者平等の原則」が果たされないおそれがあるため、絶対にやってはいけません。
また、債権者に嫌がらせをする目的で、意図的に特定の債権者だけ「債権者名簿」に載せなかったり、架空の債権者を載せたりすると、免責不許可事由に該当します。
裁判所への説明を拒絶したり、うその説明をしたりする行為
破産法第252条1項8号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
引用:破産法第252条1項8号
こちらについては、数多くある免責不許可事由のなかでも、免責が不許可になるリスクが非常に高いです。
裁判所や破産管財人の調査には素直に協力し、絶対にうそや隠しごとをしないようにしてください。
管財業務を妨害する行為
破産法第252条1項9号では、次の行為が免責不許可事由として定められています。
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
引用:破産法第252条1項9号
管財人等を脅迫する場合はもちろん、管財人の指示に従わない場合にも「管財業務を妨害する行為」に該当する可能性があるので注意してください。
過去7年以内に免責を受けたことがある場合
一度免責を受けたり、免責と同じような法律上の保護を受けたりしたことが7年以内にある場合、原則として2度目の免責は認めてもらえません(破産法第252条1項10号)。
破産法上の義務違反行為
破産法で定められている破産者の説明義務(破産法第40条1項)、重要財産開示義務(破産法第41条)、免責調査協力義務(破産法第250条2項)に違反するなどの行為は、免責不許可事由に該当します(破産法第252条1項11号)。
免責不許可事由に該当しても免責が許可される裁量免責とは?
免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責が許可される「裁量免責」という制度があります(破産法第252条2項)。
そのため、悪質なケース(※)以外は、免責不許可事由があっても裁量免責によって免責許可が下りるケースが多いのです。
※意図的な財産隠しや裁判所にうそをついた場合や7年以内に免責を受けたことがある場合など
「免責不許可事由に該当するから、自分は自己破産できないかも…」と心配されている方は、ぜひ一度、自己破産に関する専門知識や経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
免責にならない債権がある
免責が許可されても、すべての債権の支払義務が免除されるわけではありません。
一定の債権については、免責が許可されても支払義務は残ります。このような債権を「非免責債権」といい、具体的には以下のようなものが該当します。
- 税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
- 罰金
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 生活費など夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
- 養育費など子の監護義務に基づく請求権
- 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権
裁量免責も受けられず、免責不許可となった場合の対処法
万が一免責不許可になってしまった場合には、次の対処法を採ります。
どちらの方法を採るにしても、自己破産に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
即時抗告をおこなう
免責が不許可になった場合、その決定に対して異議申立て(「即時抗告」といいます)ができます。
免責不許可となった場合には、その決定が裁判所から破産者に送達されます(破産法第252条4項)。
なお、即時抗告をするには、その決定が送達された日の翌日から1週間以内に行わなければいけませんので、注意が必要です。
ただし、明らかな免責不許可事由がある場合は、即時抗告しても決定が覆らない可能性が高いです。その場合には個人再生を選択します。
個人再生の手続をする
免責が許可されなかった場合には、免責不許可事由の規定のない個人再生を検討します。
ただし、個人再生は基本的に減額された借金を原則3年間、場合によっては5年間で返済していく手続なので、返済できるだけの収入がなければ個人再生をすることもできません。
アディーレなら自己破産や個人再生のご相談は何度でも無料です。
「免責不許可事由に該当するか不安…」という方はお気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。