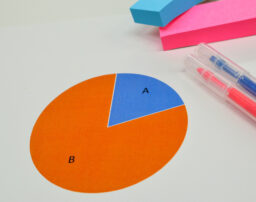飲酒運転の厳罰化が叫ばれて久しい今日でも、飲酒運転は後を絶ちません。
2021年における、車両等の道路交通法違反の取締り件数554万6115件のうち、飲酒運転(酒酔い・酒気帯び運転)は1万9801件に上りました。
さらに、2021年における、飲酒運転による交通事故発生件数は2198件で、そのうち死亡した方は152人でした(死亡事故率は約6.9%)。
飲酒していない場合に比べ、死亡事故率は約9.1倍も高く、飲酒運転は重大事故につながりかねないとても危険な行為であることがよく分かります。
アルコールはお酒に強い・弱いにかかわらず、情報処理能力、判断力、注意力の低下を招きます。
飲酒の上で運転すると、発見・反応・操作が遅れて重大な交通事故を引き起こしかねません。
飲酒運転は犯罪ですので、飲酒運転をしたら刑事上重い処罰を受けたり、行政上も免許取消処分を受けるなどの不利益がありますので、絶対にしてはいけません。
今回の記事では、次の内容についてご説明します。
- 「飲酒運転」の内容
- 飲酒運転の罰則・罰金
- 飲酒運転と自動車保険の補償
参照:令和4年版交通安全白書 (cao.go.jp)|内閣府
参照:飲酒運転による交通事故件数の推移|警察庁
参照:令和3年における交通事故の発生状況等について12頁|警察庁
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
飲酒運転とは?
飲酒運転とは、お酒を飲みアルコールが身体に残っている状態で運転をする行為です。
アルコールには、たとえ少量でも判断能力を低下させ、反応を鈍くさせる力があります。
そのため、アルコール影響下では、気が大きくなる、ブレーキを踏むタイミングが遅くなる、スピードを出しすぎる、集中力が低下するなどといった運転するのに不適切な症状が起きます。
「飲酒運転」は、道路交通法上、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つが定義されています。
まずはこの2つの違いをお伝えします。
(1)酒気帯び運転
道路交通法65条1項は、次のように規定しています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
引用:道路交通法65条1項
簡単に言うと、お酒を飲んで運転してはいけないということです。
自動車を運転する行為だけでなく、自転車に乗る行為も含まれます。
どのような状態だと「酒気帯び運転」として罰せられるか(道路交通法117条の2の2第3号)というと、道路交通法施行令44条の3で次のように規定されています。
法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする
引用:道路交通法施行令44条の3
つまり、次のいずれかに該当する行為を酒気帯び運転といいます。
| 血液 | 1mLにつき0.3mg | 以上のアルコールを保有する状態で運転する行為 |
| 呼気 | 1Lにつき0.15mg |
個人のアルコール分解速度によっても異なるため、どの程度お酒を飲むと基準値を超えるのか、お酒を飲んだ後どのくらい時間をおけばいいのかは一概にいえません。
「私はアルコールに強いから大丈夫」「私はお酒を飲んでも普段と変わらないから大丈夫」と思わずに、お酒を飲むなら車を運転しないことを徹底してください。
「仮眠を取ったからお酒はもう抜けただろう」と思って運転をして飲酒検問にあい、呼気から基準値以上のアルコールが検出される方は少なくありません。
お酒を飲んだ当日に運転しないのはもちろん、翌朝車を運転する際には、前日の夜にお酒を飲まないようにすることが大切です。
呼気検査を拒否したらどうなりますか?
警察による呼気検査を拒否した場合、3月以下の懲役(※)又は50万円以下の罰金を科される可能性があります(道路交通法118条の2)。
それなら、酒気帯び運転の方が刑罰は重いから、あくまでも拒否して酒気帯び運転は隠した方が罪は軽くなりませんか?
かたくなに呼気検査を拒否したら、その場で警察に現行犯人逮捕される可能性があります。
それでも呼気検査を拒否した場合、最終的には裁判所の発布する令状をもって「強制採血」される可能性がありますので、酒気帯びの事実を隠し通すことはできません。
そうなると刑が重くなるだけですので、呼気検査が任意で行われているうちに応じる方が良いですよ。
※2022年6月に懲役と禁錮を廃止し「拘禁刑」に一本化する改正刑法が成立しました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。
(2)酒酔い運転
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で運転することを指します。
蛇行運転や逆走など冷静な判断力を欠いた人は何をするか分かりませんので、酒酔い運転はとても危険な行為です。
後でご説明するとおり、「酒酔い運転」は「酒気帯び運転」よりも、刑事上も行政上も厳しい処分を受けます。
正常な運転ができるかどうかは次のような基準で判断されます。
- 直立できるか
- まっすぐに歩行できるかどうか
- ろれつが回っているか、支離滅裂な内容になっていないか
- 会話を正しく聞き取ることができるか など
この場合は、血液中や呼気中にどの程度のアルコールが残っているかという基準は関係ありません。
ですから、ものすごくアルコールに弱くて、一口飲んだだけでふらふらになってしまう、という方だと「酒気帯び運転」には当たらないけれど「酒酔い運転」に当たるということもあるのです。
飲酒運転の罰則・罰金
飲酒運転の罰則についてご説明します。
道路交通法上、飲酒運転に関しては、次のような罰則が設けられています。
(1)運転者への罰則・罰金
運転手への刑事罰・行政処分は次の表のとおりです。
| 刑事罰 | 違反点数 | 行政処分 | |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取消し 及び 欠格期間3年 |
| 酒気帯び運転 (呼気1L中のアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満) | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 | 13点 | 免停90日 |
| 酒気帯び運転 (呼気1L中のアルコール濃度0.25mg以上) | 25点 | 免許取消し 及び 欠格期間2年 |
参照:飲酒運転の罰則等|警視庁
酒気帯び運転の初犯で、他の違反や被害者がいなければ20万~40万円程度の罰金で済むケースが多いでしょう。
罰金を科される場合には、通常は略式裁判(公開の法廷ではなく裁判官が書面だけを見て審理をする裁判手続)で済みますから、通常の裁判に比べて負担は小さいです。
他方、酒酔い運転はそれより重く、初犯であっても50万円以上の罰金が科されることが多いです。さらに、案件によっては罰金で済まず、公判請求をされて懲役刑を科される可能性もあります。
通常裁判となれば、判決が出るまで時間もかかりますし、精神的な負担は略式裁判よりも重くなります。
(2)車両提供者への罰則・罰金
飲酒運転が発覚した際には、運転者以外の周囲の責任も問われる可能性があります。
まず、飲酒運転をする可能性のある人に車を貸した人(車両提供者)には、次のとおり、処罰される可能性があります(※酒気帯び運転か酒酔い運転かは運転手を基準に考えます)。
| 刑事罰 | |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
(3)酒類提供者及び車両同乗者への罰則・罰金
お店で「ドライバーの人にアルコールは提供しておりません」などというポスターを見たことはありませんか?
もしもドライバーに飲酒運転をさせてしまうと、次のとおり処罰される可能性があります。
| 刑事罰 | |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |
飲酒運転だと知りながらその車に同乗した場合にも同様の処分が科される可能性があります。
ドライバーに酒類を提供したり、飲酒運転と知りながら車に同乗した方が運転免許を保有している場合、運転者の処分基準に応じて行政処分を受けます。
自分が飲酒運転をしていなくても免許が取り消されることもありますからくれぐれも飲酒運転には関わらないように注意してください!
このように飲酒運転で逮捕されると、周囲の人も捜査に応じなければならず、場合によっては仕事に支障が出る可能性があります。周囲に迷惑がかかるとしっかりと認識して、飲酒運転をしないようにしてください。
(4)飲酒運転中に死傷事故を起こした場合の刑法による罰則・罰金
飲酒運転中に死傷事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪あるいは過失運転致死傷罪が適用される場合があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条、5条)。これらの犯罪の罰則は次の表のとおりです。
| 成立する犯罪 | 刑事罰 |
|---|---|
| 危険運転致死 | 1年以上の有期懲役 |
| 危険運転致傷 | 15年以下の懲役 |
| 過失運転致死傷 | 7年以下の懲役若しくは禁錮 又は 100万円以下の罰金 (※ただし、ケガが軽い等の事情があれば起訴猶予の可能性あり) |
人身事故を起こした場合にアルコールを摂取した事実を隠そうとすると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として、12年以下の懲役に処せられることもあります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条)。
飲酒運転事故における自動車保険の補償について
最後に、飲酒運転事故の加害者、あるいは被害者となった場合、保険金が受け取れるのか解説します。
(1)飲酒運転中に事故を起こした又は加害者となった場合
一般的な保険契約において、飲酒運転は保険金の支払われない事由(免責事由)に該当します。
お酒を飲めば事故を起こす可能性が高いのに運転したのだから保険会社としては責任を持てないということです。
そのため、飲酒運転中に事故を起こした場合、運転者自身の死亡補償や治療費、車への損害に保険金は支払われないのが通常です。
もっとも、保険制度における被害者救済の観点から、被害者の損害補償は有効とされるため、被害者に対しては保険金が支払われます。
注意をしたいのは、相手の方から接触してきたように思える場合であっても、飲酒運転をしていたことで加害者と扱われてしまう可能性が高いことです。
交通事故では双方の運転手にどの程度の不注意があったかを割り出すのですが(過失相殺)、酒気帯び運転であれば「著しい過失」、酒酔い運転であれば「重過失」があったとして扱われ、飲酒運転をした方の責任が5~20%重くなる傾向にあります。
ただし、前日飲んだお酒が残っていた場合のように酒気帯び運転に該当しても、正常な運転ができていれば、アルコールが残っていても考慮されないケースもあります。
(2)飲酒運転した車両の被害者となった場合
加害者が飲酒運転をしていれば、被害者側に過失があっても、加害者の過失が大きくなる分だけ相手方の保険会社から受け取れる金額が増える可能性があります。
加害者が飲酒運転をしていたからといって、自身の加入している保険に影響はありません。
そのため、相手方の保険だけでなく、自分が加入している任意保険の「人身傷害保険」も使うことができます。
人身傷害保険は、ノーカウント事故として扱われるため、保険の等級が下がる恐れもありません。もっとも、生じた損害の金額を超えて加害者からの賠償金と人身傷害保険の保険金を受け取ることはできないため、どちらを受け取るか検討しましょう。
判断に迷う場合には、保険約款を持参して、弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、「酒酔い運転」が法定刑が重く、基本的には罰金も高額になる
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 「飲酒運転」には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」がある。
- 「酒気帯び運転」とは、血液1mLあたり0.3mg以上又は呼気1Lあたり0.15mg以上のアルコールを保有した状態で運転すること。法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 初犯で他の違反がない場合には、20万~40万円程度の罰金で済むことが多い。
- 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態のことを指し、身体のアルコール保有量の基準はない。直立できるか、まっすぐ歩行できるかなどの基準で判断される。
- 「酒酔い運転」の法定刑は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。初犯で他の違反がない場合でも50万円以上の罰金になることが多い。場合によっては初犯であっても公判請求をされて懲役刑となる可能性もある。
- 「飲酒運転」に関しては、酒類提供罪や同乗罪もあり、運転手と同様に懲役・罰金の刑罰を科されたり、行政処分を受ける可能性がある。
- 飲酒運転の上、交通事故を起こして死傷結果を招いた場合には、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などに問われ、さらに重い処罰を受ける可能性がある。特に、危険運転致死傷罪には罰金刑がない。
飲酒運転に関して、近年厳罰化が進んでいます。特に飲酒運転により人身事故を起こした場合には、初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
もしあなたが飲酒運転の車両に接触されてしまったならば、加害者の加入している保険会社と示談交渉を行っていく必要があります。
交通事故の被害にあい、加害者が飲酒運転だったという方で、保険会社への対応にお困りの方はアディーレ法律事務所へご相談ください。