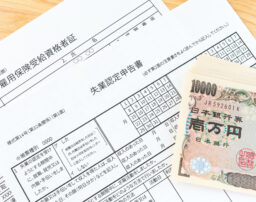「給与からいろんな保険料が引かれているけど、社会保険って何だろう?」
就職・転職する際、「社会保険」という言葉を耳にされたことがあるかもしれません。社会保険とは、国民の生活を保障するために国が設けた、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険という5種類の公的な保険制度の総称です。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 社会保険とは何か
- 社会保険に加入するメリット
- 社会保険の加入手続き
社会保険制度の内容は、年々更新されていくので、最新の情報をチェックするようにしましょう。今回ご紹介するのは、2021年12月時点の情報です。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
社会保険とは
「社会保険」とは、国民の生活を保障するために国が設けた公的な保険制度です。
広く「社会保険」というと次の公的な5つの保険制度を指します。
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
このうち、労災保険は雇い主が保険料を全額負担しますが、それ以外のものは雇い主と従業員がそれぞれ保険料を負担します。
ケガをしたときや定年退職をしたときにも、一定の場合には収入を得られるのが社会保険のメリットです。
これらの5つの社会保険についてご説明します。
(1)医療保険
医療保険とは、医療費の一部を負担してくれるものです。
医療保険に加入していると、病院にかかったときなどに支払う医療費の一部が医療保険から出されます。
これにより、窓口で支払わなければならないお金(自己負担額)が低く抑えられます。
日本では国民全てが公的な医療保険に加入しなければならないという「国民皆保険制度」が採られています。
このため、私たち国民は必ず何らかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
サラリーマンなどが加入する「健康保険」、自営業者などが加入する「国民健康保険」が公的な医療保険の代表例です。
そのほか船員が加入する「船員保険」、公務員が加入する「共済組合」があります。
医療費の自己負担額は次のとおりです。
| 一般・低所得者 | 現役並所得者 | |
|---|---|---|
| 75歳~ | 1割 | 3割 |
| 70~74歳 | 2割 | |
| 6~69歳 | 3割 | |
| 6歳(義務教育就学前)未満 | 2割 | — |
(2)年金保険
年金保険とは、国が運営している年金制度であり、老齢になった時や障害を負った時などに年金として一定額の給付を受けることができるものです。
公的な年金保険には、「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。
年金保険についても、国民全てが公的な年金保険制度に加入しなければならないという「国民皆年金」の制度がとられているので、私たち国民は何らかの公的な年金保険に加入しなければなりません。
なお、かつては公務員や私立学校教職員を対象とした「共済年金」がありましたが、2015年10月に共済年金は厚生年金に統合されました。
個人事業主やフリーランスの方は、国民年金に加入することとされており、厚生年金には加入できません。
これに対して、会社勤めの方は、原則として厚生年金に加入することとされています。
2020年6月5日に年金改革関連法が公布されたことで、パート・アルバイトの方でも厚生年金に加入できる方が段階的に増えていく予定です。
参考:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
参考:令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|日本年金機構
(3)介護保険
介護保険とは、介護を必要とする人が少しの負担で介護サービスを受けるための保険制度です。
たとえば、介護保険を利用して次のようなサービスを受けることができます。
- 介護士による訪問介護サービス
- 介護施設に入所するサービス
- 病院などでのリハビリのサービス
40歳以上になると介護保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。
介護保険料は、40~64歳までは健康保険料と一緒に支払い、65歳以上の場合には原則として年金から天引きされる仕組みです。
介護保険の給付は、次のような流れで受けることができます。
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請をして、要介護認定(要支援認定)を受ける。
- ケアマネジャーに依頼して、ケアプランを作成してもらう。
- 介護サービスを提供する事業者に、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいて介護サービスを利用し始める。
介護保険を利用すると、一部のサービスを除き、サービス利用金額のうち基本的に1割を負担します。
自己負担割合は、所得に応じて3割まで増えることがあります。
参考:介護保険制度について(40歳になられた方へ)|厚生労働省
参考:令和3年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります|厚生労働省
(4)雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合、育児休業をした場合などに、一定額が給付されるものです。
また、失業中・在職中の職業訓練などの費用も雇用保険から給付されます。
具体的には、失業給付金や教育訓練給付金などを受けることができます。
雇用保険に加入するための条件は、原則として次の3つです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 昼間学生でないこと
正社員に限らず、パート・アルバイトであっても条件を満たせば意思にかかわらず雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険について、詳しくは次のページもご覧ください。
(5)労災保険
労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中にケガや病気などをしたときなどに一定額の給付を受けることができる保険です。
労災保険には、例えば、次のようなものがあります。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)年金
- 障害(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 二次健康診断等給付
このうち、休業(補償)給付とは、従業員が仕事中や通勤中に負ったケガや病気が原因で働けず、賃金を受け取れない場合に支給されるものです。
労災保険の休業補償について、詳しくは次のページをご覧ください。
一部の事業所を除き、正社員に限らず、パートやアルバイトを一人でも雇用すれば、事業主は、労災保険に加入する義務があります。
2016年10月から社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象が拡大
2016年10月1日から社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用範囲が拡大されました。
従来は、厚生年金保険・健康保険に加入するためには、「週30時間以上働くこと」という絞りがかけられていました。
しかし、適用範囲の拡大によって、原則として次の5つの条件をすべて満たす場合には、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となったのです。
- 従業員規模501人以上の会社で働いていること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 月額の所定内賃金(※)が8万8000円以上であること
※ボーナス、残業代、通勤手当などを除く - 1年以上雇用される見込みであること
- 昼間学生ではないこと
さらに、2017年4月1日から従業員規模500人以下の企業で働く方であっても、労使間で合意すれば、会社単位で社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入できるようになりました(※)。
※個々の労働者が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入するためには、上記2~5の条件を満たす必要があります。
2022年10月1日からは、上記1の条件が緩和され、従業員規模101人以上の会社で働いていることが条件となるとともに、上記4の条件も緩和され、2ヶ月を超えて使用される見込みが条件となります。
2024年10月1日からは、上記の1の条件が更に緩和され、従業員規模51人以上の会社で働いていることが条件となります。
参考:令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|日本年金機構
パート・アルバイトの社会保険(厚生年金保険・健康保険)について
パート・アルバイトの方が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することを義務付けられるのは次の2つの条件を満たす場合です。
- 週の所定労働時間が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上
- 1ヶ月の所定労働日数が一般社員(常用雇用者)の4分の3以上
たとえば、一般社員の週の労働時間が40時間、月の所定労働日数が20日である場合には、1週間に30時間以上、1ヶ月に15日以上働くパート・アルバイトが社会保険に加入する必要があります。
もっとも、この条件にあてはまらなくとも、すでにご説明したとおり、2022年10月1日以降、従業員規模が101人以上の会社(2024年10月1日以降は従業員規模が51人以上の会社)であれば、一定のパート・アルバイトの方でも社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しなければならなくなりました。
この場合には、すでにご説明したとおり、次の条件を満たす必要があります。
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 月額の所定内賃金(※)が8万8000円以上であること
※ボーナス、残業代、通勤手当などを除く - 2ヶ月を超えて雇用される見込みであること
- 昼間学生ではないこと
参考:パート・アルバイトの皆さんへ社会保険の加入対象が広がっています。|政府広報オンライン
社会保険に加入するメリット

社会保険に加入するメリットって何だろう?いつも高い保険料を給料から天引きされているけれど……。
例えば老後にもらえる年金が増えたり、障害を負った時にもらえる年金が増えたりするなどのメリットがありますよ!
何のために社会保険があるのかわからないと、高い保険料を給料から天引きされていくことに抵抗を感じてしまいますよね。
社会保険は万が一の事態が生じたときに私たちを支えてくれる保険です。
ここでは、年金保険と健康保険について、加入するメリットをご説明します。
(1)老後にもらえる年金が増える
厚生年金に加入すると、老後にもらえる年金(老齢厚生年金)が増えます。
具体的には、全国民共通の基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができるようになります。
支給される老齢厚生年金の内訳の一つに「報酬比例部分」があります。
これは、在職中の給料の額や厚生年金に加入していた期間に応じて、支給される年金額が増えるというものです。
たとえば、厚生年金に40年間加入し毎月8000円の保険料を納めると、将来受け取る年金の金額は1万9000円増えます。
日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すれば、将来受け取れる年金の見込額を試算することができます。
(2)障害年金と遺族年金の支給額が増える
厚生年金の加入期間中に一定の障害がある状態になると、障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。
また、万一ご本人が亡くなった場合にも、ご本人の遺族は遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金を受け取ることができます。
このように、障害年金や遺族年金の支給額が増えるというメリットがあります。
(3)ケガや病気、出産の際の給付が充実している
健康保険に加入していれば、ケガや病気、出産などで仕事を休まなければならない場合でも、傷病手当金や出産手当金として賃金の3分の2程度の給付を受け取ることが可能です。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会 協会けんぽ
(4)保険料の半分を会社が負担してくれる
厚生年金や健康保険では保険料を会社と従業員本人が半分ずつ負担します。
これに対して、国民年金や国民健康保険では被保険者本人が保険料を全額負担しなければなりません。
社会保険に加入する際の手続きについて
社会保険に加入するために、何か自分でしなければならないことはあるのかな?
社会保険に加入するための手続きは、基本的には勤務先の会社で行ってくれます。
しかし、国民健康保険の喪失届の提出など一部自分で行わなければならないこともあります。
このことについて、次の3つの場合に分けてご説明します。
- 国民年金に加入している場合
- 国民健康保険に加入している場合
- 配偶者の健康保険に加入している場合
参考:パート・アルバイトの皆さんへ社会保険の加入対象が広がっています。|政府広報オンライン
(1)国民年金に加入している場合
勤務先の会社にて、厚生年金保険の加入手続きを行ってもらうようにしましょう。
国民年金から厚生年金への切り替え手続きに関して、ご本人が市区町村役場の窓口で行わなければならない手続きはありません。
(2)国民健康保険に加入している場合
勤務先の会社にて、健康保険の加入手続きを行ってもらうようにしましょう。
ただし、国民健康保険の資格喪失の届け出は自身で行う必要があります。
手続きには、次の3つの書類が必要となります。
詳しくはお住まいの市区町村の窓口でお尋ねください。
- 新しく加入した会社の健康保険証
- 不要となった国民健康保険証
- マイナンバー(個人番号)の確認できる書類・本人確認書類(運転免許証など)
窓口に直接行くのが難しい場合には、郵送で手続きを進めることもできます。
(3)配偶者の健康保険に加入している場合
勤務先の会社にて、健康保険の加入手続きを行ってもらうようにしましょう。
ただし、配偶者の健康保険の資格喪失の届け出を配偶者の勤務先を通じて行う必要があるため、配偶者の健康保険の資格喪失の届け出を行ってもらうように配偶者の勤務先に申し出ましょう。
【まとめ】社会保険は国民の生活を保障するための公的保険制度
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 社会保険とは、国民の生活を保障するために国が設けた公的な保険制度。
社会保険には、次の5つの保険制度がある。- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 医療保険に加入していると、病院にかかったときなどに支払う医療費の一部が医療保険から出され、自己負担額が低く抑えられる。
- 年金保険に加入していると、老齢になった時や障害を負った時などに年金として一定額の給付を受けることができる。
- 介護保険に加入していると、介護が必要となったときに、少しの負担で介護サービスを受けることができる。
- 雇用保険に加入していると、失業したときや育児休業をしたときなどに、一定額の給付を受けることができる。
- 労災保険に加入していると、仕事中や通勤中にケガや病気などをしたときなどに一定額の給付を受けることができる。
- 2016年10月から社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象が拡大した。
これにより、パート・アルバイトの方も含めて、従来より多くの人が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することが義務付けられるようになった。 - 社会保険に加入するメリットには、次のものがある。
- 老後にもらえる年金が増える
- 障害年金と遺族年金の支給額が増える
- ケガや病気、出産の際の給付が充実している
- 保険料の半分を会社が負担してくれる
- 社会保険に加入するための手続きは、基本的には勤務先の会社で行ってくれる。
もっとも、国民健康保険の喪失届の提出など、一部自分で行わなければならないものもある。
社会保険のことは、ぼんやりと分かっているつもりでも詳しいことはよく分からないという方も少なくありません。
社会保険には何のために加入しておりどんなメリットがあるのかということを知っておけば、いざという時にしっかりと活用できて安心ですよね。
社会保険について分からないことがあれば、市区町村役場の窓口など公的な窓口に相談するようにしましょう。
年金保険についての相談窓口は、次のページをご覧ください。
雇用保険についての相談は、最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
ハローワークの所在地情報については、次のページをご覧ください。
参考:ハローワーク|厚生労働省
労災保険についての相談窓口は、次のページをご覧ください。
参考:労災保険|厚生労働省
医療保険や介護保険については、最寄りの市区町村役場の窓口などにお問い合わせください。