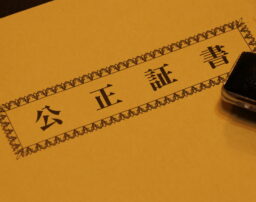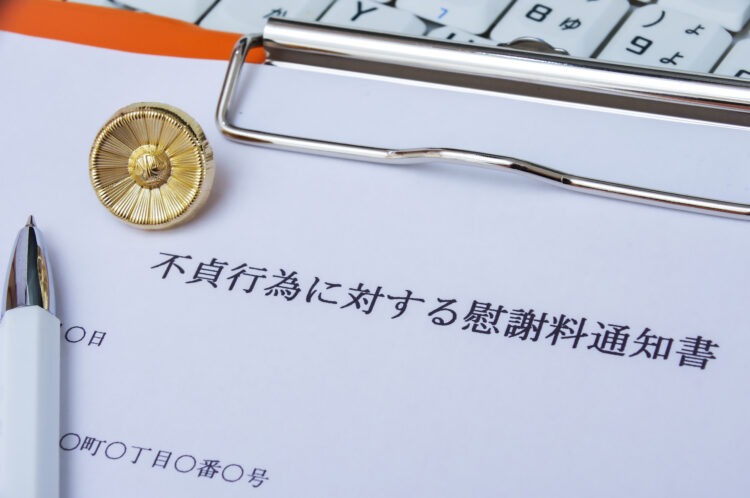離婚の際に子どもの養育費を取り決めたものの、その後事情が変化し、決めてあった養育費では不足してしまうこともあるかと思います。
いったん養育費を決めた場合でも、話し合いで増額できる場合があります。また事前に予測できなかった事情の変化がある場合など、一定の条件を満たせば、調停で、養育費の増額を求めることができる可能性があります。
今回の記事では次のことについて弁護士が解説します。
- 養育費を増額できる条件
- 養育費増額調停の概要
- 養育費はどれくらい増額できるのか
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
養育費を増額できる条件とは
一度養育費の額を合意で決めた以上は、その合意には法的な拘束力があり、一方の当事者側の事情で増減を認めることはできないのが原則です。
もっとも、支払う側ともらう側の双方の合意さえあれば、当事者同士の話し合いによって養育費を増額することも可能です。
話し合いで合意できず、それでも増額を求めたい場合には養育費増額調停を申立てることになります。調停では、「合意の前提になっていた事情自体に、合意時には予測できなかった変化があった場合には、合意の変更が認められる」という考え方で進められることが多いです(事情変更の原則)。
(調停で話し合って双方が合意するのであれば、特にこのような養育費増額の条件はありません)
では、どのような場合に、増額が認められるような事情変更があったといえるのでしょうか。
(1)事情変更の原則
裁判所によって養育費の増額請求が認められるのは、原則として養育費に関する合意の後に、合意時点では予期せぬ出来事があり、事情が変わった場合です。
これは、合意の時点で予測できないような事情の変更であれば、そもそも合意としての拘束力で縛ることは酷であるとされる考え方によるものです。
「事情の変更」があったといえるかについての主な判断要素は次の3つです。
- 事情の変化の重大性
- 事情の変化の予測可能性
- 金額を変更する必要性
養育費の増額が認められるのは例えば次のようなケースです。
- 支払義務者(非監護親:子どもと離れて暮らす親)が会社で昇進・昇格し収入が上がった
- 子どもが難病にかかって入院し、多額の医療費がかかるようになった
- 勤務先の倒産やリストラによって親権者が失業し、収入が激減した
- 親権者が重いケガや病気で入院・長期療養が必要となり、仕事ができなくなった
(2)事情変更があった場合
では、このような事情変更があった場合、どのような手段で養育費の増額を求めることになるのでしょうか。
まずは、非監護親に電話やメールなどで連絡を取り、話し合いの場を設けて養育費を増額してほしい旨を伝えてみましょう。
日頃から面会交流などで子どもと交流のある非監護親であれば、事情の変更についても既に把握しており、増額について前向きに考えてくれる可能性もあります。
話し合いで合意できれば、書面を作成しておくことをおすすめします。
そして、養育費増額についての合意内容を書面に残す場合、その書面は強制執行認諾文言を記載した公正証書にしておくのが良いでしょう。
強制執行認諾文言を記載した公正証書にしておくことで、支払いが遅れたときの強制執行がスムーズになるという利点があります。
公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
話し合いができなければ養育費増額請求調停へ

話し合いで非監護権者との間で養育費増額の合意ができればそれに越したことはありません。
しかし現実には、非監護親が話し合いに応じない場合もあります。
その場合には、調停に備えて内容証明郵便で養育費の増額請求書を送っておきましょう。
内容証明郵便とは、記載された内容・発送日・受け取った日付などを郵便局側で証明してもらえるサービスです。
内容証明郵便で養育費の増額請求書を送っておけば、話し合いや支払いを、非監護親から調停前に拒否されたことを証明する証拠にできる可能性があります。
内容証明で養育費の増額請求を送っても拒否される場合には、次に家庭裁判所に養育費増額請求調停を申立てることになります。
調停では、調停委員を介して相手と話し合います。
話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、そのまま審判に移行し、裁判所が増額請求を認めるかどうか、金額はいくらにするかの審判をすることになります。
(1)養育費増額請求調停で必要な書類
養育費増額調停を申立てる際に必要となる書類は次のとおりです。
- 申立書原本及び写し 各1通
- 連絡先等の届出書 1通(書類の送付先や平日日中の連絡先を書いた書類)
- 事情説明書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票や給料明細、確定申告書等の写し)
- 収入印紙 子ども1人につき1200円
- 郵便切手 100円2枚、84円10枚、10円20枚
- 非開示の希望に関する申立書(必要な場合)
必要な収入印紙や郵便切手の金額は、変更になる場合がありますので、次で説明する申立先の家庭裁判所に確認しておくことをおすすめします。
参考:養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て|裁判所 – Courts in Japan
(2)養育費増額請求調停の申立先
養育費増額請求調停を申立てる場合、自分が住んでいる地域の裁判所ではなく、相手方(非監護親)の居住する地域を管轄する家庭裁判所に申立てることになるので、注意が必要です。
もっとも、相手方との合意があれば、ほかの地域の家庭裁判所に申立てることも可能です。
(3)養育費増額調停で何が行われるか
養育費増額調停で何が行われるかについて見てみましょう。
ひょっとすると既に離婚の際に離婚調停を経験しているかも知れません。
この離婚調停と手続きはほぼ変わりません。
まずは、当事者双方が指定された期日に裁判所に出向きます。
調停委員は、当事者双方を部屋へ交互に呼び出し、なるべく当事者双方が対面することがないよう配慮しながらそれぞれの事情や意見を聞き、養育費の増額を認めるか、認めるとすればどれくらいの金額が妥当かを検討します。
こうして、調停委員を介して相手方と話し合いを行うことで合意を目指し、合意ができれば裁判所で調停調書が作成されることになります。
(4)調停不成立なら養育費増額審判へ
調停での話し合いによっても合意できなければ、調停不成立となり、自動的に養育費増額審判へ移行することになります。
ここでは、裁判所が増額を認めるかどうか、認めるとすればどれくらいの金額が妥当かを判断します。
裁判所が養育費の金額の判断をするにあたり「養育費の算定表」が用いられます。
「養育費の算定表」とは家庭裁判所が公表している養育費の相場をまとめた表で、協議離婚、調停離婚、裁判離婚する場合にもよく用いられているものです。
参考:養育費・婚姻費用算定表|裁判所 – Courts in Japan
裁判所が養育費の増額について、妥当と判断した場合には、養育費増額調停を申立てた月にさかのぼって養育費が増額される旨の審判がなされます。
ただし、審判の内容に不服がある場合、当事者は不服申立て(即時抗告)をして、高等裁判所で更に争うことができます(この場合、審判手続きから裁判手続きに移行することになります)。
養育費はどれくらい増額できる?
養育費増額請求調停を申立てることで、どれくらいの増額が認められるのかは気になるところです。増額が認められるためには、その金額が必要な証拠を示し、説得力ある主張をすることがポイントになります。
(1)算定表に基づいて妥当な金額を算出するのが原則
増額後の妥当な養育費は、基本的に「養育費の算定表」に基づいて金額が算出されることになります。
支払義務者(非監護親)の収入が上がっている場合は、算定表を使って算出した金額も以前に合意した金額よりも上がっている可能性が高いので、調停や審判でも増額請求が認められやすい傾向があります。
次のサイトで、養育費の目安を簡単に確認できますのでぜひお試しください。
(2)増額を認められやすくするには
例えば、高額な学費や医療費が必要になったという事情は、算定表の数字には現れないものです。
ですから、非監護親が支払う養育費に学費の分を上乗せしてもらいたいときは、入試要項や入学案内など学費の金額がわかる資料を用意すると良いでしょう。
子どもの重篤な病気などを理由に高額な医療費が必要になる場合でも、医師の診断書や診療明細書などかかる医療費がわかる資料を用意することをおすすめします。
(3)養育費増額請求に関する事例
養育費増額請求は個別の事情が考慮されるため、ケースごとに判断されることになります。
裁判例の事情に近いものをぜひ参考にしてみてください。
高等裁判所における養育費の増額請求に関する事例が2つあるので、ここで紹介します。
(3-1)支払終期の延期が認められた事例(東京高裁決定平成29年11月9日)
例えば離婚の際の養育費については、子どもが20歳になるまでの養育費ということで合意することが多いようです。
しかし、大学へ進学した場合、20歳を超えても学費が必要となってきます。
この事例は、そのような場合に支払終期を延長することを認める内容となっています。
概要は次のとおりです。
- 2008年に裁判離婚し、子どもが20歳になるまでひと月5万円の養育費を支払う取り決めを行う。
- その後父親側から減額請求調停の申立てがあり成立したが、2014年に子どもが私立大学の付属高校に進学したことから母親が養育費の終期を22歳に達した後の3月までに延期する調停を申立てた。
その際に養育費を5万5000円に増額することは認められたが、支払終期の延期は認められなかった。
- 2015年子どもが私立大学に進学し、学納金の支払いと養育費の終期の延期を家庭裁判所に申立てたが却下され、東京高裁に抗告をした。
- 東京高裁は2014年に養育費の増額がなされているので学納金の負担までは認められないとしながらも、支払終期については22歳に達した後の3月までとすることを認めた。
(3-2)医学部進学に伴い養育費増額が認められた事例(大阪高裁決定平成29年12月15日)
学費といっても、子どもが公立の学校に通うか、私立の学校に通うか、また大学であれば学部によっても異なるため、必ずしも離婚時に予測することは容易ではありません。
この事例は、私立医大に通う子どもの学費が足りないことを理由とした養育費の増額請求のケースです。
概要は次のとおりです。
- 2012年に父母が離婚したときに
「子ども1人につき500万円の一時金を支払うとともに、子どもたちが医学系を含む大学を卒業するまで1人あたり毎月25万円を支払う」
「子どもが私立医学部に進学を希望する場合は父親にその旨を伝え、学費不足分を別途協議する」
と取り決めた。
- そののち原告(子どもの1人)が私立の医学部に進学したが、父親が学費の不足分の支払いを拒否した。
- 原告が父親を相手に養育費増額調停を申立てたが、不成立となり審判に移行。
- 家庭裁判所が6年間で約400万円の支払いを命じたが、双方が不服申立てをした。
- 大阪高裁は離婚時に子どもが医学部へ進むことを想定しており、追加費用を支払う意思もあったため、追加費用を支払う義務を認定。
- 最終的に父親に6年間で合計900万円を支払うことを命じた。
【まとめ】事前に予測できなかった事情の変化等がある場合には、調停で養育費増額請求に成功することも
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 当事者同士が合意すれば、事情に関わらず養育費を増額することは可能
- 合意できれば、強制執行認諾文言を記載した公正証書を作成すると良い
- 養育費の増額請求が認められるのは、原則として養育費に関する合意の後に予期せぬ出来事があり、事情が変わった場合
- 養育費は、基本的に「養育費の算定表」に基づいて妥当な金額が算出される
- 高額な学費や医療費が必要になった場合には、算定表の金額よりも高い金額が認められるケースがあるが、必要になった金額を示す資料が用意できると良い
離婚の際に養育費について取り決めを合意していたとしても、離婚後に合意できれば、いつでも養育費の増額はできます。
また、「事情の変更」が認められれば調停や審判で、養育費増額に成功する可能性があります(※調停では、合意さえできれば事情の変更がなくとも養育費の増額は可能です)。
ただし、事情の変更が認められるためには、事前に予測できなかったなどの条件を満たす必要があります。
養育費を増額してほしいと考えている方は、養育費の増額請求を取り扱う弁護士にご相談ください。