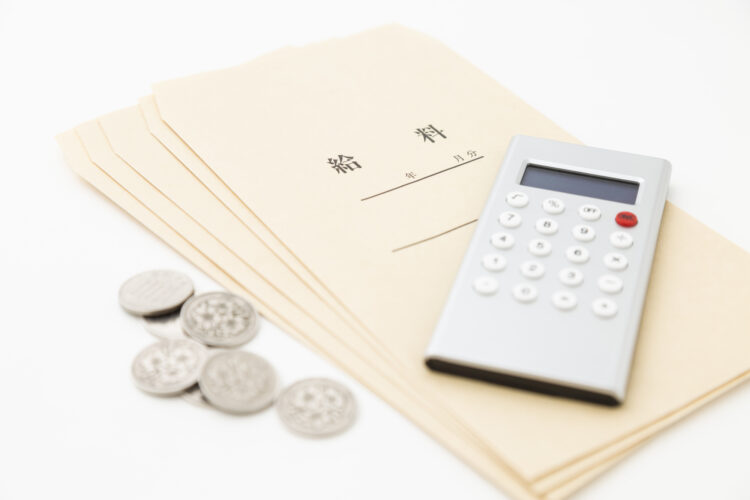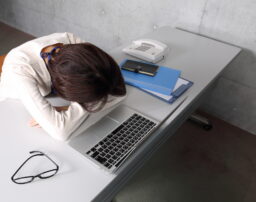「会社は60歳で定年。定年後再雇用を希望しているけれど、会社は再雇用に前向きな返事をしてくれない。定年後再雇用の拒否って許されるのかな?」
定年を迎える日が近づいてくると、その後の雇用がどうなるのかは気になるところですよね。
定年を迎えたのだから、その後は一切雇用し続けてもらうことはできないと考える方もいるかもしれません。
しかし、定年後も再び雇用を継続してもらうための定年後再雇用という制度があります。
定年を65歳未満と定めている会社において、定年後再雇用の拒否や雇い止めは、原則として違法なものとして許されません。
この記事を読んでわかること
- 定年後再雇用とは何か
- 定年後再雇用の拒否や雇い止めが原則として許されないこと
- 定年後再雇用の違法な拒否や雇い止めへの対処法
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
定年後再雇用制度とは何か
定年後再雇用制度とは、定年に達した時点でいったん退職してその直後に引き続き新たに雇用契約を結ぶ、高年齢者の雇用の安定を図るための制度です。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、会社などの事業主が定年を定める場合、定年年齢は60歳以上でなければいけません。
そして、定年を65歳未満に定めている会社は、次のいずれかの措置を取らなければなりません。
- 65歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの「継続雇用制度」の導入
「継続雇用制度」には次の2種類があります。
- 勤務延長制度
- 再雇用制度
勤務延長制度は、定年に達してもそのまま雇用を継続する制度で、労働条件は変わりません。
再雇用制度(定年後再雇用制度)は、定年に達した時点でいったん退職してその直後に引き続き新たに雇用契約を結ぶ制度で、雇用形態、賃金、労働時間、待遇などの労働条件が定年前と変わるのが一般的です。
なお、2021年4月1日以降は、会社は「70歳までの就業機会を確保する努力義務」も負っています。
これは「努力義務」なので努力すればそれで足り、会社が実際に70歳までの就業機会を確保できなかったとしても問題となるわけではありません。
定年後再雇用制度の基本的なルール
定年後再雇用制度があるため、定年を65歳未満に定めている会社は、原則65歳までの再雇用を拒否できないなどの制約を受けます。
ここからは、定年後再雇用制度の基本的なルールについて、詳しくご説明します。
(1)ルール1|会社は原則として再雇用を拒否できない
定年を65歳未満に定め、定年後再雇用制度を採用している会社は、原則として定年後も働き続けることを希望している労働者の再雇用を拒否できません(※)。
これは法的義務であり、努力義務ではありません。
場合によっては、「定年後に再雇用するかどうかは会社の自由だ」と会社が誤解していることもあります。
しかし、定年後再雇用制度を採用している以上、再雇用は義務であるので、直接その旨を会社に申し入れても会社が再雇用を拒否する場合には労働基準監督署などに相談するようにしましょう。
(※)2013年3月以前に、労使協定により再雇用の対象となる高年齢者の選別基準を定めていた会社は、基準の対象者の年齢を2025年3月31日まで段階的に引き上げながら、同基準によって再雇用対象者を選別することができます。
(2)ルール2|会社は原則として「雇い止め」ができない
定年後の再雇用では、1年ごとに雇用契約を更新する有期契約が結ばれるケースなどがあります。
このような場合であっても、定年後再雇用の労働者は、65歳まで契約が更新されることを期待していると考えるのが通常です。
労働者が雇用継続に対して合理的な期待を有している場合には、客観的合理性・社会的相当性を欠く更新拒絶(いわゆる雇い止め)をすることは許されません(労働契約法19条2号)。
このような客観的合理性または社会的相当性を欠く雇い止めは違法・無効とされ、契約が更新されたのと同様の取扱いがなされることとなります。
客観的合理性や社会的相当性を欠く場合とはどのような場合なのでしょうか?
一律には言えず、さまざまな具体的事情を総合的に考慮して、客観的合理性・社会的相当性を欠くかどうかが判断されます。少しでも「おかしいな?」と思ったら、弁護士に相談してみましょう。
定年後再雇用の拒否・雇い止めが認められる2つの例外ケース
次のようなケースに該当する場合には、例外的に会社による定年後再雇用の拒否や雇い止めが認められる可能性があります。
- 合理的な労働条件による再雇用申込みを労働者が拒絶した場合
- 労働者を適法に解雇できるような事情がある場合
(1)例外ケース1|合理的な労働条件による再雇用申込みを労働者が拒絶した場合
会社が、定年後再雇用について合理的な労働条件による再雇用契約を申し込んだにもかかわらず、労働者が再雇用契約の締結を拒絶した場合には、定年後再雇用の雇用契約が成立しないことも認められる可能性があります(東京地裁判決令和元年5月21日・アルパイン事件)。
このように、会社は、必ず労働者の要求する労働条件による定年後再雇用に応じなければならないわけではありません。
(2)例外ケース2|労働者を適法に解雇できるような事情がある場合
会社が労働者を適法に解雇できるような事情がある場合にも、定年後再雇用の拒否等が認められる可能性があります。
会社は、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当であると認められる場合に限り、労働者を解雇することができます(労働契約法16条)。
このように客観的合理的理由・社会的相当性のいずれも満たす場合であれば、定年後再雇用の拒否等が許されることがあります。
正当な解雇と不当解雇との違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。
定年後再雇用の違法な拒否や雇い止めへの対処法
会社が定年後再雇用を違法に拒否したり雇い止めをしたりして、それが違法な解雇・雇い止めにあたる場合には、解雇・雇い止めが無効であることを主張できます。
また、本来働いていれば得られたはずの賃金の支払を請求できることもあります。
会社が定年後再雇用を違法に拒否したなどの場合には、次のような対処法があります。
- 労働基準監督署に相談・申告する
- 会社と交渉したり、労働審判や訴訟などの法的手続きをとる
会社との交渉や労働審判などの法的手続きを自分で行えるか不安です。どうすればいいでしょうか?
弁護士に相談・依頼するという方法があります!
労働トラブルを積極的に扱っている弁護士に相談・依頼すれば、弁護士があなたに代わって会社との交渉を行ってくれたり、労働審判・訴訟における代理人としてあなたに代わって裁判所に主張を伝えたりしてくれます。
これにより、定年後再雇用をめぐるトラブルを解決できる可能性があります。
労働基準監督署と弁護士のどちらに相談すべきかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】定年後再雇用の拒否や雇い止めは違法として許されないことがある
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 定年後再雇用制度とは、定年に達した時点でいったん退職してその直後に引き続き新たに雇用契約を結ぶ、高年齢者の雇用の安定を図るための制度。
- 会社は、法律上、60歳未満を定年と定めることはできない。また、定年を65歳未満に定めている会社は、65歳までの継続雇用制度を導入するなど、65歳までの雇用確保措置を講じなければいけない。
- 定年を65歳未満に定めた会社が定年後再雇用制度を採用している場合には、会社は原則として再雇用を拒否できない。
- 定年後再雇用の違法な拒否や雇い止めへの対処法として、弁護士に相談・依頼して会社と交渉などを行うという方法などがある。
定年後の雇用が安定しないと、安心して働けませんよね。
定年後再雇用の違法な拒否や雇い止めに対しては、弁護士に相談・依頼するなどの対処法があります。
少しでも不安なことがあれば、ためらわずに労働トラブルを扱う弁護士に相談するようにしましょう。