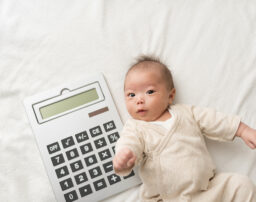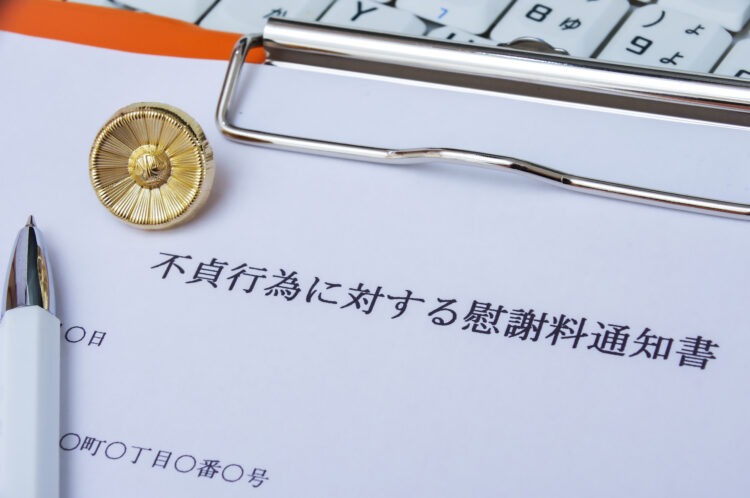「離婚したいが、もめたくない。」
このように円満な離婚を希望する人は多いです。
しかし、夫婦間で離婚条件が折り合わず、険悪な状態になってしまうケースも多くあります。実際、友人や知人から「離婚が大変だった」と聞かれた方も多くいるでしょう。
そのような話を聞くと、「円満離婚なんて難しいのでは?」なんて思われているかもしれません。
しかし、「円満離婚」は、決して難しいことではありません。
「円満離婚」をするためには、離婚をする前の準備をきっちりしておくことが重要です。
この記事を読んでわかること
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
「円満離婚」とは
「円満離婚」とは、夫婦がもめることなく、互いに納得のいく形で離婚を成立させることをいいます。
「円満離婚」をするにあたっては、夫婦でもめないということはもちろん、どちらか一方に不満を残さないということが重要です。なぜなら、どちらか一方に不満が残る形での離婚では、後々トラブルのもとになる可能性があるからです。
例えば、夫が養育費の額に納得していなければ、離婚後、夫が養育費を支払わなくなるなどのトラブルに発展するケースもあります。
離婚後にお互いに禍根を残さないためにも、「円満離婚」が望ましいでしょう。
「離婚」について知っておくべき基礎知識
離婚をする前に、離婚の3つの方法について知っておくとよいでしょう。
離婚には、主に次の3つの方法があります。
- 協議離婚:夫婦間だけの話し合いで離婚条件を決めて離婚すること
- 調停離婚:裁判所で裁判官や調停員を通じて夫婦で話し合い離婚条件を決めて離婚すること
- 裁判離婚:裁判官が離婚の有無や離婚条件を判決して離婚すること
多くの夫婦が「協議離婚」によって離婚しています。
しかし、離婚の話し合いがうまくいかない場合には、協議離婚ではなく、「調停離婚」や「裁判離婚」の方法で離婚することになります。
「裁判離婚」の場合には、夫婦が納得していなくても裁判官が離婚という判断を下せば、離婚が成立してしまいます。互いが納得いかない離婚条件が付されることもあります。
そのため、互いが納得いく形での円満離婚をするためには、話し合いで離婚をする「協議離婚」や「調停離婚」であることが必要です。
なお、裁判所での調停手続には、「円満調停」という調停手続もあります。「円満調停」とは、裁判所を介して、夫婦仲を円満にし、離婚しないように話し合う手続きですので、「円満離婚」とは別物です。
円満離婚をする4つのメリット
円満離婚をするメリットには次の4つがあります。
- 短い期間で離婚できる可能性が高い
- 離婚にかかる費用を抑えられる可能性が高い
- 夫婦が互いに納得のできる離婚条件を決められる
- 夫婦が良好な関係でいられる可能性が高く、子どもへの影響が少ない
順番に説明します。
(1)短い期間で離婚できる可能性が高い
離婚で揉めた場合には、これまで説明した通り、調停や裁判といった方法で離婚することになります。そして、調停や裁判となった場合には、離婚までに1年以上かかるケースも多くあります。
円満離婚の場合には、夫婦間の合意がまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚ができるため、裁判などを通じて離婚する場合に比べて、短い期間で離婚することができます。
(2)離婚にかかる費用が抑えられる
円満離婚の場合には、基本的に離婚にかかる費用はありません(なお、引っ越し費用などは必要となります)。
一方、離婚で揉め裁判になった場合には、裁判所に支払う費用が必要となります。また、裁判となり、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も必要となります。
離婚によって、夫婦それぞれ新たな生活がはじまります。新たな生活のためにお金が必要な人もいるでしょう。少しでも離婚にかかる費用は抑えましょう。
(3)夫婦が互いに納得できる離婚条件を決めやすい
夫婦でもめることなく、話し合いによって、離婚することで、互いに納得のいく離婚条件を決めやすくなります。そのため、離婚後に「もっと養育費をもらうべきだった」「財産分与の方法に納得ができない」など後悔することはあまりありません。
一方、どちらか一方が納得していないまま離婚条件が定めてしまうと、のちに定めたことが実行されない等のリスク(例えば、養育費の不払いや子どもに勝手に会いに来てしまうなど)もあります。
双方にとって納得のできる離婚条件は、後で決めたことがきちんと実行されやいため、後々のトラブル防止の観点からも有用です。
(4)夫婦が良好な関係でいられる可能性が高く、子どもへの影響が少ない
円満離婚の場合には、離婚後も相手と連絡を取り合えるような良好な関係でいられる可能性が高いです。
一方、相手と裁判などで争った末に離婚する場合には、離婚成立後に良好な関係を築くことは難しいといえます。
いくら離婚するからとはいえ、子どもにとっては大切な母であり、父であるということに変わりありません。そのため、離婚後も夫婦がある程度良好な関係を継続している場合には、子どもへの影響も少なくてすむでしょう。
「円満離婚」に向けた2つの心構え
「円満離婚」をしたいのであれば、この2つのことを心構えとしておくことが大事です。
- 離婚条件を妥協するのは禁物
- 離婚条件について、配偶者の意思も尊重する
この2つの心構えをせずに離婚の話し合いに臨んでしまうと、円満離婚が難しくなるばかりか、離婚後に後悔しておそれもあります。
(1)離婚条件を妥協するのは禁物
争いを避けて円満に離婚を成立させたいがために、離婚条件を妥協してしまうのはいけません。
離婚条件の取り決めを曖昧にしたり、納得がいっていないにもかかわらず妥協した取り決めをしてしまうと、後々の紛争の火種になったり、後悔したりする可能性が高いからです。
【具体例】
- 養育費の金額を決めずにいたら、毎月数千円の振込しかない
- 財産分与について十分な話し合いをしなかったため、家財道具や車を相手に持っていかれて、離婚後の生活が困った
- 慰謝料の金額に決めずにいたら、支払いがない
- 面会交流について十分に話合わかったため、子供と会わせてもらえない
特に、財産分与、慰謝料、養育費は、離婚後の生活の原資(お金)ともなりますので、妥協せずに、きっちり決めておかなければなりません。
(2)離婚条件について、配偶者の意思も尊重する
「円満離婚」は、これまで説明したとおり、夫婦が互いに納得をして離婚をすることです。
つまり、円満離婚をするためには、相手にも納得してもらうことが必要ということです。
あなたの思いや希望もわかりますが、お互いが納得のできる離婚をするためには、相手を説得することや相手の意思を尊重することが重要となります。
確かに、離婚に向けた話し合いは、これまで婚姻生活の中で感じていたこと、ためていたことがあふれてきて、感情的になりがちです。
しかし、感情的に自己の思いや希望を相手にぶつけてしまうことで、ささいな争いを生み、円満に解決できるはずのことも出来なくなってしまいます。
あなたの意思だけでなく、配偶者の意思も尊重するということを心にとめておきましょう。
離婚に向けて話し合うべき5つの離婚条件
円満離婚に向けた心構えを知ったところで、円満離婚に向けて何を話し合うべきなのかを知っておきましょう。
円満離婚に向けて話し合うべき主な離婚条件は次の5つです。
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
- 親権、子の戸籍
- 養育費、面会交流
どういった離婚条件があるのかを事前に知っておくことで、どういった準備が必要かを知ることができます。
(1)財産分与
「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算し分配する制度のことをいいます(民法768条1項)。
財産分与の対象となる財産は主に例えば、次のようなものです。
| 【具体例】 | |
|
|
これらの財産は夫婦共同名義になっているものはもちろん、夫婦の片方の名義となっているものも原則、財産分与の対象となります。
離婚の話し合いをする前には、どういった財産をそれぞれ持っているかを整理しておくとよいでしょう。離婚後に新たに財産があることが発覚するとトラブルの元になりかねません。
財産分与についてくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
(2)年金分割
「年金分割」とは、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。
年金分割をするには、原則離婚後2年以内に手続をする必要があります。
離婚時に年金分割の話し合いを忘れてしまうと、離婚後年金分割をしたくても出来ないという事態になってしまうかもしれません。特に、熟年離婚の場合には、年金が離婚後の生活の糧となることが多いと思われますので、しっかり決めておきましょう。
なお、相手の年金の額・加入状況・分割した場合の具体的な年金の金額を知りたい場合は、年金事務所に、「年金分割のための情報提供請求書」を提出して、情報提供を受けることができます。離婚の話し合いの前に請求しておくとよいでしょう。
(3)慰謝料
離婚における「慰謝料」とは、配偶者の行為(例:不倫やDVなど)によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したものです。
離婚で揉めたくないと思うあまり、慰謝料はいらないと主張される方も多くいらっしゃいます。
しかし、配偶者に精神的に傷つけられたまま終わるのでは、離婚後も心に深いキズを残します。離婚を機に心機一転したいと思われるのであれば、慰謝料請求をし、きちんと清算しておくことをおすすめします。
なお、慰謝料を請求する場合には、話合いをする前に証拠を集めておくことをおすすめします。証拠もなく請求すると言い逃れをされてしまうケースもあります。
離婚慰謝料の相場についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(4)親権、子どもの戸籍
未成年の子どもがいる場合、離婚後、必ず父母のどちらかが親権者になります(民法819条)。
親権を得たいのであれば、離婚の話し合いに先立って、養育の実績を作っておき、また、離婚後子どもが育つにふさわしい環境を整えておくようにしましょう。
もし揉めて裁判所が親権を決めるということになれば、養育の実績の有無、子どもが育つにふさわしい環境といえるかなどによって、親権をどちらが持つかを決めることになるからです。
なお、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可(民法791条)」を申立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
親権についてくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
(5)養育費、面会交流
子どもがいる場合、養育費や面会交流についても決める必要があります。
(5-1)養育費
「養育費」とは、衣食住の費用、教育費、医療費などの子どもの養育に必要な費用のこといい、定期的、継続的に支払っていくものです。
養育費の金額は夫婦双方の年収などを加味して、話し合いで決めることが一般的です。離婚の話し合いをする前に、相手の年収額について調べておくとよいでしょう。
養育費についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(5-2)面会交流
「面会交流」とは、子どもと離れて暮らしている父または母が、定期的・継続的に子どもと交流することをいいます。
養育費を支払う側が「養育費を支払うなら子どもに会いたい」と希望することも多く、養育費の金額を決める際に、面会交流の条件も決めるということもあります。
面会交流について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
円満離婚のためにしておきたい2つの準備
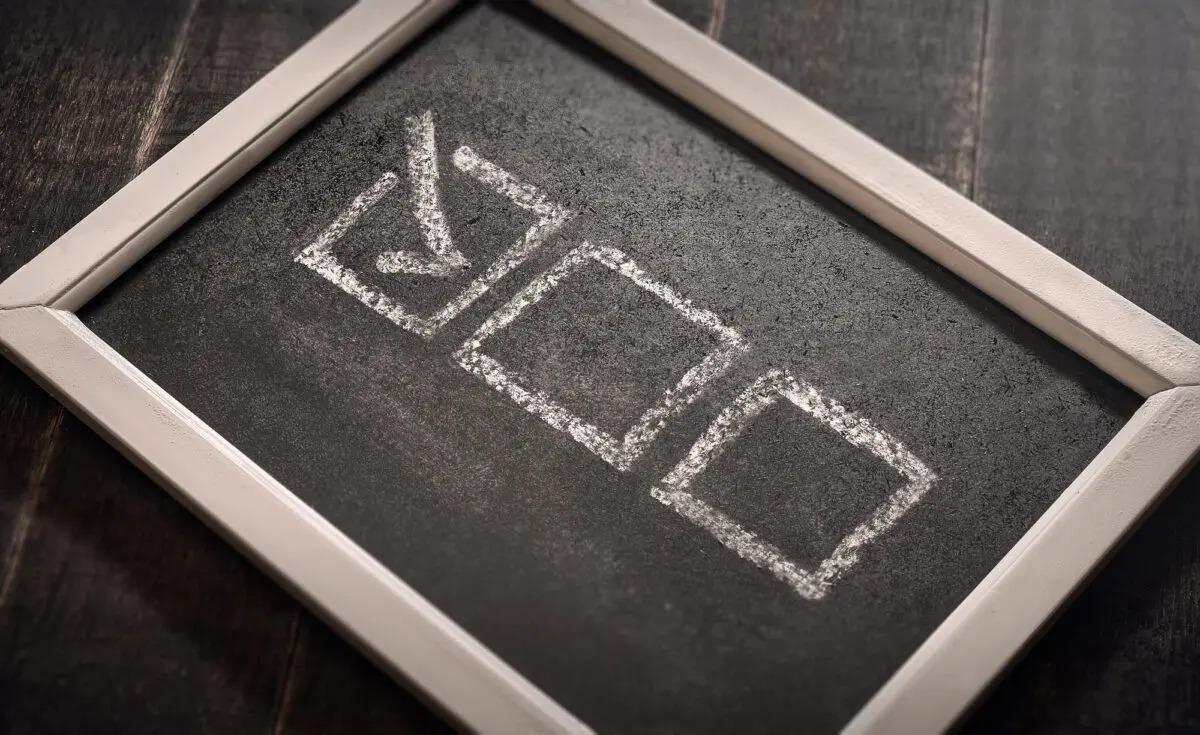
円満離婚のためには、離婚条件に応じた交渉準備(例:相手の財産の調査、証拠の収集など)が必要なのはこれまで説明したとおりです。
さらに、後悔のない「円満離婚」のためには、次の2つの準備を行っておくとよいでしょう。
- 離婚後の生活の目途をつける
- 離婚問題にくわしい弁護士に相談する
それぞれ説明します。
(1)離婚後の生活の目処をつける
離婚後は、夫婦それぞれが自立して生活しなければなりません。
離婚に踏み切る前に、次の3つ目途をつけておく必要があるでしょう。
- 経済的自立の目途
- 住まいの目途
- 離婚時に必要なお金の目途(弁護士費用、引っ越し費用など)
具体的にどういった準備が必要なのかを説明します。
(1-1)経済的自立の目途
これまで夫婦で協力して生活していたものを、離婚後はそれぞれで生活していかなければなりません。
配偶者から養育費や慰謝料がもらえるから大丈夫と思われているかもしれません。しかし、離婚に向けた話し合い次第では、あなたが期待しているよりも低い金額になる可能性もあります。また、養育費がもらえたとしても、途中から支払いが滞ってしまうということも少なくありません。
離婚に踏み切る前に、経済的自立の目途を立てましょう。
(1-2)住まいの目途
離婚したのであれば、夫婦別々に居住するということを考えている方も多いと思います。
しかし、実際は、離婚が決まった後に探そうとすると、転居先がなかなか見つからず、離婚しているにもかかわらず、仕方なく夫婦で同居を続けているという方も多くいらっしゃいます。
離婚後、夫婦で別居したいと考えている人は、離婚に踏み切る前に、住まいの目途は立てておきましょう。
さらに、子どもがいる場合は、子どもの学校や保育園を決めること、また、子どもが安心して育つことができる環境を整えることも考えなければなりません。子どもは急に環境が変わってしまうことに不安を覚えるかもしれません。子どものことも考えながら、住まいの目途を立てましょう。
(1-3)離婚時に必要なお金の目途
離婚には、別居の際の引っ越し費用、転居先の家具家電費用など、お金がかかるものです。弁護士に依頼することになった場合、弁護士費用も必要になります。
離婚に踏み切る前に、少しでも多くのお金を貯めておきましょう。
(2)離婚問題にくわしい弁護士に相談する
離婚に向けてどういう準備が必要なのか、離婚手続きの流れについて知りたい方は、離婚問題にくわしい弁護士に相談しましょう。
離婚に必要な準備事項は人によって異なります、周りから見聞きした話があなたにも当てはまるとは限りません(子どもの有無や収入状況、財産状況、不貞行為の有無等)。
離婚に向けた話し合いをスムーズに行うために、話合いの前に、離婚に必要な準備事項や離婚手続きの全体像を把握しておくのがおすすめです。
前もって弁護士に相談しておくことで、離婚が話し合いでまとまらず、もめることとなったとしても、その時点で弁護士を探さなくてすみます。準備不足や対応漏れで後悔することのないように、別居や離婚の話を切り出す前の段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
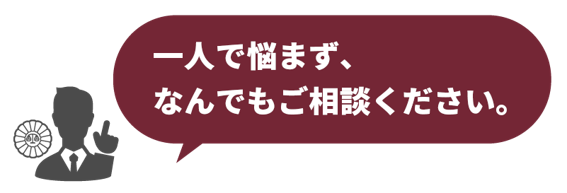
離婚条件の話し合いがまとまったら、公正証書の作成を!
離婚条件の話し合いがまとまったら、離婚協議書を「公正証書」として残すことがおすすめです。
「公正証書」とは、中立公正な立場である公証人が作成する公文書のことをいい、公証役場という公の機関で作成されます。
離婚協議書を公正証書として残しておくメリットは次のとおりです。
- 公正証書は、公証人や証人が立ち会いのもと作成されるため、離婚後に相手から「勝手に作られた」「サインした覚えはない」などの言い逃れをさせないことができる。
- 公正証書は、公証役場で原則20年間保管されることが決められているため、汚したり、紛失したりするリスクがない。
- 強制執行受諾文言があるのに金銭の支払いがない場合には、裁判所の判決を待つことなく、すぐに強制執行(例:給料や預貯金を差し押さえる)ができる。
特に3つの目の強制執行がすぐにできるというのは大きなメリットです。
もし離婚後合意した養育費や慰謝料の支払いがなかったとしても、公正証書を作成しておけば、すぐに相手方の預金や給料を差し押さえることができます(公正証書がなければ、裁判を起こして、裁判所の判決が出て初めて、強制執行することになります)。
離婚協議書を公正証書にすることで、後々の紛争を防止することができます。
離婚後に平穏な生活を送るためにも、離婚協議書は、公正証書にしておきましょう。
【まとめ】「円満に離婚を進めたい」とお悩みの方は弁護士にご相談ください
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「円満離婚」に向けた2つの心構え
- 円満な離婚を目指すあまりに離婚条件を妥協するのは、禁物
- 離婚条件について、配偶者の意思も尊重する
- 離婚に向けて話し合うべき5つの離婚条件とその交渉のための準備
- 財産分与→話し合う前に相手が持っている財産の整理をしておくこと
- 年金分割→年金事務所に相手の年金情報の提供請求をしておくこと
- 慰謝料→不倫やDVの場合には証拠を集めておく
- 親権、子の戸籍→親権を得るためには、養育環境を整えておくこと
- 養育費→養育費の目安額を知るために相手の年収などを調査しておく
- 円満離婚をするためにしておきたい2つの準備
- 離婚後の生活の目途をつける
- 離婚問題にくわしい弁護士に相談する
- 離婚条件の話し合いがまとまったら、離婚協議書を公正証書で作成するのがおすすめ!
「円満離婚」を成立させたい場合には、早くから、離婚準備や離婚手続きの全体像を把握し、交渉ポイントのアドバイスを得ておくことが重要です。離婚問題にお悩みの方は、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。
弁護士に相談・依頼すると、「大ごとになる」「揉め事になる」とのイメージをお持ちかもしれませんが、実は、弁護士に相談した方が、感情的な話し合いにならず、冷静な話し合いができるため、双方に納得がいく形での離婚が実現できる可能性があるのです。
アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)
また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。
離婚についてお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。